千々和至編著『日本の護符文化』弘文堂、2010年
「おふだ」を抜きに日本の庶民文化は語れない。火災除け、泥棒除け、神社の神札、お寺で祈祷された「おふだ」、蘇民将来の「おふだ」、御守りも中身は「おふだ」である。最近、六波羅蜜寺の空也踊躍念仏の報告をしたばかりであるが、最後に御守りをもらったのを財布に入れてある。
京都の町家に入ると、とくに帰りに靴を履くときに戸口を見上げると「おふだ」のオンパレードであることに気がつく。神様仏様のご加護を求める町家の暮らしがそこに残っている。地域によって組み合わせが異なることも確認している。
『日本の護符文化』は國學院大学と国史学会とが共催した国際シンポジウム「護符、牛玉宝印研究の現状と課題ー日本のおふだ文化」(2004年)が主な元になっている。
第一部 護符とは何か
この概論を読むと護符の混沌具合が分かるとともに、問題意識を持って臨まなければ眠気に勝てないことに気がつく(笑)。神符(しんぷ)と護符(ごふ)はどう違うのかとか、発行主体の話に行き着くことになる。
第二部 海を渡った日本の「おふだ」
護符は使われて焚き上げられてなくなってしまうが、外国人にはその文化がないため、海外に貴重なコレクションがある。B・H・チェンバレン、アンドレ・ルロワ=グーランそしてベルナール・フランクのコレクションが紹介される。ベルナール・フランクの『日本仏教曼荼羅』(藤原書店、2002年)など気になっているが探せていない。
第三部 寺院の護符と神社の護符
宮家準氏の稲荷信仰の展開と護符で改めて、稲荷が気になった。神道の稲荷(伏見稲荷)、曹洞宗の稲荷(豊川稲荷)、日蓮宗の稲荷(最上稲荷)などの歴史を抑えておきたいと思う。
第四部 護符の調査とその成果
機械印刷に変わり、もう手刷りしていない護符版木の拓本が情報として有用なのが分かった。年輪まで写しとるのが凄い。
第五部 座談会「日本の護符文化」
あとがきを読むと千々和至氏が、この出版の原点と位置づけている。したがって、これを読んでから第一部を読まないと、いきなり各学問分野の定義の羅列に面食らうことになる。
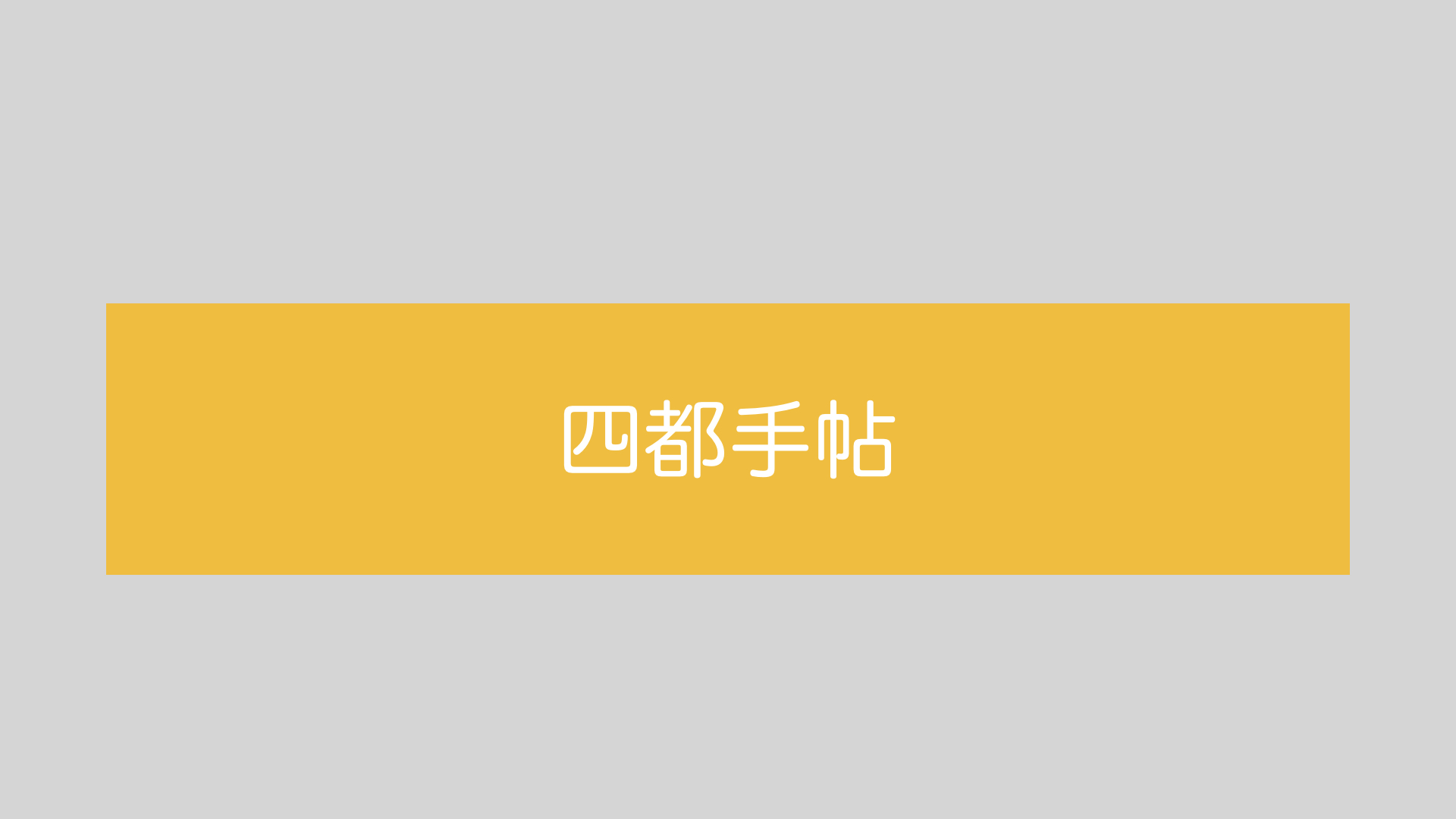

コメント