柳田國男『退讀書歴』書物展望社、1933年
限定1,000部、第629號
いつだったか、齋藤昌三の装幀本を紹介する機会があればと書いた。柳田國男の『遠野物語』に刺激されて、この本を引っ張り出してきた。
天金でつゞれ織りの装幀で立派な本である。しかし、残念なことに紙魚にやられてボロボロである。扉の付け根の痛みも酷い。齋藤昌三が『退讀書歴』の装釘に就て書いてあるのをメモしておく。
内容は土俗研究の權威柳田先生の文稿であるから、本文も實は和紙をとも思はぬことはなかった。然し印刷上和紙では安心が出來ないので、一般出版物には使用しない上質紙を選み、外装には特産品を材料にするつもりでゐたが、本文刷りとの調和と堅牢を主とする本社としては、結局國産の織物を選むことにして、特に山形米澤産のつゞれ織りを試用した。
このつゞれ織りは、米澤の誰も一般的に産出するものではなく、冬期の室内手工として極めて少數の出鱈目縞である。従って二反と同一の模様なく、又大量の生産は不可能な一種の土俗品であるので本書には幾分の調和を保てることゝ信じた。
本來なら一應著者にも御相談すべきであるが、なまじつか先生に見せぬ方がよからうと勝手に装幀したもので、著者並に讀者に不滿の點ある場合は拙者の責任である。
齋藤昌三の傍若無人振りが出ている説明である。
さて、柳田國男が讀書術雜談を書いていた。
「一代前の讀書子は氣樂なものであつた。學問が大體に共通で、人の讀みさうなものを勉強して、殘らず讀んで置けばそれでよかつたのである」(P210)。
學問といえば經學が中心の頃の話である。しかし、柳田國男は1875年生まれであるから、一代前というのは誇張であろうか。『論語』では學問を問うがその内容は経綸の學である。私も學問とはそういうものだと思っていたが、『論語』は士大夫の為に編纂された問答集であることが分かって、離れたのである。國民として普遍的に學ぶものは何かあるはずと思い、本を探したが、未だに見つけていない。
柳田國男が「書目の學問の日本では根つから當てにならぬことである。古書の新發見といふことが、これからも尚續くらしいことである」(P213)と云う。
書目の學問とは目録學のことであろう。印刷が発達した近世より板本がどのくらいでたのか分からないが、學問をするために讀むに値する本を題名で見分けることは難しいと書いている。解題の必要性に言及しているのである。
自衛策は「つまらぬものを讀まされぬ用心に、途中で放棄する習慣をもつと養つて置く必要が寧ろ有る」(P211)ということらしいが、これができれば苦労はしない。
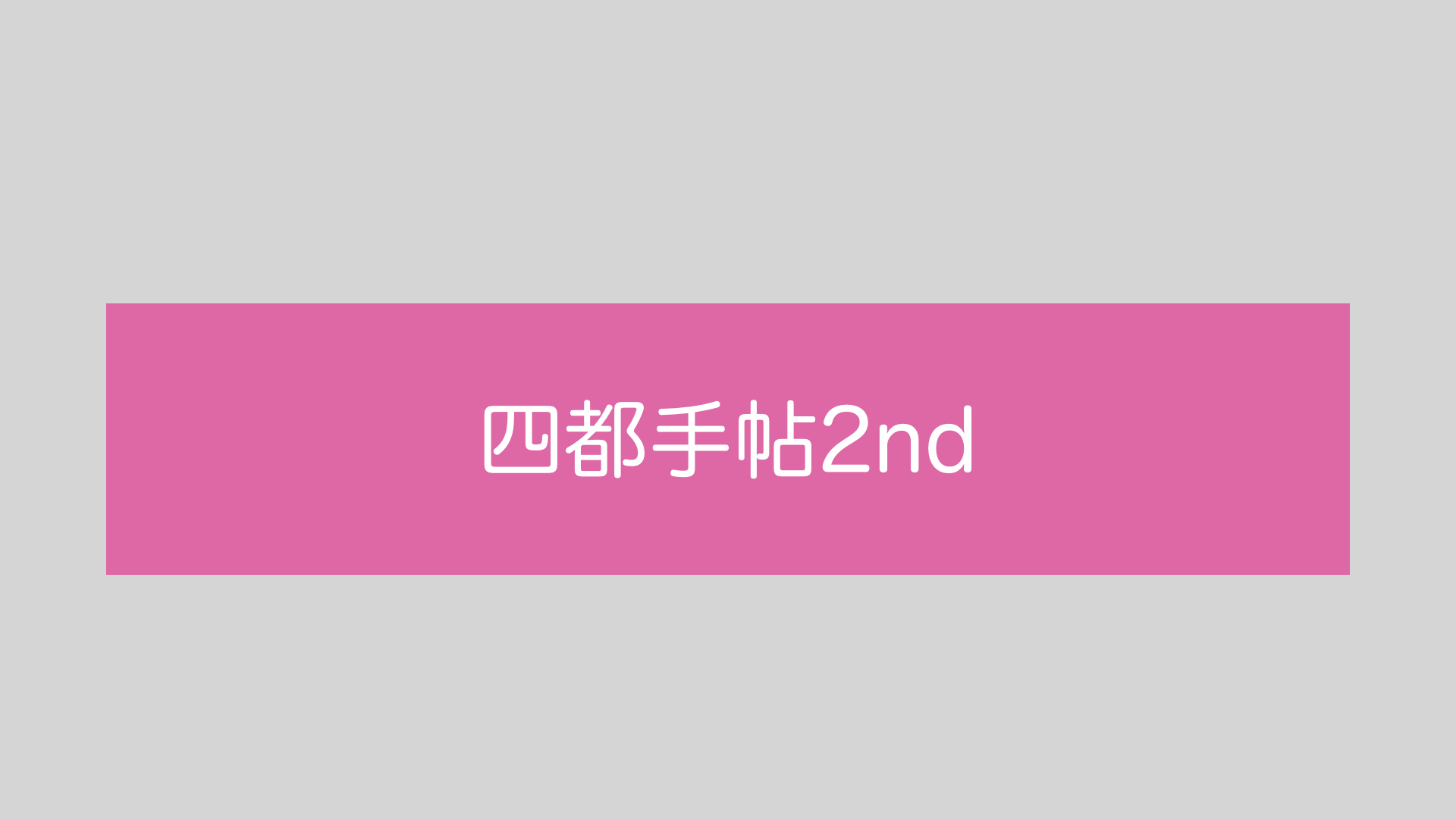

コメント