若松英輔氏が「NHKこころの時代~宗教・人生~ それでも生きる旧約聖書「コヘレトの言葉」」の第3回「すべての出来事に時がある」の中で、唐木順三の言葉を引用していたのでメモする。
『詩とデカダンス 近代における芸術の運命』の最後、四 考え、待つということ
ラジオやテレビは便利であるが、その言葉は待ってくれない。書物はラジオ、テレビと違っていくらでも待ってくれるとした上で、断片化された生は人間らしくないと批判する。
「真に人間らしい人間とは、奥行のある人間のことである。人間は華の如くに弱い、いささかの風にも倒れ伏すだろう、然し人間はみずからの弱さを知るが故に何物よりも強い、といったのは パスカルだが、自己自身の生身を自覚する高次の知性、叡智をもつこと、有限な人間でありながら、無限永遠のものとのかかわりあいをもつことが、ここにいう奥行のあるということの意味である。人はパンのみにて生くるにあらず、ということは、永遠のいのちとのかかわりあいにおいて生くるということであろう」(P251)。
「現在の自己を、永遠という広く深い背景において思い、自己の周辺を永遠とのかかわりあい、すなわち運命において思い、自然をもその背景における同類として思うということが、奥行の内容といってよい。このとき、自己も人間も、また自然も、断片ではなくなるだろう」(P251)。
そして、「待つ」ことの重要さを強調する。ここではギリシャ語のクロノス(時間)ではなく、カイロス(瞬間、永遠)の訪れを「待つ」こと、カイロスは過ぎ去っても私たちの中で深く刻まれていく。
「ところで「待つ」ということにはかなりの緊張と心の修練が必要である。たえず自分の問題を考えつづけているという状態が必要なのだが、今日来るか、明日来るかという待ち方は、実はほんとうに待つのではない。むずかしくいえば、待たないように待つことが、待つことの極意である。緊張して待機するというのと違って、いわば等閑に待つのである。時が熟し、時節到来するのを、待たないように待つというのが、修行というものであろう。訪れるもの、よびかけて来るものは、いつ来るかわからない。そのいつ訪れるかわからないものが、いざ来たという場合、それに心を開き、手を開いて迎え応ずることのできるような姿勢が待つということであろう。邂逅という言葉には、偶然に、不図(ふと)出会うということが含まれていると同時に、その偶然に出会ったものが、実は会うべくして会ったもの、運命的に出会ったものということをも含んでいる。そういう出会いのよろこびは、それを自身で味ったひとでないと解しがたく、伝えがたいであろう。
研究のため、資料を整えるための古典の渉猟と違って、古典に真に出会うことが、その古典を自分自身の古典とするということであり、自分一人にとっての古典をもつということが、人生の大きな幸福というものであろう」(P253-254)。
注)
唐木順三『唐木順三ライブラリーⅡ 詩とデカダンス 無用者の系譜』(中公選書、2013年)
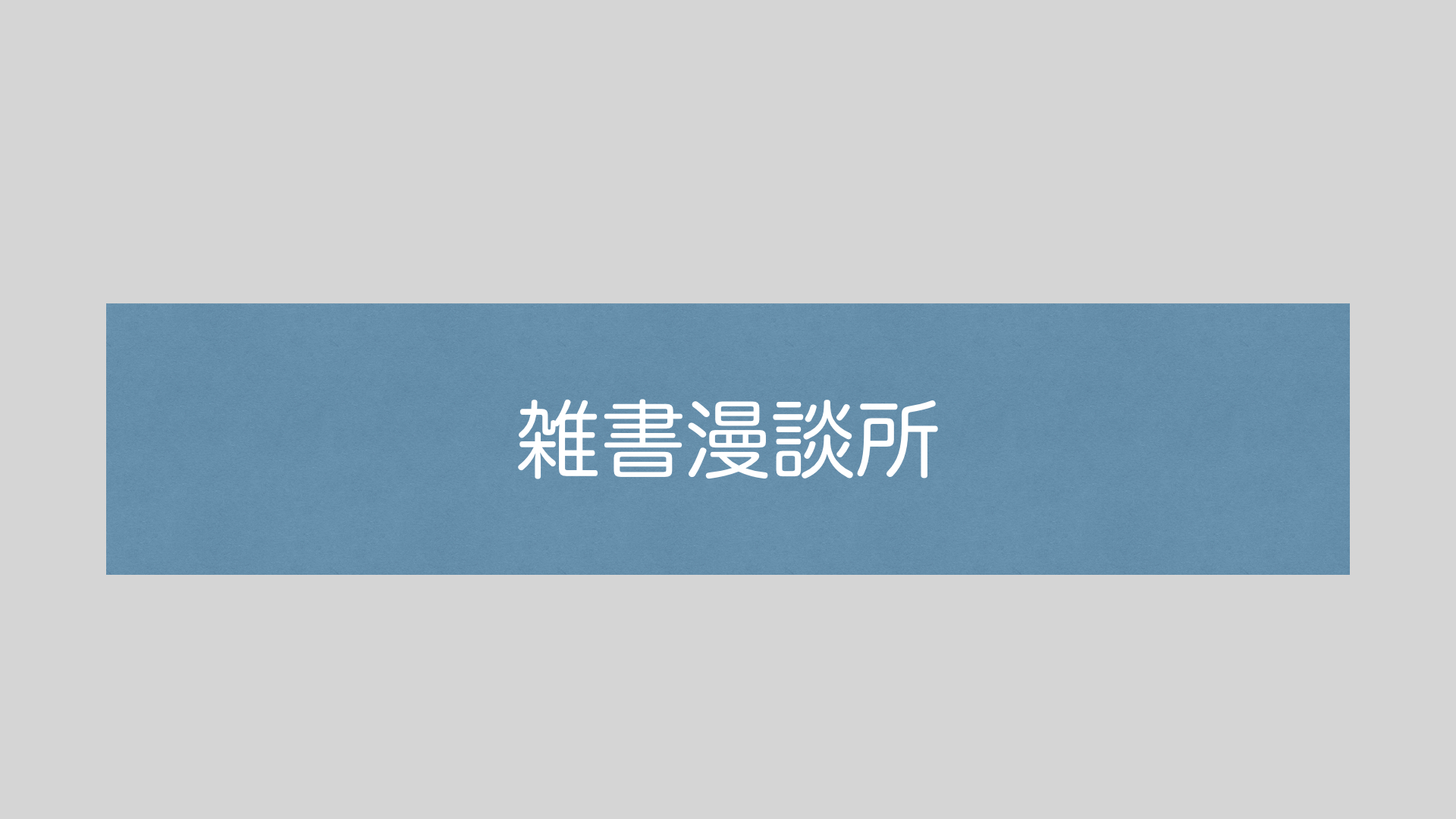

コメント