近藤義郎『前方後円墳の時代』岩波文庫、2020年
書誌情報
本書は生前に近藤義郎が『前方後円墳の時代』(日本歴史叢書、岩波書店、1983年)の増補改訂版を念頭に書き込みした初版本を底本にして文庫本にしたという。その辺りの経緯は「文庫版編集にあたって」を澤田秀実氏が書いている。
本の腰帯は不思議なものである。宣伝に使われるが著者は関与していない。「〈階級社会〉はいかに生まれたか?」とくれば巨大な建造物が造られた背景を知りたくなるではないか。古墳時代として習った身としては、『前方後円墳の時代』という区分は面白いと思った。考古資料だけでどこまで言えるのかも興味があった。しかし、戦後マルクス主義歴史学の影響を受けた階級社会論という砂上の楼閣であったらつまらないとも思った。そんなわけで春に出た本を手にしたのは夏であるが、読むのは秋になった。
解説の下垣仁志氏は近藤義郎の『蒜山原』(岡山大学医学部第2解剖学教室内人類学考古学研究室、1954年)を小学3年生の冬に読んで、古墳に強い興味をもったという。近藤義郎が発掘した蒜山原(ひるぜんばら)の報告書との出会いがその後の人生に影響を与えることになった。これほどの本の解説を書くのは相当な縁がないと難しいだろう。
「このだび近藤先生の代表作の解説を担当させていただくことを、まことに光栄と感じている」(P522)。
下垣仁志氏の解説を二度読んでよくできた解説だと分かった。近藤義郎の方法論と戦後マルクス主義歴史学との葛藤が見えてきた。普通は前方後円墳という巨大建造物の出現が階級社会の始まりと見るのであるが、近藤義郎は「国家および階級社会の出現が前方後円墳の廃絶をもって画される」(P537)と論じたのだという。しかし、本書の目次をみる限りでは「階級」や「階級社会」という用語が使われていない点でも近藤義郎の立ち位置が見えてくる。
準備が整ったようである。弥生時代から前方後円墳という厚葬の終わった7世紀までの全13章487頁の旅(参考文献や解説まで含めると539頁)に出ることにしょう。
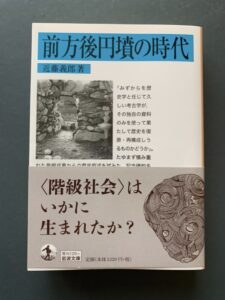
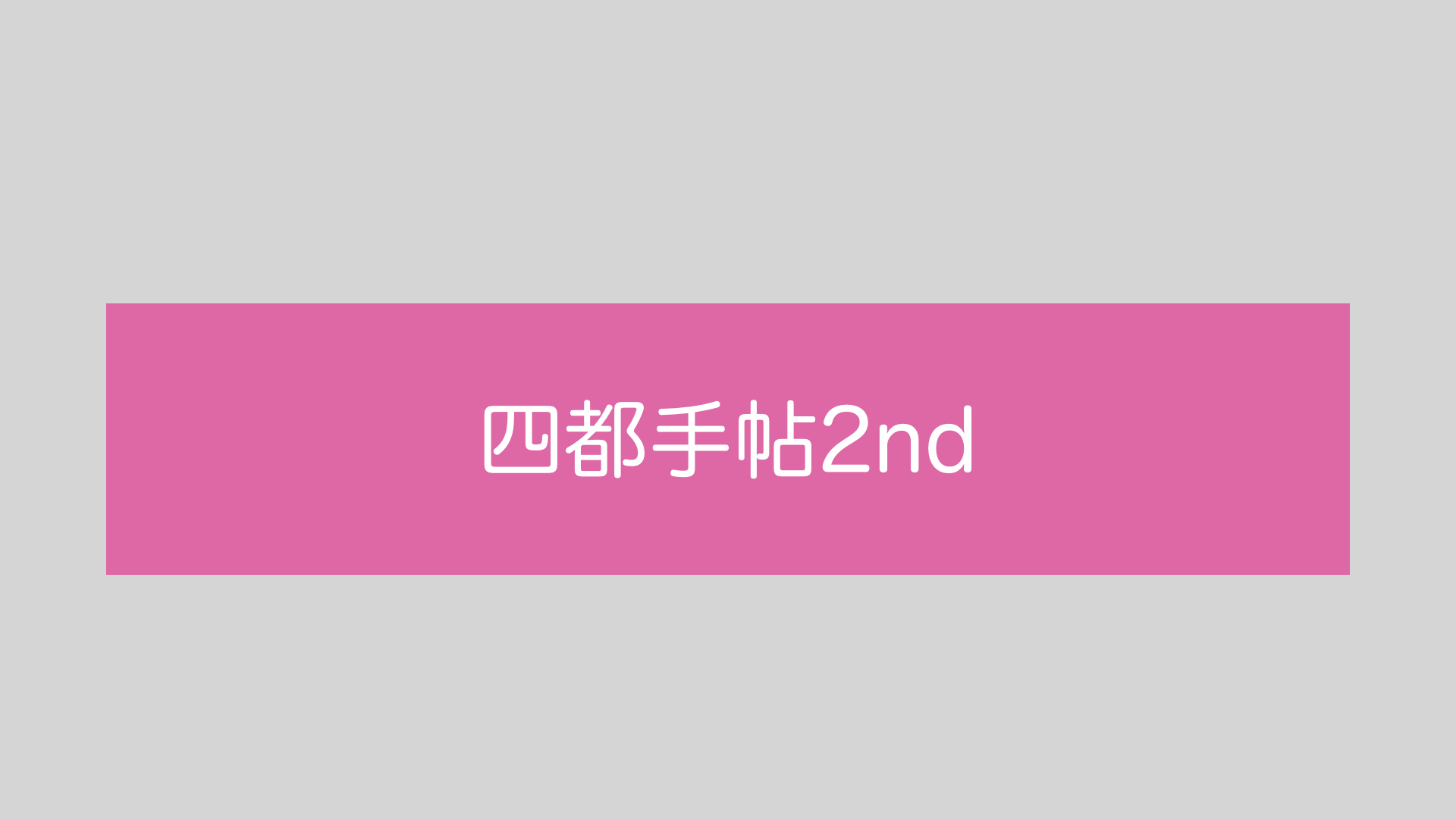

コメント