宮崎市定『古代大和朝廷』ちくま学芸文庫、1995年、2010年第3刷
タイトルからして、東洋史の専門家がなんで日本の大和朝廷のことを書くのか不思議だった。しかし、序を読めばそれは不明なことだと分かる。
「日本の学界では、東洋史と日本史との分業が判然と区別されているので、東洋史に籍を置く私は、別に日本史に関わる義務な初めから無く、そこへ口出しすることは、むしろ余計なお節介として煙たがられるくらいが落ちである。しかし実際には日本史は東洋史と本質的に続きあっていて、途中で切断することができぬ場合があり、特に私が日本人である以上は、専門外だからと言って捨て去るわけに行かぬ」(P007)。
解説を読むと「裃を脱いだ雰囲気が漂っている」(P359)と礪波護氏が書いていた。まあそんなものかということで、内藤湖南の弟子の日本史論も面白かろうと読むことにした。古代大和朝廷のことだけを書いているのではなく、テーマはばらばらであった。宮崎市定の『中国古代史論』(平凡社選書、1988年)と一対として『古代大和朝廷』(筑摩叢書、1988年)が出版された。
「出雲政権の興亡」は荒神谷の遺物の整然とした並べ方から商品だったとし、出雲が交易の拠点だったという話だった。出雲に八百万の神々が集うのは商業の殷賑を物語っていたのだという。青銅器に関してさもありなんと思うが、論証不可能なテーゼで困る。確かに松江の博物館で銅剣の出土の写真を見たとき、昔の農業市を思い出した。神社の境内に農耕具の市が立って、賑わっていたのを見た記憶がある。しかし、そんなことをいう学者は他に知らない。交流があったという言い方はされたけれども、商売という人はいなかった。だから新鮮に思えたけれども、少し踏み込み過ぎだとも思った。
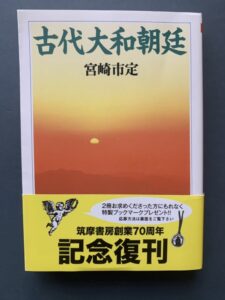
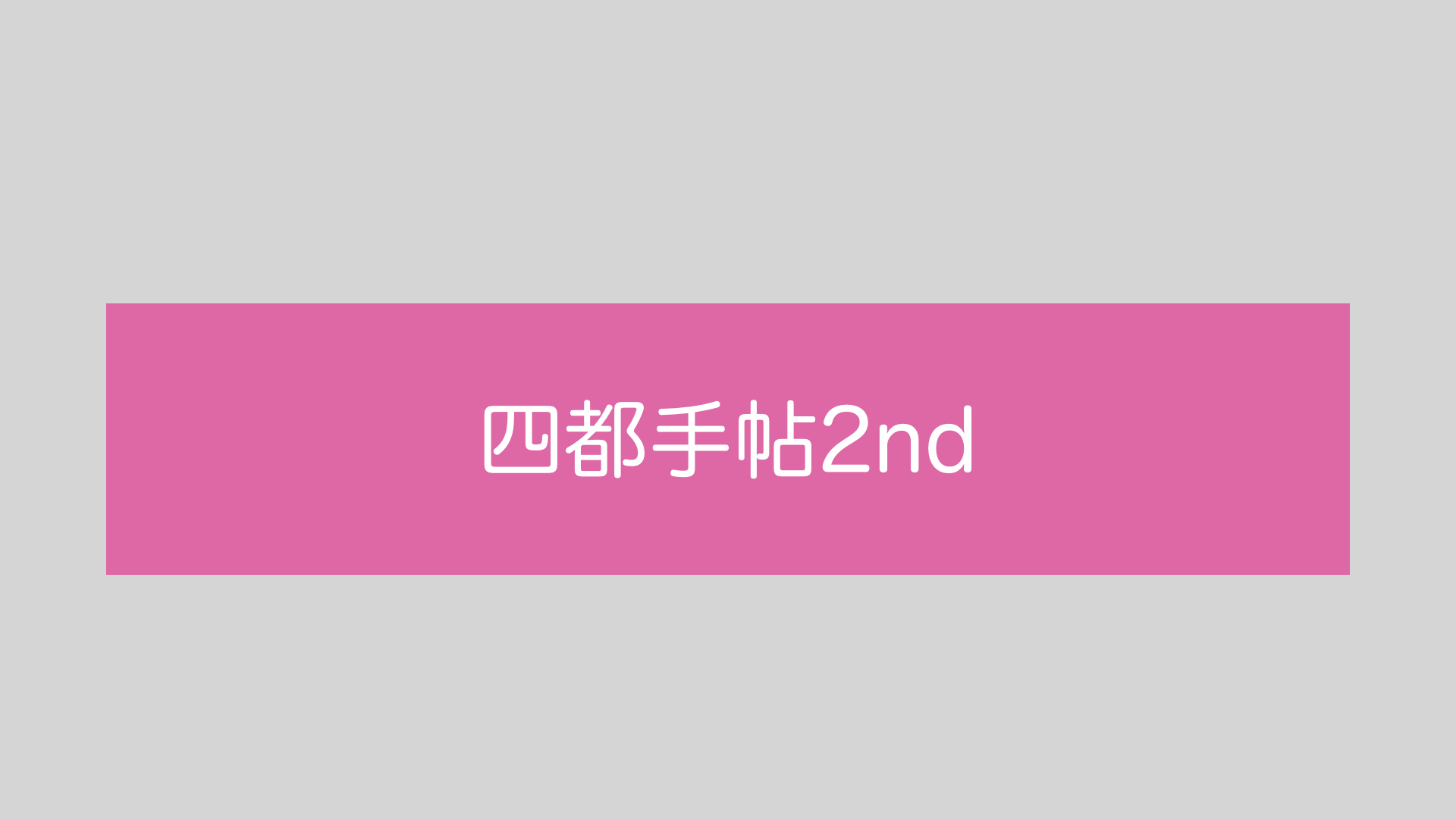

コメント