ケン・オールダー、吉田三知世訳『万物の尺度を求めて メートル法を定めた子午線大計測』早川書房、2006年
二人の天文学者が優秀な助手を伴い、観測機器を載せた馬車で、パリから南北に出発した。
ジャン-バティスト-ジョセフ・ドゥランブル(1749-1822)が1792年から99年にかけての子午線観測ミッションで、その北半分を担当した天文学者
ピエール-フランソワ-アンドレ・メシェン(1744-1804)が1792年から99年にかけての子午線観測ミッションで、南半分を担当した天文学者
彼らの使命は、「ダンケルクからパリを通りバルセロナに至る範囲の子午線の長さを測定することであった」(P13)。
彼らの願いは、「将来世界中の人々が、地球を基準にした共通の測定単位を使うようになることである」(P13)。
彼らの仕事は、「この新しい単位、「メートル」を、北極から赤道までの距離の一千万分の一の長さとして決定することであった」(P13)。
フランス革命下の当時、彼らのミッションがいかに困難なものだったかは読まなくても分かる。むしろ、革命下の実態がどう描かれているか興味があった。彼らの日誌から、著者のケン・オールダーが再現して見せる。ケン・オールダーはハーヴァード大学で物理学を学び、歴史学の博士号を取得している科学技術史の専門家である。
「十八世紀の測定単位は、国ごとに違うだけでなく、国のなかでもまちまちだった。おかげでコミュニケーションや商業は滞り、国を合理的に統治することができなかった」(P13-14)。
「当時の推計によると、アンシャン・レジームのフランスには、約八〇〇種類の重さと長さの単位が使われていたが、同じ名称だが実際には異なっていた度量衡をきちんと区別すると、二五万種類という驚異的な数にのぼったという」(P15)。
近代国家として度量衡の統一が求められたは、「世界を合理的で一貫性のある方法で把握する」(P15)ためである。
しかし、皮肉なことに、「フランスはメートル法を生み出した国であるだけではなく、メートル法を拒否した最初の国でもあった」(P18)。
メートル法を庶民が拒否したのである。「ナポレオンは、惨憺たる結果に終わることになるロシア遠征の前夜、メートル法を中断してアンシャン・レジーム時代のパリ度量衡を復活させる」(P18)。「フランスがメートル法に戻るのはやっと一九世紀の半ばになってからのことであり、古い度量衡は二十世紀になっても使われつづけた」(P18)。
ここで、気になる記述に出会った。
「メートル法の核心に密かな誤りが存在するということだ。この誤りは、メートル法が正式に決定されて以降、これを定義しなおすたびに、訂正されることなくそのまま維持されてきたのである」(P18)。
著者のケン・オールダーが書いていることを確かめるために読書を進めることにする。
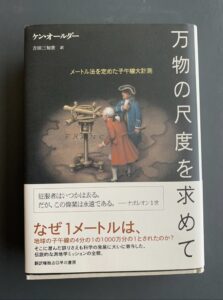
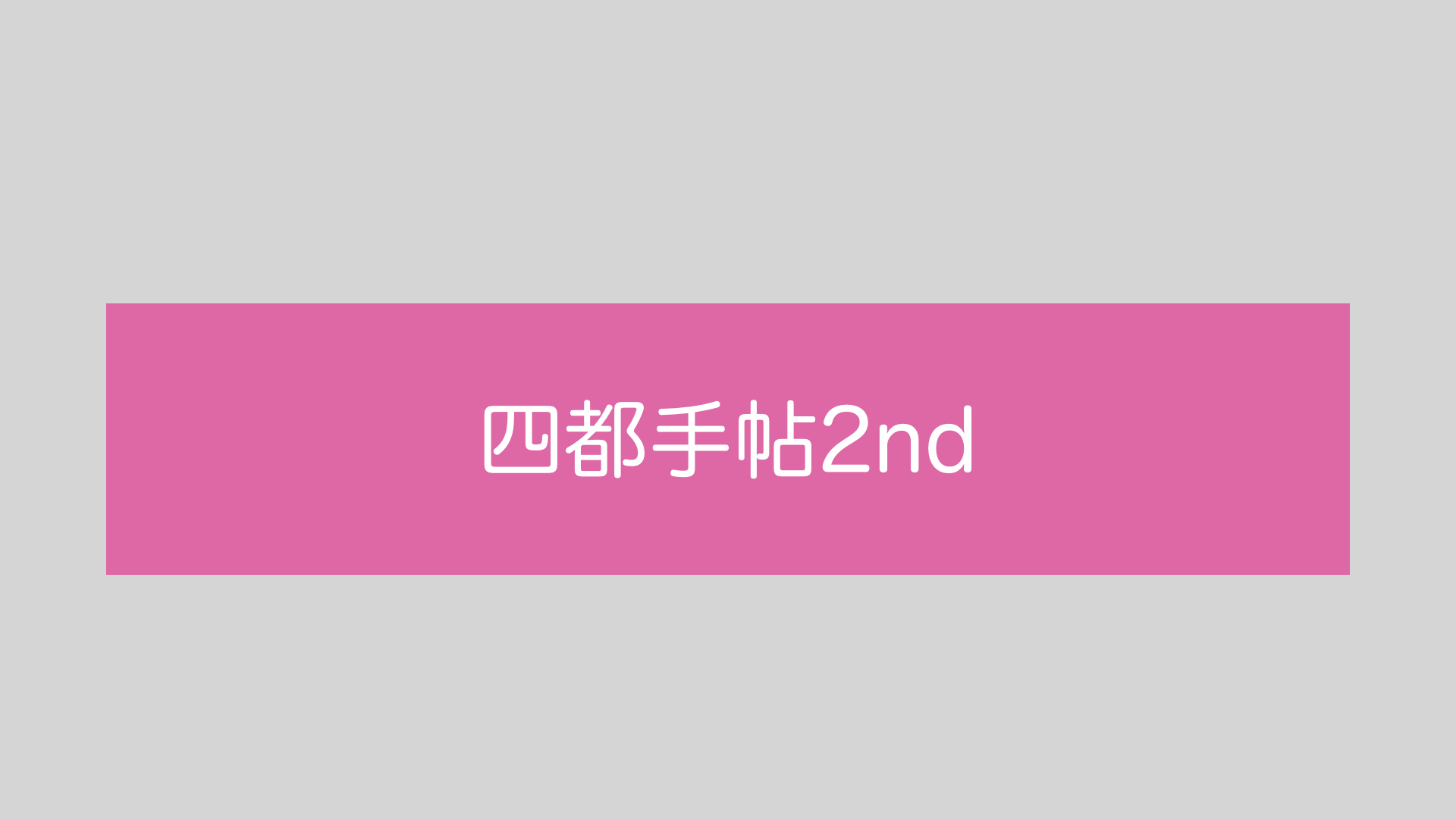

コメント