横田冬彦『日本の歴史16 天下泰平』講談社学術文庫、2009年、2014年第3刷
第七章 開けゆく書物の世界
江戸初期の知のネットワークの具体例を見ていこう。父親が福島正則の元を離れ大坂方につき敗死したため、母方の姓を名乗る三田浄久が各種の糟を肥料として販売することで商人として成功し『河内鑑名所記』を刊行するまでになった。これは河内の名所に俳人の句を載せた本である。
前句付とは何か
俳諧がどのように庶民の間に普及していったのか。俳諧はふつう句会を通じて行われる。中世から連歌が行われ、ルールによって句を継いでいくスタイルが確立した。俳諧の通信学習システムのようなものが江戸初期にはできていた。俳諧の師匠(業としての俳諧師)が前句の題を出し、これに弟子が付句をする。俳諧とは連句である。付句ができることが座に参加する資格である。この取りまとめを三田浄久が行う。糟の売り先である有力な農民はまた俳諧好としてお題に対し自身の句をつける。これを集めて清書して(清書所)師匠に送り、師匠が添削し、清書所にて回覧することで連句の基礎が学べる。
業俳の成立
こうした連中(れんじゅう)を取りまとめる有力な弟子を持てば、添削料が毎月入るので、俳諧師は業俳(ぎょうはい)となることができる。『河内鑑名所記』は三田浄久の師匠が何人も出句している。三田浄久の商売のネットワークであり、俳諧のネットワークが重なっているといえる。しかし、俳諧が大衆へ広まるとレベルも下がっていく。三田浄久は俳諧をやめることを子に言い置いて、2代目浄賢は漢詩文へ向ったのだったが、本書ではそれから先を追求していない。2代の蔵書が売り払われた事情は分からない。
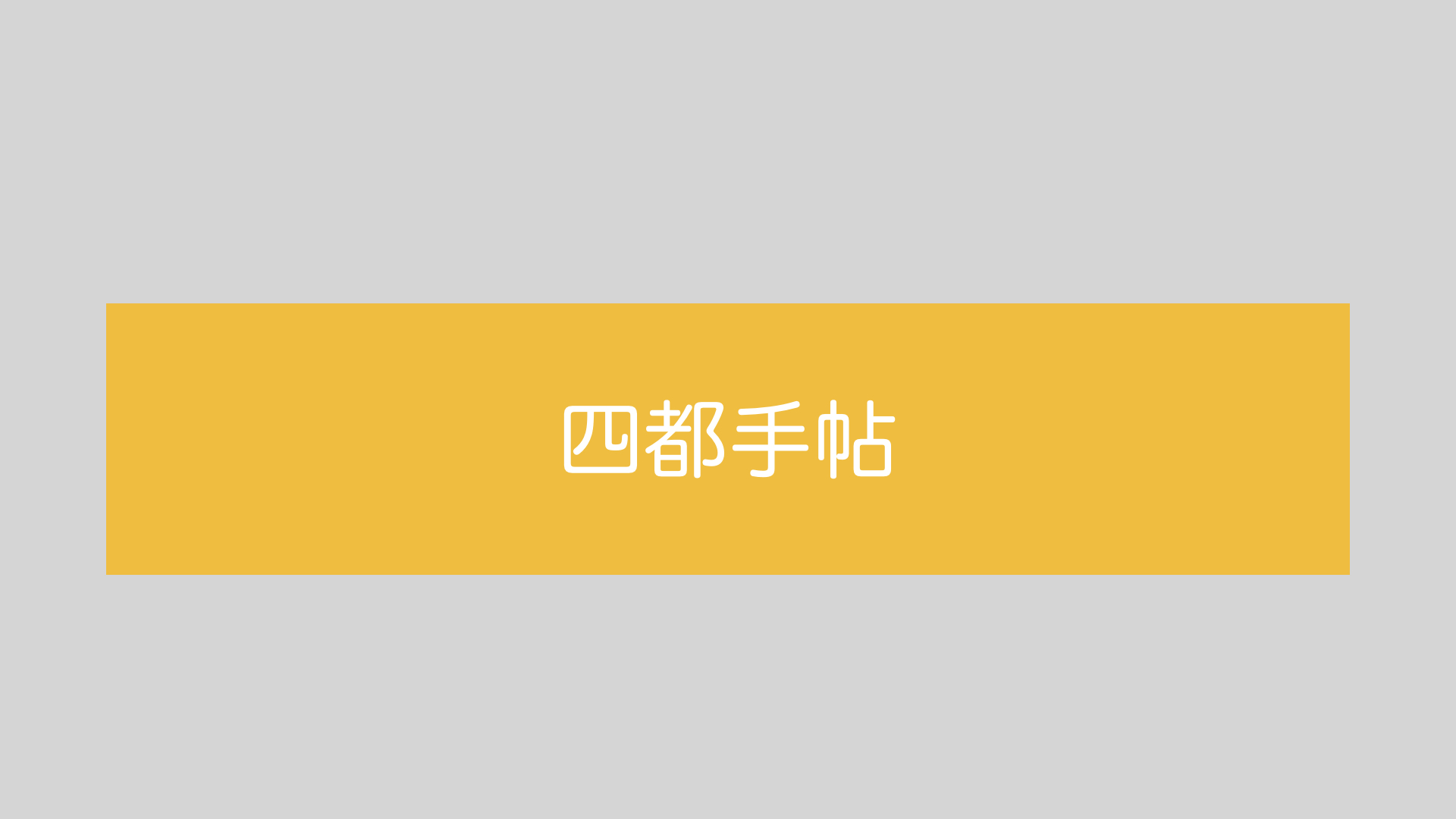

コメント