山折哲雄『『教行信証』を読む 親鸞の世界へ』岩波文庫、2010年
驚くということ
『教行信証』の二つの主題と一つの目的を山折哲雄氏は提示するが、それは後に回すことにする。まず、『教行信証』の時代背景が語られる。「すでに師の法然は念仏のみを選択すると宣言し、それを支持する民衆の輪が広がっていた。ややおくれて道元が出現し、「正法」の旗をかがげて坐禅の道を歩きはじめる。そして日蓮もまた「妙法蓮華経」の真実性だけが世の中を救うと主張して、「題目」の功徳を唱えるようになる」(pp.ii-iii)。
では親鸞は何を考えていたのか。「流罪以降の親鸞がどのようなことを考えていたのか、かならずしも明瞭な像を結んではいたいということだ」(p.iii)。
「その疑問に答えるためには、やはりかれの主著とされる『教行信証』を読み解くほかはないだろう」(p.iv)。
「その『教行信証』の本文に対面して、まず私が驚くのはその書名自体が作品の主題をまったく明示していないことだ」(p.v)。
本を読んで驚くということを暫く忘れていたような気がする。積極的に読むということ大切さである。漠然と文字を追っていけばいなされるに決まっている。相手は知の巨人である。こっちは何故何故責めをしてよいはずである。
「無常」と「無明」ということ
『平家物語』冒頭の「無常偈」と『教行信証』の思想的の根源対立を山折哲雄氏は言う(p.21)。「無常」について、親鸞は多くを語らない。「端的に言ってしまうと、親鸞の言葉づかいや文章のなかに「無常」という表現を見出すことがほとんどない、ということだ」(p.21)。「無明の闇」に立ち向かう親鸞に対し、寧ろ蓮如は『平家物語』の無常感覚を継承していると言う。それは「白骨の御文」を読めば明らかである。「無常の絶唱である」(p.29)と言っている。山折哲雄氏は無常観をめぐり親鸞と蓮如の断絶を言うのである。この断絶はどこから来ているのだろうか。
比較という手法
『教行信証』は挫折した本で、どこかの段ボール箱に眠っている。本棚に挿してあれば、また、引っ張り出したかもしれない。
比較は照合ではない。構造を明らかにするものである。『教行信証』と『古事記』の序の文末を山折哲雄氏は対比する。「西蕃月氏の聖典、東夏日域の師釈」と「「帝皇日継」(帝紀)、「先代旧辞」(本辞)」を対比し、そして「愚禿釈親鸞」と「正五位上勲五等太朝臣安萬侶」を対比する。
山折哲雄氏は親鸞が『古事記』を読んだかどうかを言っているわけではない。山折哲雄氏が『教行信証』の序を読むと『古事記』の序が念頭に蘇ると言っているのだ(p.9)。インド、中央アジア、中国そして日本という民族と国家を超える横断的なの思想世界の水平構造と高天原から豊葦原への天孫降臨の神話から歴史へという国造りの原理が垂直構造という形で非対照的な構造として浮かび上がってみえるという。
『教行信証』の内容に入る前に山折哲雄氏の読み方に圧倒されてしまった。
『教行信証』を読むための「見取図」
こうして、「『教行信証』の世界を読み解くための、さしあたっての私の見取図」(p.30)が示された。それは二つの主題と一つの目標であった。
「第一の主題が、「海上浄土」にたいするイメージと心情が大胆に語られているということだ。つづいて第二の主題が、父殺しの大罪を犯した人間ははたして救われるのか、という人間「悪」にかかわる問題だった」(p.31)。
「そしてこの二つの課題を、どのような目標につなげるのか、親鸞自身の生きる目標とどのように結びつけるのかということになる。それはひとえに「悪」を転じて「徳」を実現し、「信楽(信心)」の深まりによって「証」に至りつくためだ、と結んでいるーー不動の目標だったと言っていい」(p.31)。
しかし、この確信に満ちた「序」の中に親鸞のこころの揺れがあると山折哲雄氏は言う(p.32)。それは「顯浄土眞實教行證文類序」という序文の初めに「教行證」とあり、「信」が欠落しているのに対し、章には「信」、「眞佛土」、「化身土」が加わっているからである。「『教行信証』という作品を読み解くための重大な難所が横たわっている」(p.36)。
まだ、第一章 総序である。
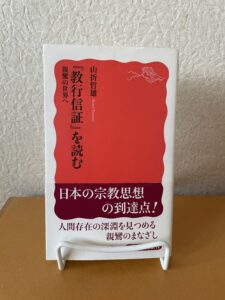
『教行信証』を読む


コメント