藤木久志『城と隠物の戦国誌』ちくま学芸文庫、2021年
書誌情報
『城と隠物の戦国誌』(朝日選書、2009年)をちくま学芸文庫とした。
民衆の危機管理の習俗
戦国時代に、「人びとは、どうやって家族を守り、家財を守ったのか。その世の現実を、見直してみよう」(P009)というのが著者の問題意識である。
「思えば、私たちの生きる現代もまた、「身構えた社会」そのものではないか。地震や水害の惨禍などのあいつぐ報道におびえて、いつしかわが家でも、三日分の水や乾パンや炭や七輪やトイレットペーパーなどを、密かに物置に用意している。
世界を覆う金融の危機、インフルエンザの恐怖、地球の温暖化がもたらす、得体の知れない環境悪化・・・・・・。
そのなかで「身構えた社会」「自分の身は自分で守る時代」の再来。それは現実であり、昔話でも、虚構でもない。(省略)戦国の村びとの危機管理はどうなっていたのだろうか」(P009-010)。
2004年新潟県中越地震、2008年のリーマンショック、2009年のインフルエンザパンデミック、2008年や2009年の記録的大雨。まだ、この後の東北地方太平洋沖地震(2011年)は起きていない。歴史学者が現代について中世社会に言及しているのである。そういえば鎌田東二氏も中世の到来と言っていたことを思い出した。
藤木久志氏は城郭の役割を中国、西洋との対比で考える。城郭は「中国古代には、領主の「城」と民衆を保護する「郭」とを合わせた、城と郭との二重構造(内城外郭式)をもった「城郭都市」」(P016)であった。
要するに城は民衆の避難場所ではないかと。しかし、遺構から実証するのはなかなかに難しい。
また、銭などを穴に埋めて隠すことも広く知られていた(隠物(かくしもの))というが、敵が去ればまた掘り出してしまうので考古学的に説明するのは難儀だ。銭が穴に残ったままだと「信仰の呪術」(橋口定志)と説明されたりする。しかし、戦国社会を考えれば、こうした危機管理がないはずがないのである。
解説で千田嘉博氏が以下のように結論した。
「検討してきたように、本書が示した個々の城や遺構の解釈には、再検討が必要である。しかし著者が解き明かした民衆の危機管理の習俗の意義はゆるがない。本書は戦国史をとらえ直した名著である」(P281)。
藤木久志氏の本を読み直したくなった。研究所には結構あるのである。ただし、藤木説への批判を押さえているわけではないので、読み返して得られる利益が大きくなる時を考えなければならない。専門家ではないため、歴史本との付き合い方は難しいのである。
注)鎌田東二『世直しの思想』(春秋社、2016年)
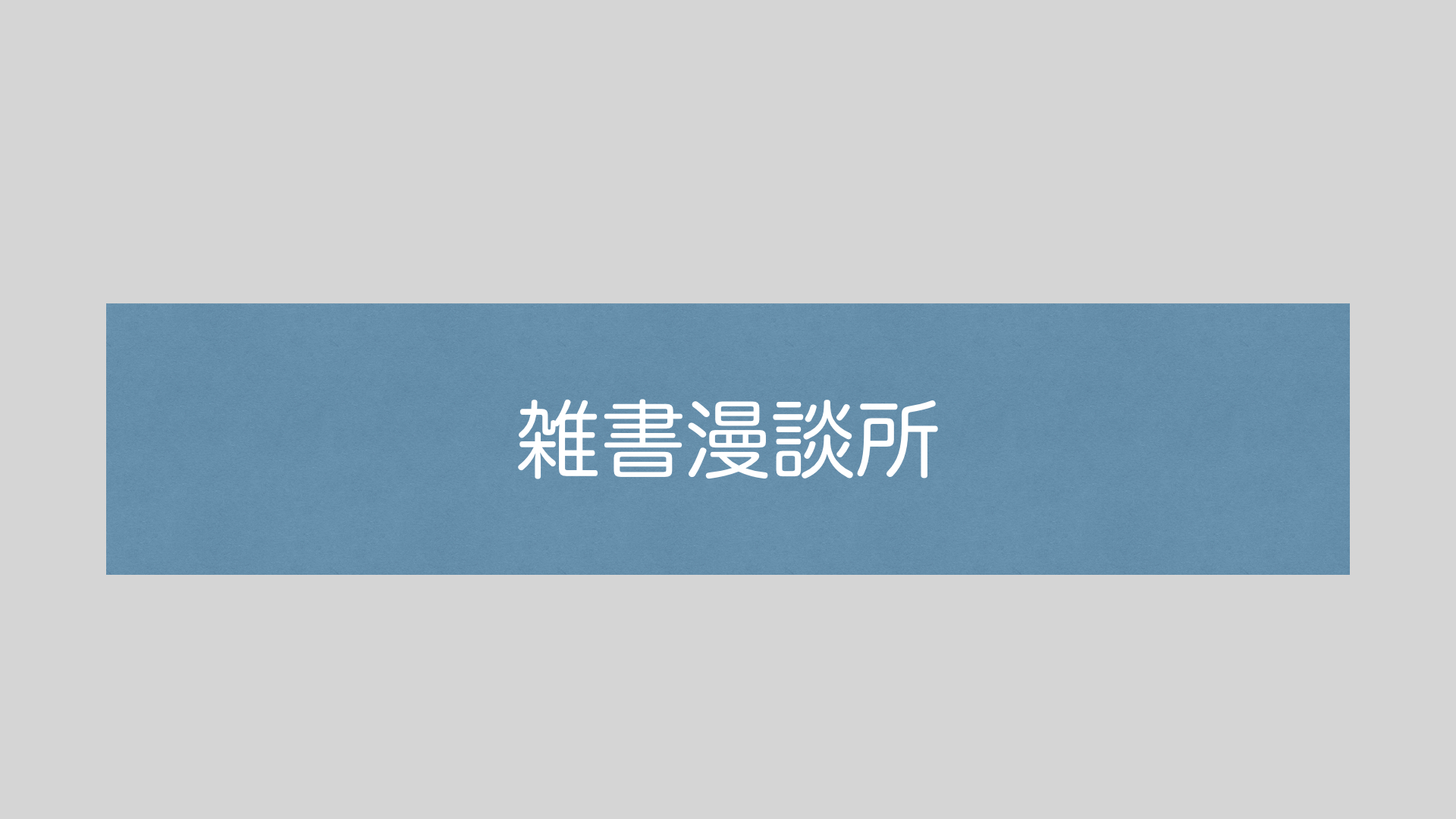

コメント