前田真三『奥三河』グラフィック社、1985年、1991年第6刷
奥三河という場所の範囲は様々だという。四季を撮した写真集を見ると失われた日本の風景という言葉が浮かんでくる。
序で色川大吉氏が書いている。
「今度の作品集は何の変哲もない『奥三河』を取りあげたものだけに、いっそう大胆な作家の新しい意図を感ずる。奥三河は豊川、天竜川水系の奥、南信濃や駿河と境を接する山また山の辺境である。そこには日本一人口の少ない村もあれば、七百年来の神事芸能を伝える花祭りの古俗もある。それほどに近年までは陸の孤島の一つであった。その地に前田さんは、ここ数年、足しげく通われた。なぜであろうか」。
あとがきで前田真三は奥三河の知人宅へ通ううちに「そこに日本の山村風景の原点のようなものが潜んでいることを感じとったからである」と書いている。
わずかに畑仕事をする人が写っているだけだが、前田真三からすれば風景写真に人は入らなかったから、ここでは人も風景の一部とみていたのだろう。
色川大吉氏が地元の民俗学者早川孝太郎の『花祭』(1930年)ついて書いている。「早川によると、この中世古来の神事芸能は修験道の影響が濃く、「山伏の一派かと思われる先達によって七年目ごとに三日三夜にわたって神の世界を現出したと伝えられる」その村々の共同による大神楽の祭りは、安政四年(1857)、今の豊根村字上黒川での行事を最後に中絶してしまい、今の花まつりはその後をひき継いだものだという」。
豊根村の上黒川に前田真三が拠点とした故熊谷賢一氏の家があった。写真集の表紙には国の重要文化財に指定された建築が雪に化粧されて写っている。
前田真三が花祭りを見て、写真を撮らなかったのだろうかと想像してみたが、前田真三はカメラを持たずに見入っていたに違いないと思うのだった。LINHOF SUPER TECHNIKAで動きのある花祭りは納まりはしないのだから。
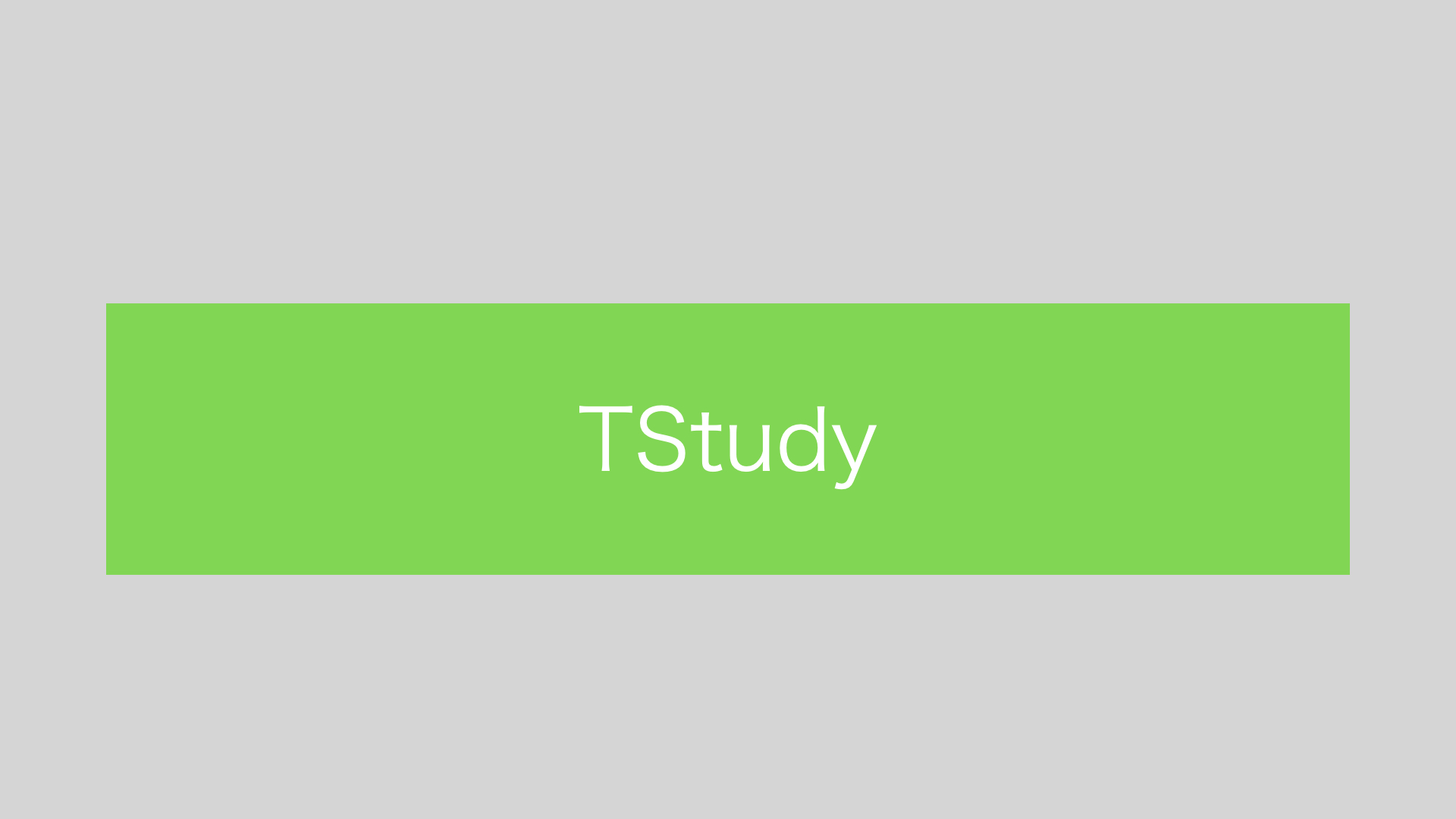

コメント