この本を読む人はどういう人だろうか。日本の中世の民衆世界を京都の西京(にしのきょう)の神人(じにん)を通じて論じる本を手に取るきっかけは何だろう。私のように著者の著作を何冊か読んでおり、どういうテーマで研究しているかをある程度知っていることで買うのであれば、特に理由はいらない。私は2020年10月購入図書の購入後記に書いたとおり、神人についてよく理解していなかったことで知りたくなったからである。それも現在に繋がる神人が西京神人というので読むしかない。
網野善彦氏の都市史研究に対して、三枝暁子氏は西京の農村的な要素を指摘し、網野善彦氏が年貢・公事を負担する「平民」と年貢・公事を負担しないが、特殊な技能を通じて公家や寺社に奉仕する「職人」との違いを論じたのに対し、三枝暁子氏は「麹業者という点においては「職人」としての要素をもちながらも、北野天満宮領の領民として年貢・公事を負担する「平民」でもあった西京神人に着目してみると、現実には「平民」/「職人という区分を相対化し得る中世民衆の実態のあったことが見えてくる」(xi)と書いている。
西京神人(じにん)が史料上に確認されるのは、「鎌倉時代後期の弘安七年(一二八四)の『勘仲記』八月四日条」(p.10)であるという。北野天満宮創建に関わって安楽寺天満宮創建が語られるが史料上の裏付けはない。
祭には祭費がかかる。北野祭と三年一請会(さんねんいっしょうえ)の祭費はかつて朝廷が負担していた。戦乱により執行できない状況になった。室町幕府二代将軍義詮は西京の酒屋、土倉へ一部賦課したという(p.58)。室町幕府三代将軍義満の時に西京神人に酒麹役(しゅきくやく)免除がされ、室町幕府四代将軍義持によって北野麹座として麹業の独占権を認められることになった。
この麹業の独占権に関する文書は北野天満宮にあるが、かつては安楽寺天満宮に保管されていたという。安楽寺天満宮は明治6年に上地令により北野天満宮へ移管されるまで、西京七保の中心的な神宮寺であった。神宮寺については、岡田精司著『京の社 神と仏の千三百年』(ちくま学芸文庫、2022年)を読んだのでピンときた。宮寺は重要な概念である。現在の安楽寺天満宮は北野天満宮より分祀し再建されたものである。北野七保にはそれぞれ神宮寺があった。安楽寺天満宮は一ノ保社であった。北野天満宮にある西京神人の関する古文書は安楽寺天満宮から北野天満宮へ移管されたものであり、西京神人は麹の製造・販売の独占権を失ってしまったが、その記録を大切に受け継いできたのである。
「近世においては、「町人」身分に位置付けられつつ、「神人職」として御供所を拠点に独自に祭祀を行うようになるとともに、瑞饋祭を発展させていく。そして近代には、「士族」となりながらも、神人職の身分はもとより御供所の所有も瑞饋祭の執行も、国家によって廃止、停止されてしまう。しかし明治期半ば以降、瑞饋神輿を再興し、さらに西ノ京七保概念を結成し、瑞饋神輿の製作と「梅花の御供」「甲の御供」の献饌という現代に通じる西京神人・西京住人による祭祀行事の基礎を築いていく」(p.715)。
瑞饋祭の見学を通じて西京神人の世界を覗き見していたことがわかった。そう思うと、西京七保の神宮寺の現在を確認してみたくなる。
この論文は公開されていないので、本を探して読むしかない。上記の論文で参照されていた。
高橋大樹(ひろき)「中世北野社御供所八嶋屋と西京」日次紀事研究会編『年中行事論叢―『日次紀事』からの出発』岩田書院、2010年
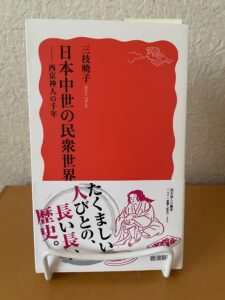


コメント