佐藤進一『新版古文書学入門』法政大学出版局、1997年、2013年新装版第7刷
本物との出会いを感じる本である。旧版のあとがきは昭和46年(1971)の日付である。入門書といっても素人である私は読むたびに打ち返される。今もって、本書を超える古文書学の入門書は知らない。しかし、古文書の範囲に関する定義や古文書学のあり方は古くなったと言われても仕方がない。
本書を読んでいくと、瑣末なところで気になる点がある。
例えば、寺社関係の文書について、「天台宗では青蓮院・曼殊院・三千院・妙法院・実相院・聖護院等の門跡寺院や、廬山寺・鞍馬寺・住心院等、いずれも平安ないし鎌倉時代以来の古文書を伝える」(P39)とある。
確かに、これらはかつて天台宗の寺院であった。
しかし、鞍馬寺は昭和24年(1949)までは天台宗に属していたが、鞍馬弘教総本山となっている。住心院は聖護院門跡の院家であったが、聖護院門跡が昭和21年(1946)に修験宗(現本山修験宗)となり天台宗門から独立したことに伴い本山修験宗である。佐藤進一が「天台宗では」と書いたのは天台宗の寺院がその古文書を伝えるという意味では厳密ではない。本書を著す時に天台宗の寺院ではなくなっている。
住心院以外は訪問したことがあるし、パンフレットを読んだことがあるので、天台宗で括ることに違和感があったので、敢えて瑣末なことを書いてみた。
その意味では、宗派で括らなくても説明はできた。

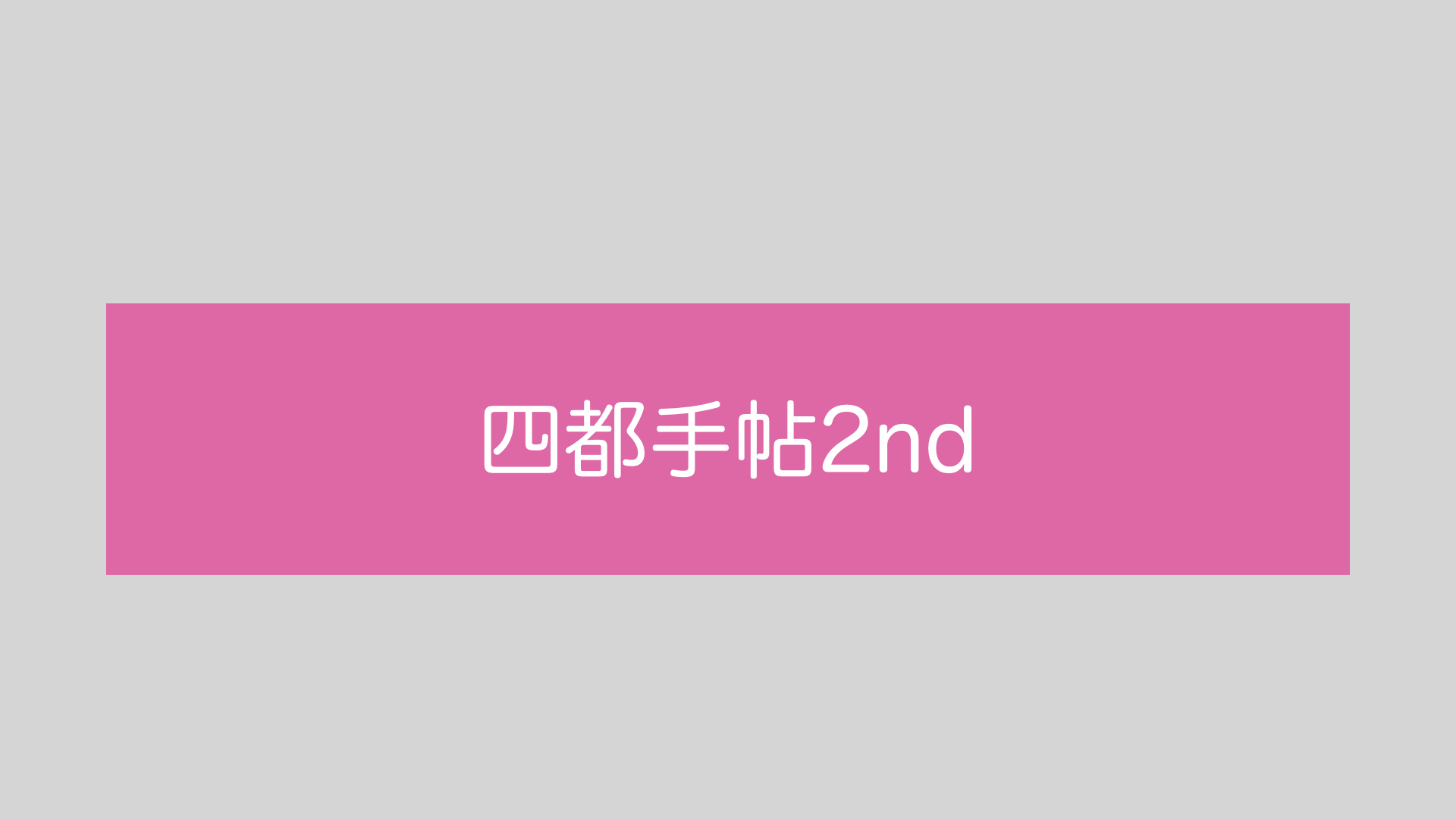

コメント