國分功一郎『中動態の世界 意識と責任の考古学』医学書院、2017年
書誌情報
本書は医学書院の雑誌『精神看護』に2014年1月号から11月号まで掲載された連載「中動態の世界」がもとになっている。担当が石川誠子氏であったことや、本書の編集者が白石正明氏であったことがあとがきで触れられていた。目次は章節がある。詳細な注はあるが、索引はない。
Twitterをフォローしていたので、刊行されて直ぐに手にしていたが、ギリシャ語をもっと知ってから読もうとでも考えたのか、2章あたりで止まっていたようだ。哲学概論の知識も持たずに読んでも本書の位置付けがわからない。それでもって古典ギリシャ語の動詞の活用の話をされても文法に関する理解もないのでもどかしい。
それが、また、読みたくなったのは、安藤礼二氏の講演に対する斎藤慶典氏のコメントのなかで、この中動態の話がでてきたからだ。「見る」(能動態)でも「見られる」(受動態)でもない「見える」(中動態)がテーマに迫っているように感じたのである。空海を存在論から見た斎藤慶典氏の話だった。この話は難しいのでここでは触れないでおく。
能動態と受動態で意志の存在を表せるのかについての考察から始まる。
脳科学では注でリベットのマインドの話が出てきた。行動が先に起こり、意識はあとで認識される。この意味づけは意志の曖昧さを考えさせることになる。
インド=ヨーロッパ語族の諸言語において能動態と受動態が対立するものと教えられてきたが、「もともと存在していたのは、能動態と受動態の区別ではなくて、能動態と中動態の区別だった」(p.34)。
「態には大きな変動の歴史がある。態に注目することでわれわれは、歴史を無視した構文の意味論的分析を避け、言語の歴史に注目できるようになる」(p.37)。
意味深な言い方である。ウイットゲンシュタインが構文に注目したというのであれば、ウイットゲンシュタインを批判したのだろうか。ウイットゲンシュタインの主張を読まないと何とも言えない。それにしても索引のない本は扱い辛い。
注)
ベンジャミン・リベット、下條信輔・安納令奈訳『マインド・タイム 脳と意識の時間』岩波現代文庫、2021年
ブログを見たが、2021年3月購入図書にあるだけで、Evernoteに書き出したものはあったがまとまっていないのでブログに載せなかったものとわかった。中動態の観点から読み直してみる必要がある。
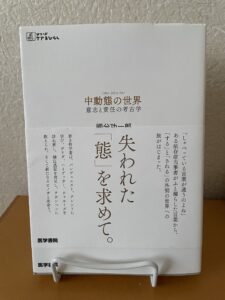
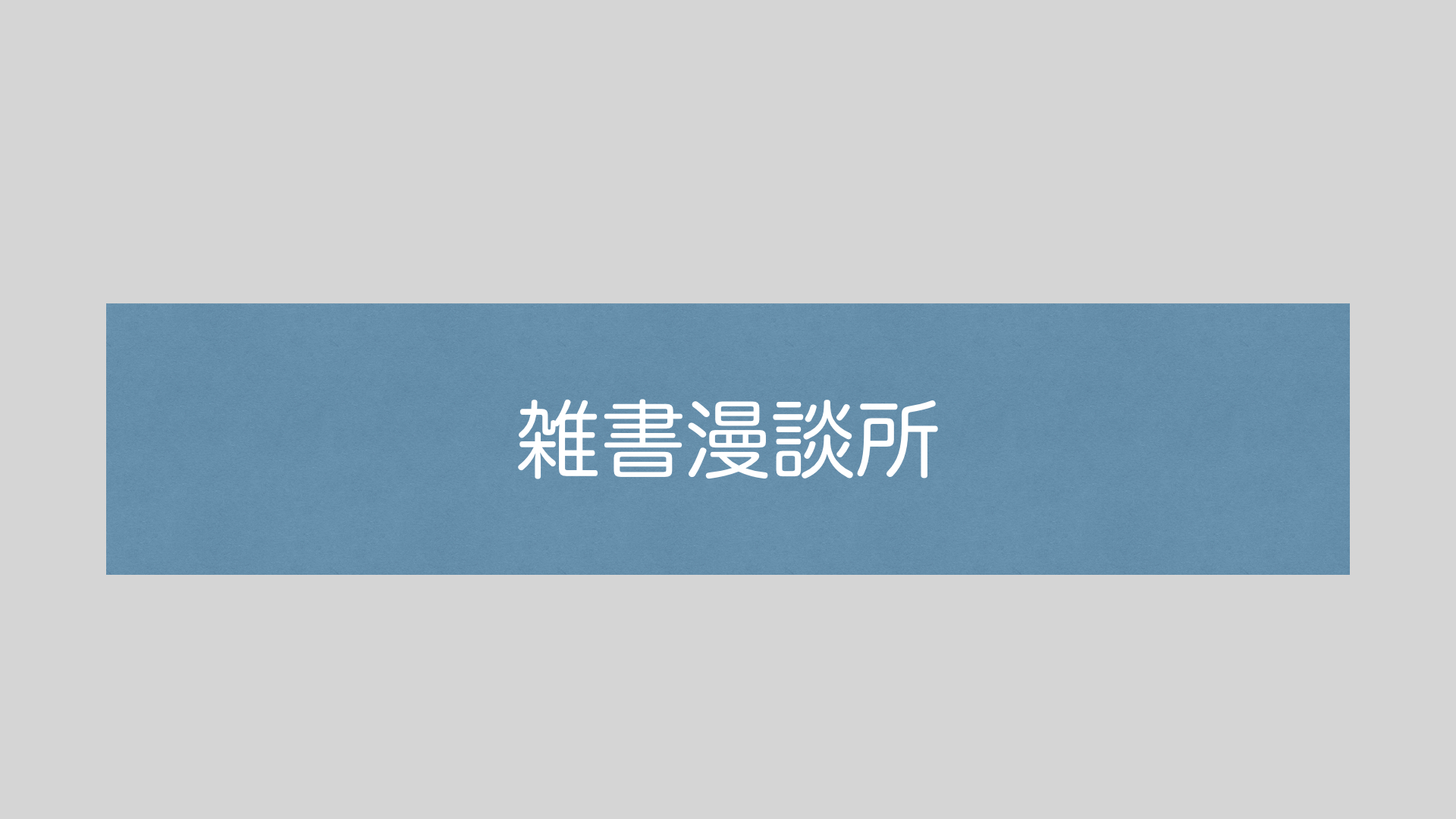

コメント