河内将芳『信長が見た戦国京都 城塞に囲まれた異貌の都』洋泉社歴史新書y、2010年
部屋の片づけをしていたら、出てきた。付箋もペタペタと貼ってある。しかし、内容は忘れていたので、他の並行読書中の本より、先に再読することにした。5冊を抜き去って読むのだから、私の波長に会うのだろう。ある程度その時代について読み慣れていないと、右から左に情報が流れて定着しない。最初に読んだ時は、京都本の一つとして読んだので、京都本の箱に入っていた。読み返したいと思っても見つからない訳である。
信長が永禄二年(1559)に上洛したときから、本能寺の変で亡くなる天正十年(1582)までの戦国京都を紹介した本である。『信長と京都:宿所の変遷からみる』(淡交社、2018年)が書かれる前に「信長のことを京都という定点からこだわって見ること」(P9)がすでにこの書でなされていた。
信長が行った延暦寺焼き討ちや、洛外放火、上京焼き討ちは、泣く子も黙る信長の軍勢と受け取られた。
「しかし、そのように恐れられる存在となったことは、信長やその軍勢にとって、あるいは京都の人びとにとっても、けっしてプラスに働くことはなかったであろう」(P193)。
「おそらくは表面的にはわからないところで、信長やその軍勢と京都の人びととのあいだには、埋めることのできない深い溝ができていった。そして、その溝を埋めることができないまま、あるいはそれを埋めるいとまもないまま、信長は京都で命を落とすことになる。逆説的な言い方ではあるが、本能寺の変が京都で起こったのは、このようなところにもその理由があったように思われる」(P194)。
それにしても河内将芳氏の文章は先を急がない。
信長は敵対するものに対して容赦なかった。上京焼き討ちの際の信長の軍勢による乱暴狼藉は戦国時代のそのものだ。
河内将芳氏はこの本の結論をこう結ぶ。
「信長は本拠地の安土城でもなく、また戦場でもない、自らがもっとも安全と認識していたはずの京都で命を落とすことになった。おそらくそれは、信長自身、まったく予期していなかったことであったに違いない。しかしそのように予期もしないほど「御油断」していたところにこそ、このとき信長が京都で死ななければならなかった最大の原因があったように思われる」(P210)。
戦国時代に自信過剰でいては命を保つのは難しいと言わざるを得ないのはもっとものことだ。
#歴史 #河内将芳 #中世史
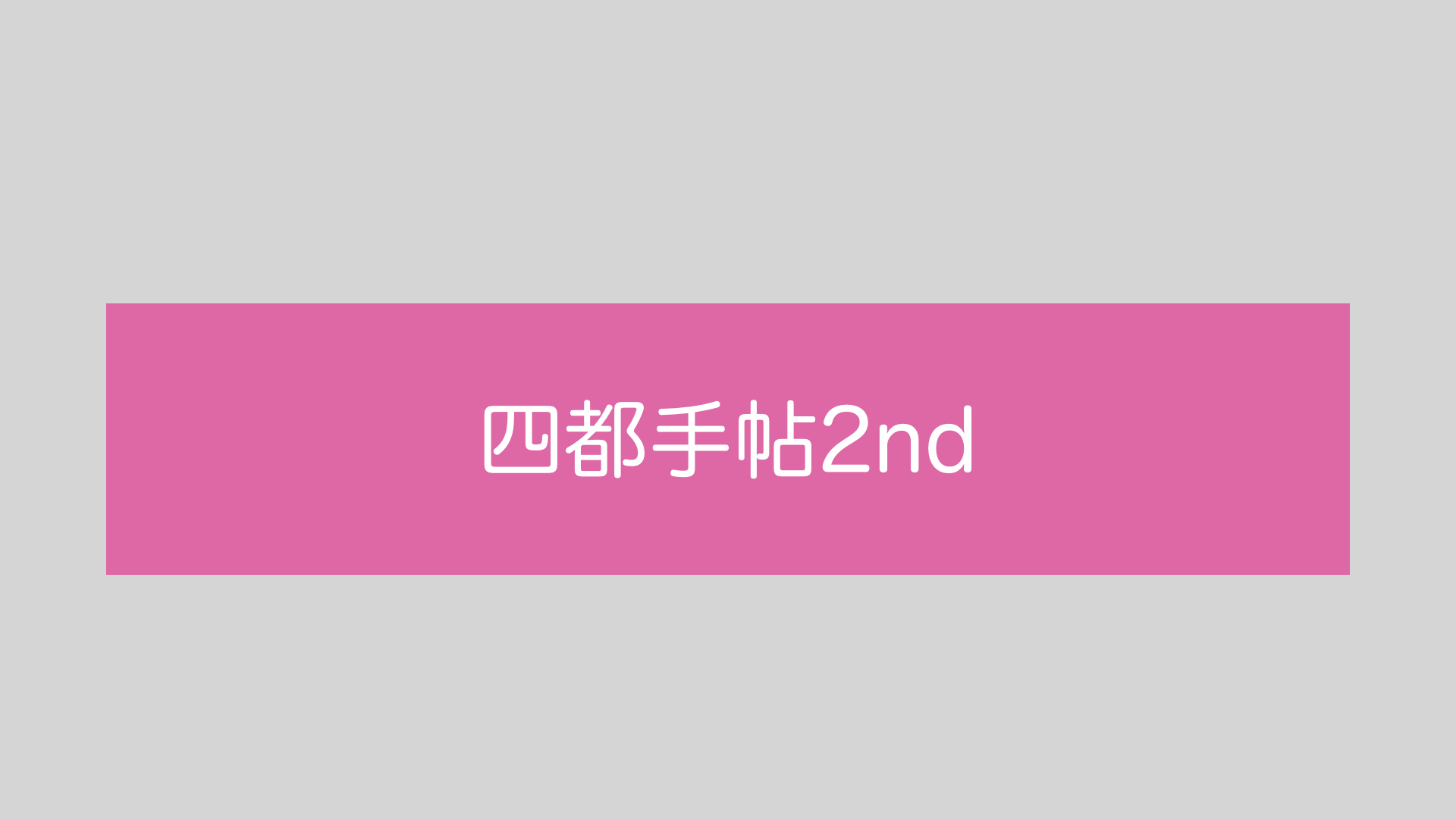

コメント