若松英輔「霊性論 第4章 岡倉天心と東洋的霊性」『思想 2017.4 No.1116』岩波書店
若松英輔氏が「日本的霊性」を論じていたのは、内村鑑三、新渡戸稲造、鈴木大拙を対象にしたものだった(注1)。若松英輔氏の岩波書店の『思想』に連載している「霊性論」は内村鑑三、新渡戸稲造と続き、岡倉天心となった。私は岡倉天心が「霊性論」に取り上げられるのは予期していなかった。内村鑑三、新渡戸稲造そして鈴木大拙は宗教としてのキリスト教と対峙することで日本的霊性の自覚が生まれたとすると、岡倉天心に「美の霊性」を見出した若松英輔氏は、どういう契機を見ているのであろうか。
「岡倉天心(1863-1913)は、一元的思想に強く抗いつつ、東洋、あるいは日本的霊性の可能性を追求した」(「霊性論」)。
「明治期における霊性の探求が新渡戸、内村のようなキリスト者、あるいは山崎弁栄のような仏教者といった宗教者によって牽引され、真と善のあわいで進められていたなかで、美に着目した天心の存在は異彩を放っている」(「霊性論」)。
若松英輔氏は『茶の本』から茶道を「宗教」と述べる天心を見出す。狩野芳崖に「美術家の宗教は美術宗」という天心を見出した。「宗教」はどのような意味で使われているのか。
若松英輔氏が『狩野芳崖』から引用するところより前から引用したい。狩野芳崖が舞にも筆法に通ずるものがあるとしたうえで、「翁は画理を以って天地万物の真理を発明せんと試み、仏家禅僧の妙悟、儒道西哲の深旨、総て丹青鏡裏に照映して、其意義を判じ、得失を論じ、仁義道徳の大道、坐臥進退の庸行に至るまで、尽く画訣となせり。翁常に言ふ、『人生各自独立の宗教なかるべからず。」とあった後を若松英輔氏は引用する。
「美術家の宗教は美術宗あり、復た何ぞ他に之を求めんや』と。而して翁が画学上に於いて最も切に論弁したる所は照応の理是なり」。
若松英輔氏は「照応」に注目する。「英語の、corespondenceの訳語で、地上界と天界は不可分の関係にあり、前者は後者によって照らされ、それに呼応するように存在しているという思想を指す」と。そして、エマニュエル・スウェーデンボリの思想に天心が触れている可能性をみているし、「天心が美を単なる視覚的現象ではなく、むしろ、霊的なものとして認識していたことは明らかだろう」としている。
しかし、深読みのような気がする。
「照応の理」について考えてみる。「翁又謡曲を愛し、舞を好む。常に舞法の筆法と同一なる所以を説き、得意の事、得意の人に遇へば、婆娑として起舞し、傍に人なきが如し」とその前に書いてある。狩野芳崖が画理を以って真理を発明するということ、それは「画訣」という「画の描き方」を突き詰めれば、「舞法」も「筆法」に通ずるものがあることを言っているだけに過ぎないのではないか。「照応の理」といいながら、天心は狩野芳崖の言葉としては引用していない。他の「照応」の使用例をみてみると、狩野芳崖が「晩年、人をして其意見を筆記せしめたるものあり、左に掲げて、其持論の一班を示さん」としたなかで「照応」を使っていて、コンテキストから見ても画面構成の妙として「バランスをとる」くらいの意味である(注2)。
また、「宗教」と言ったのは翁である狩野芳崖であり、天心ではない。若松英輔氏は狩野芳崖の言葉を「美術家の宗教は美術宗あり、復た何ぞ他に之を求めんや」としか引用していないが、その前に狩野芳崖は「人生各自独立の宗教なかるべからず。」と一般的な考えを述べているのである。これは、陶芸家であれば、「陶芸家の宗教は陶芸宗あり、(省略)」だし、批評家であれば、「批評家の宗教は批評宗あり、(省略)」くらいのことにしかならないと思う。
注1 若松英輔『内村鑑三をよむ』岩波ブックレット、2012年
注2 「照応」の使用例
「蕪穢煩雑を避くる為めには、実際にあるべきものも、之を省くの工夫をなすべし。孤立突出を避くる為めには、実際あらざるものも之を補添せざるを得ず。長短大小、配致宜しきを得、疎密濃淡、照応度を失はず。勇猛嬌婉、物に従って妙想を発す、何ぞ必ずしも形似の末に拘泥せんや」(『狩野芳崖』)。
「画訣」という「画の描き方」のなかで、実際にあるものを省略したり、付け加えたり、長短大小をつけたり、疎密濃淡をつけたりするのは、対象間の釣合いの程度を考慮しながら行う技法にすぎない。
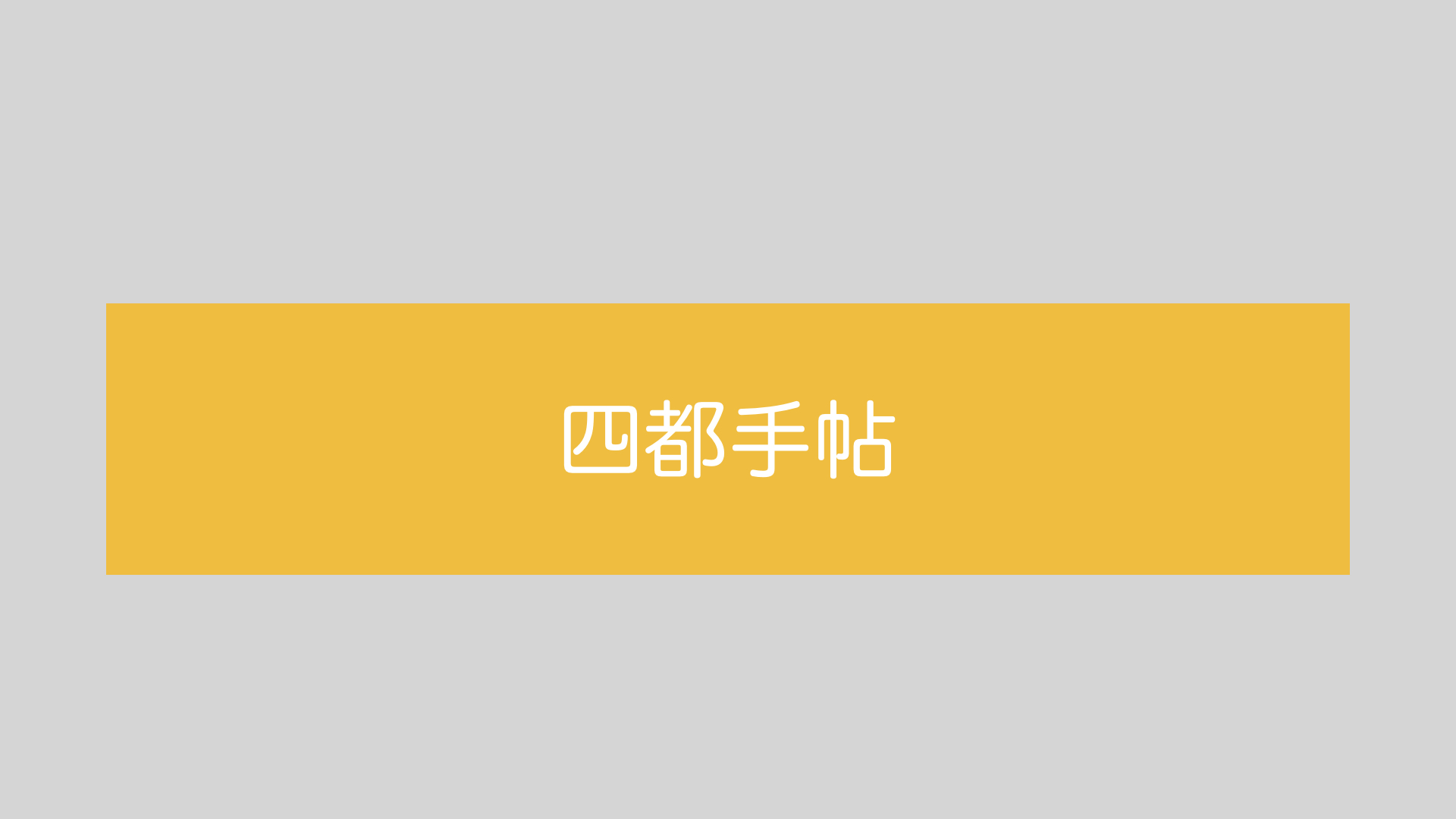

コメント