丸谷才一『快楽としての読書[日本篇]』ちくま文庫、2012年
書誌情報
本書はⅠ 書評のある人生とⅡ 書評122選からなっています。
本書は書評を載せた複数の単行本から書評をセレクトし、単行本未収録の書評23編を加えたちくま文庫オリジナル版です。書評索引が書名索引と著者(編者)名索引から成っています。カバーデザインは和田誠氏。招き猫のデザインがかわいい。なお、『快楽としての読書[海外篇]』に「イギリス書評の藝と風格について」が収録されていると解説の湯川豊氏が書いていましたので、続編も買う予定です。湯川豊氏のイワナ釣りのエッセイも読みたくなりました。どこの段ボール箱に入っているのでしょうか。
湯川豊氏は文藝春秋で『文學界』を担当した編集者でしたので、当時の書評についてよく知っています。
「新聞の書評欄があるにはあったが、なんとも中途半端な存在だったとき、敢然と書評欄の充実に取り組んだのは、「週刊朝日」の編集長だった。扇谷正造は一方で「週刊朝日」の大衆化を巧妙にすすめて125万部という驚異的な部数を実現しながら、もう一方で同じ週刊誌のなかにきわめて上質な「週刊図書館」という書評欄をつくった。雑誌というものを重層的に考えることのできた名編集長だったのである」(解説P458)。
本論とずれますが、この日本語は英訳しようとすると日本語文のつながりの曖昧さが気になります。
丸谷才一は1951年2月の『週刊朝日』の「週刊図書館」をもって「わたしの見方では日本の書評はこのときからはじまる」(P31)と云っています。
丸谷才一が「現代日本においては書評がまだ文藝時評の域に達してゐない」(P53)と書いたのは「書評の条件」(「週刊朝日」1975.10.31)でした。「一篇一篇の枚数が決定的に短いし、その悪条件を常に克服するほどの書評の藝は、わが文学ではまだ熟成してゐるわけではない」(P30)と平野謙の『新刊時評』(河出書房新社、1975年を評しています。
丸谷才一は「Ⅰ 書評のある人生」のなかで、二人のジャーナリストが書評文化をつくったといいます。扇谷正造の「週刊図書館」と毎日新聞の編集長・齋藤明氏(後に社長)の「今週の本棚」でした。
湯川豊氏は、「そこで本物の書評文化を実現していったのが丸谷才一だったのである」(P461)とみています。
Ⅰ 書評のある人生の話題を書いてきましたが、Ⅱ 書評122選はどのタイトルも興味を惹く書き方です。一々メモしたら終わらなくなりますので四つほどあげておきます。
野守は見ずや 大岡誠『私の万葉集』
西郷も大久保も食べた 高田静『さつまあげの研究』
随筆集の工夫 湯川豊『イワナの夏」
小説への風刺 吉田健一『瓦礫の中』
良質な文藝時評を読むと、読み方を教わることになりますが、なかなかそのようには読めないものです。何事にも修行が必要なわけです。職業としての書評を読むのも読書の楽しみの一つです。
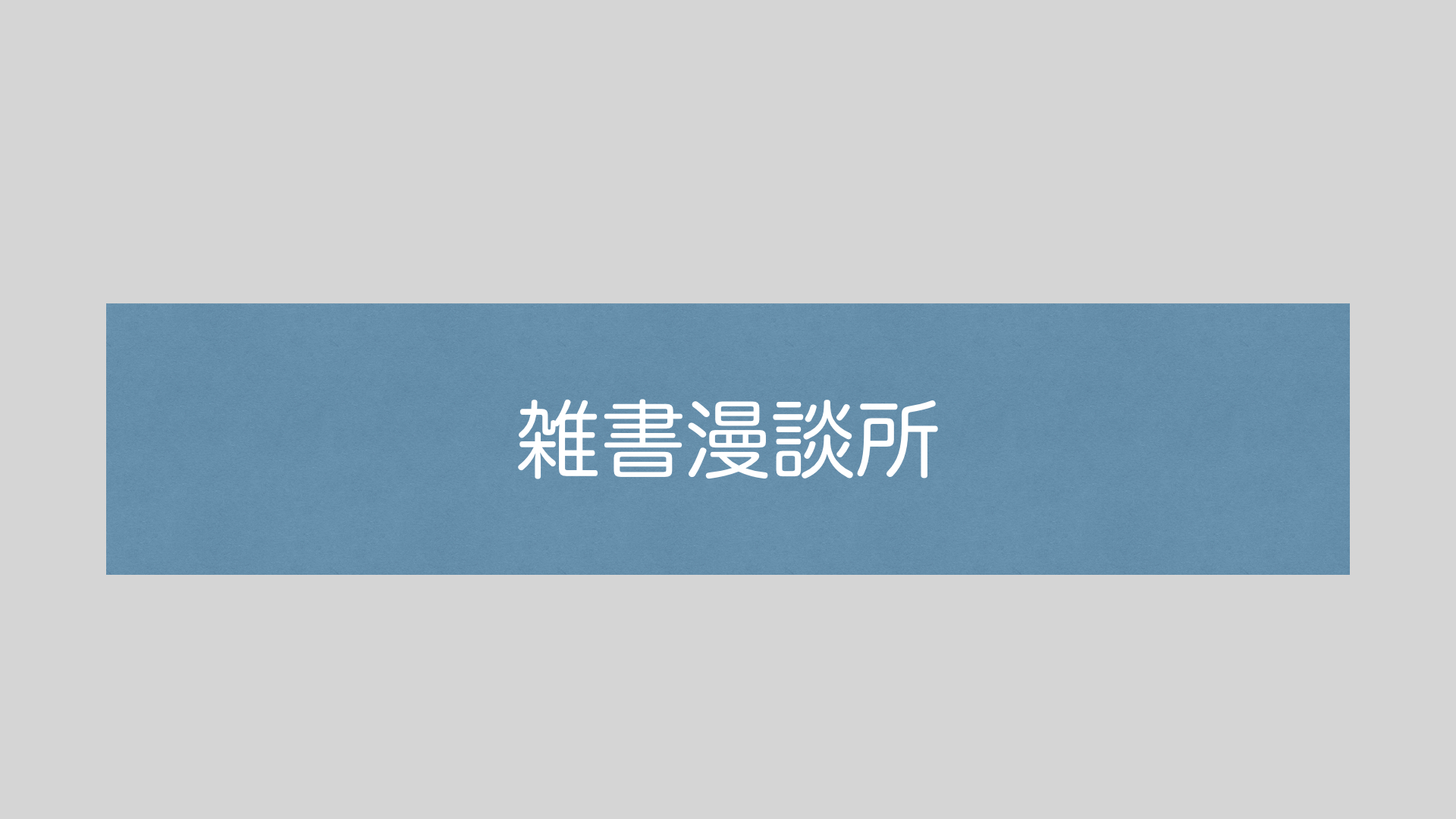

コメント