日本歴史学会編集、永原慶二『荘園』吉川弘文館、日本歴史叢書新装版、1998年、2008年第3刷
途中まで読んで付箋が貼ってある。
「歴史教育の場でも、一般の日本歴史好きの人びとのあいだでも、荘園はいつでももっとも難解なテーマだ、というのが定評である。それはなぜであろうか」(P1)。
「荘園はしばしば荘園制社会という使い方もあるように、貴族や寺社の領地というにとどまらず、中世社会の国家体制・身分・土地制度,収取体系など、国家と社会の骨格・システムを規定するもっとも基礎的かつ総括的な性格をもつものである。ところがそれにもかかわらず、荘園制はたとえば律令制や幕藩制のように、国家レベルで、いつどのようにして生み出されたかを明確にし難いという特徴をもっている。それは国家の統一的な制度や体制として一挙に生み出されたものではない。したがって、個々の荘園の規模とか管理方式も画一的なものではないし、荘園領主の領主権や収取体系などもけっして均一的なものではない。荘園にかかわるさまざまな人びとの身分のあり方さえも、とても一様なものとはいえないのである」(P1-2)。
「それゆえにこそ、私は長く荘園史の研究にかかわってきた者の一人として、自分なりの荘園史像を一つの体系として提示する義務と意義とを感じる」(P2)。
著者の荘園への視角が述べられる。
(1)荘園はほとんどの場合、本格的に成立した段階ではその規模に差はあるにしても、田畠・山野河海などの荘地と一定の住民をもち、一つ以上、場合によってはかなり多数の集落をふくむ空間であるという点にかかわる問題である。
(2)荘園は、支配層の所領・土地財産であるという点にかかわる問題である。(省略)荘園の所有と支配にかかわる問題といっておこう。
(3)中世社会・国家と荘園との関係ともいうべき個々の荘園、個々の荘園領主を超えたところにかかわる問題である。荘園と王朝国家、荘園と鎌倉・室町幕府といった問題がその中心であるが、それはまた中世の社会支配秩序の全体にかかわる問題でもある。(P3-4)。
荘園の発生から見ていく。
「律令国家のもとで懇田永年私財法が定められたのは聖武天皇の743(天平十五)年である。ついで749年、諸大寺の墾田規模が定められた、東大寺は最高の4,000町とされた」(P9)。
「古代の初期荘園群は、国家の禁制を犯してつくりだされた権門寺社の私有地ではなく、国家がみずからつくりだし東大寺などに施入したものであることろに特徴がある」(P10)。
三世一身の法から墾田永年私財法になった。私の中学生の時は墾田永代私有令だったと記憶している。いつのまにか墾田永年私財法になっていた。
注)宇治谷孟『続日本紀(中)全現代語訳』(講談社学術文庫、1992年)を開いて、巻第十五 聖武天皇 天平十五年五月二十七日条を読む。三世一身(さんぜいつしん)の法(自力で新たに開墾した田地は三代までその土地の所有を認める)を改めて永年にわたり個人財産と認める。その土地の広さは品位により限度がある。庶民は十町である。この年の冬、十月十五日、聖武天皇は盧舎那仏の金銅像一体の造立を詔された。久しぶりに『続日本紀』を読むと、天変地異が多いことに驚く。
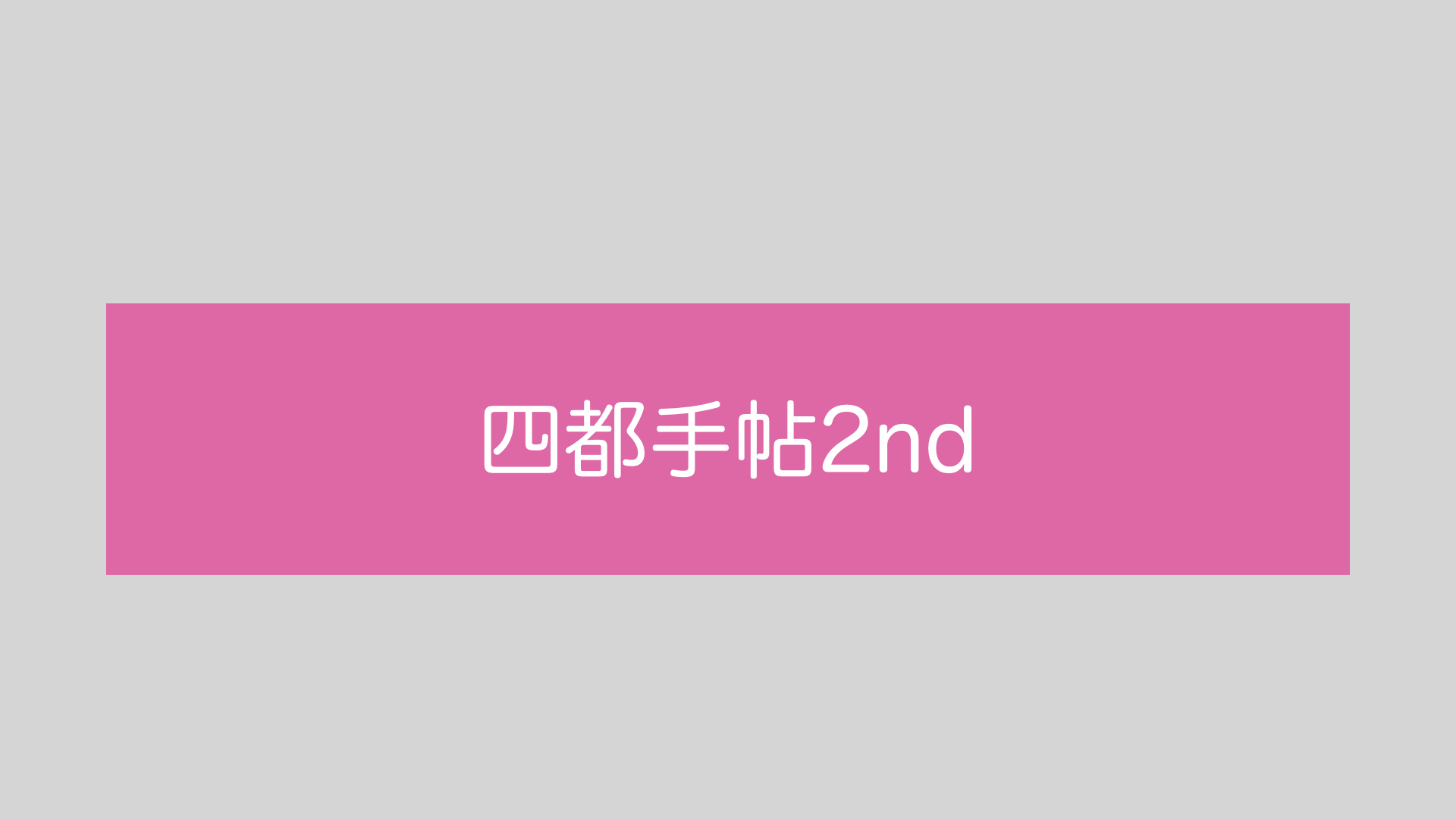

コメント