鎌田東二、南直哉『死と生 恐山至高対談』東京堂出版、2017年
第1章 出会い
第2章 恐山 死と生の場所
第3章 危機の時代と自己
第4章 生きる世界を作るもの
第5章 リアルへのまなざし
第6章 生命のかたち
2019/01/11
第4章
経験を語る言葉・言語と、それが形作る思想が話題とされる。
南氏「思想には、仏教と仏教以外の二種類しかないと私は思っています。そしてこれらを分ける大きな問題は、言語をどう考えるかという点なのです。言語が真理を語り得ると考えるか、または、言語は真理には届かず、言語で語られるものは仮説物、虚構でしかないと考えるか、そのどちらかだと思います。そしてこれが人間の考え方を大きく分ける一つのラインだと思っています。露骨に言うと、ゴータマ・ブッダの教えとそれ以外しか、この世にはないような気がしますね」(P137)。
[言語に対する不信は中島敦の『文字禍』の話やプラトンの『パイドロス』の話をする前田英樹の『愛読の方法』(2018年)を読んでいたのでピンときたが、突き詰めれば経験と言葉との間の問題でもある。南氏は佛説は真理には届かないとする。だからお経は方便という。]
南氏「ブッダが発見したのは「無明」という実存の状況だということです。つまり、これによって人間は苦である、悲惨であるという話。キリスト教では原罪にあたるものだと思います。
「無明」というのは「認識の間違い」という意味ですから、認識を成立させる言語こそが、この人の言っている無明だと思ったんですよ」(P138)
[自意識は言葉である。南氏は坐禅という身体技法で自意識を解体することができるという。鎌田氏の心身変容技法は何を目指していたのか?]
2019/01/12
第5章
[思い込みというのはあって、四国八十八箇所巡りは西国三十三所観音巡礼と同じ観音信仰だと思っていた。本尊が観音菩薩30か寺、薬師如来23か寺、地蔵菩薩6か寺、大日如来6か寺など。]
「メタノイア」という言葉で、美学者の高橋巌の話が出てくる。
鎌田氏
「高橋先生に学んだ核心的な命題は「悔い改め」です。カトリックでは、「懺悔(ざんげ)」、仏教では「懺悔(さんげ)」。この悔い改めを、高橋先生はギリシャ語で「メタノイア」と言っていました。メタ(〜を超える)、ノイア(ヌース、精神)。その意味は、これまで自分が感覚的に捉えてきた世界を、メタ、つまり転換せよ、という意味です。」(P190)。
[メタノイアは「人の視座や志に起こる変化」を意味する。ギリシャ語の新約聖書を「悔い改め」と訳したのは凄い。懺悔は正しく受け止められていない言葉だと思う。]
この章では「欠落感」が語られる。生死のリアルである。
2019/01/13
第6章
南氏の生と死の問題を捉えるために何が大切かという質問に答えて、鎌田氏は「歴史認識と詩や物語」と答えた。死に向き合うため、「自分の人生をひとつの物語にすることが大切な」のだという。
鎌田氏は「無常」と「むすび」は同じことを言っているという。
「むすひ」は自然が持っている生成の力を指しているという。関係性からものごとが生起する。南氏は「むすひ」を縁起に近いと受け止めた。
[死の受容というテーマのなかで、空海、道元、親鸞が語られるが、笑って死ねたのは誰なのか?]
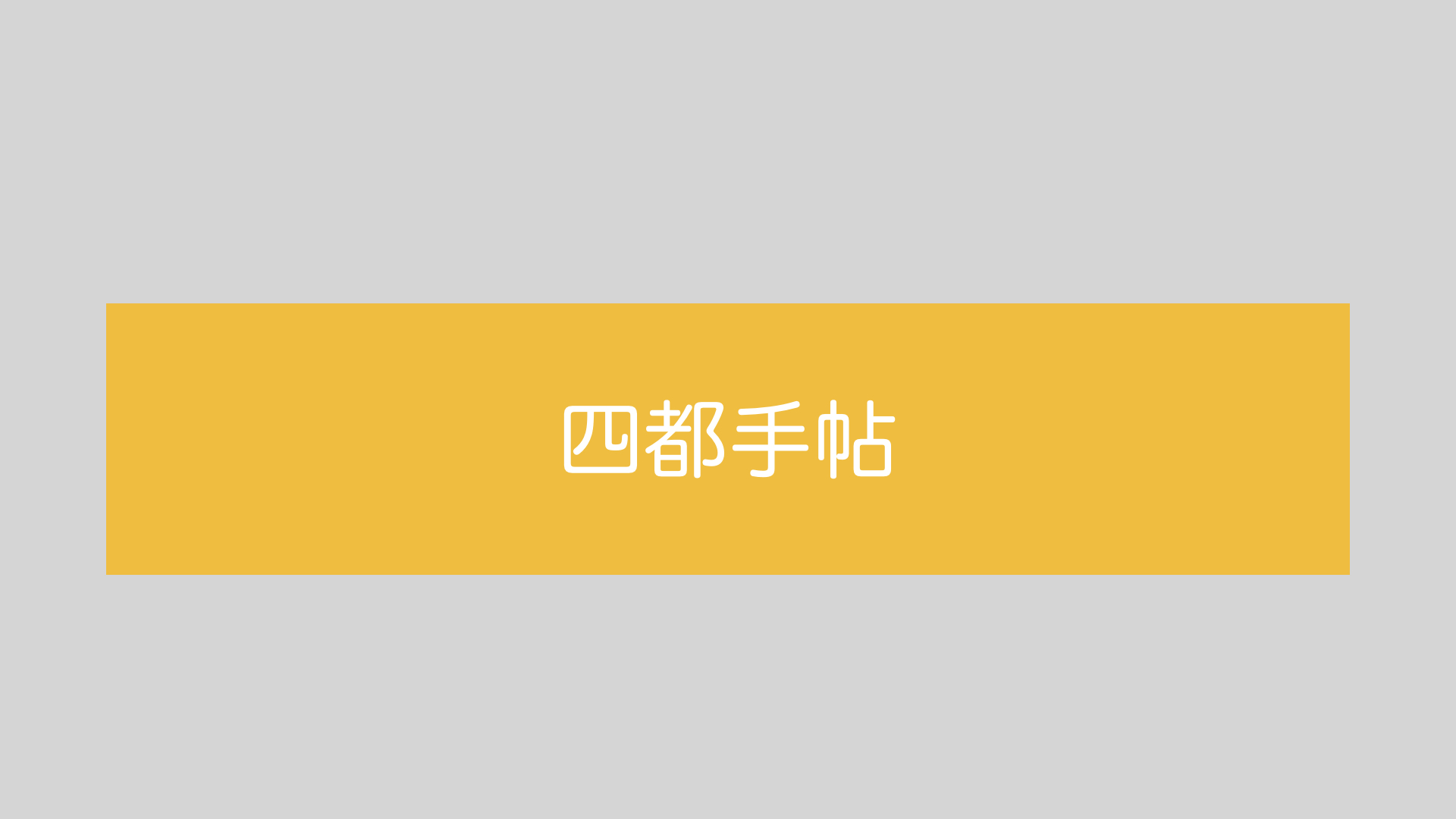

コメント