小松英雄『徒然草抜書 表現解析の方法』講談社学術文庫、1990年
重版して欲しい文庫の一つである。谷沢永一氏の本で知って神保町で買い求めた。そう容易く読める本ではないが、古典文学作品に関して読みかたを変える力がある。
前言
序章 文献学的解釈の基礎
第一章 つれづれなるまゝに
第二章 うしのつの文字
第三章 土偏に候ふ
第四章 蜷といふ貝
第五章 いみじき秀句
結語
「前言」に著書の目的が書いてあるので読み飛ばさないようにしないと著者の真意を取り違えることにもなりかねない。
「『徒然草』から、従来の解釈では理解しにくい五つの短い章段を選んで、文献学的方法に基づく解釈の手順を踏みながら、表現の解析を試み、導かれた帰結を従来の解釈と比較することによって、古典文学作品の文章を解釈するための方法について、基本から考えなおしてみようというのが小冊の主たる目的です」(P19)。
ここで、「文献学」という言い方を著者がしている。著者の定義は「文献学とは伝存する文献をあらゆる角度から徹底的に解釈し、可能なかぎりの情報をその文献から引き出すことによって、その文献の本質を明らかにするとともに、時代や民族の精神にまで迫ろうとする指導原理に基づく研究領域」(P24)とある。もっとも、「前言」で述べる事柄は、すべてたてまえといっているので、読み方に注意する必要がある。定義には踏み込む必要がないと受け取ればよく、文献学的解釈の有用性は、各章の考察を読んで判断していくことが読者に求められる。方法論は正しくても、個々の適用が不味ければ読めたものではない。
著者は日本語学の専門家であるが、「読む」ことに関して厳しい人である。
「古典文学作品に接する場合、日本文学の研究を志す人たちは、とかく、ことばの厳密な意味やその微妙な含みなどをあまり深く考えてみようとせずに短絡的な読みかたをしたうえで、作品論や作家論に力を入れたがる傾向がうかがわれるようです。また、日本語の歴史的な研究を手がけている人たちは、目前の対象が文学作品として書かれたものだという事実すらも意識せずに、特定の時期の言語資料とみなし、それぞれの作品の個性を考慮することなしに都合に合わせて手あたりしだいにつまみ食いをする、といった傾向があるように見うけられます」(P22)。
さて、「前言」のあとに「序章」がくる。その後に第一章が続く。
序章は『徒然草』の諸伝本の表記から始まる。原本が残っていない以上、著者や執筆時期は推定となる。著者は兼好と推定されている。そこに論証過程があることに注意しろという。小川剛生氏の『新版 徒然草 現代語訳付き』(2015)では兼好は吉田兼好ではないと論じていた。日本の古書の場合、中国と違って、写本の時代が長かったので、伝本批判が煩雑である。吉川幸次郎が『詩と永遠』(1975)の中で指摘していたのを思い出す。以前は古典文学作品を読もうとすると、解題で諸伝本の煩瑣な解説があり、それだけで読む気が失せるということもあったが、今は、諸伝本の扱い方を見ないと安心して読む気にならない。変われば変わるものである。
ここでは烏丸光広本と正徹本の冒頭の写真が比較される。活字で読んで来た私には古活字本や版本の文字が読めずに挫折したことを思い出す。今回はここがクリアできたのは慣れのせいだろう。定家仮名遣の問題や清濁についてすでに知っている知識をお浚いして第一章に入る。
第一章を読んだ感想からは、この文献学的解釈で『徒然草』を読み直すと楽しいということだった。何しろ本の題名すらあやふやだし、14世紀の本が読めなくて当然なのだから。
『徒然草抜書』(1990)その2
『徒然草抜書』(1990)その3
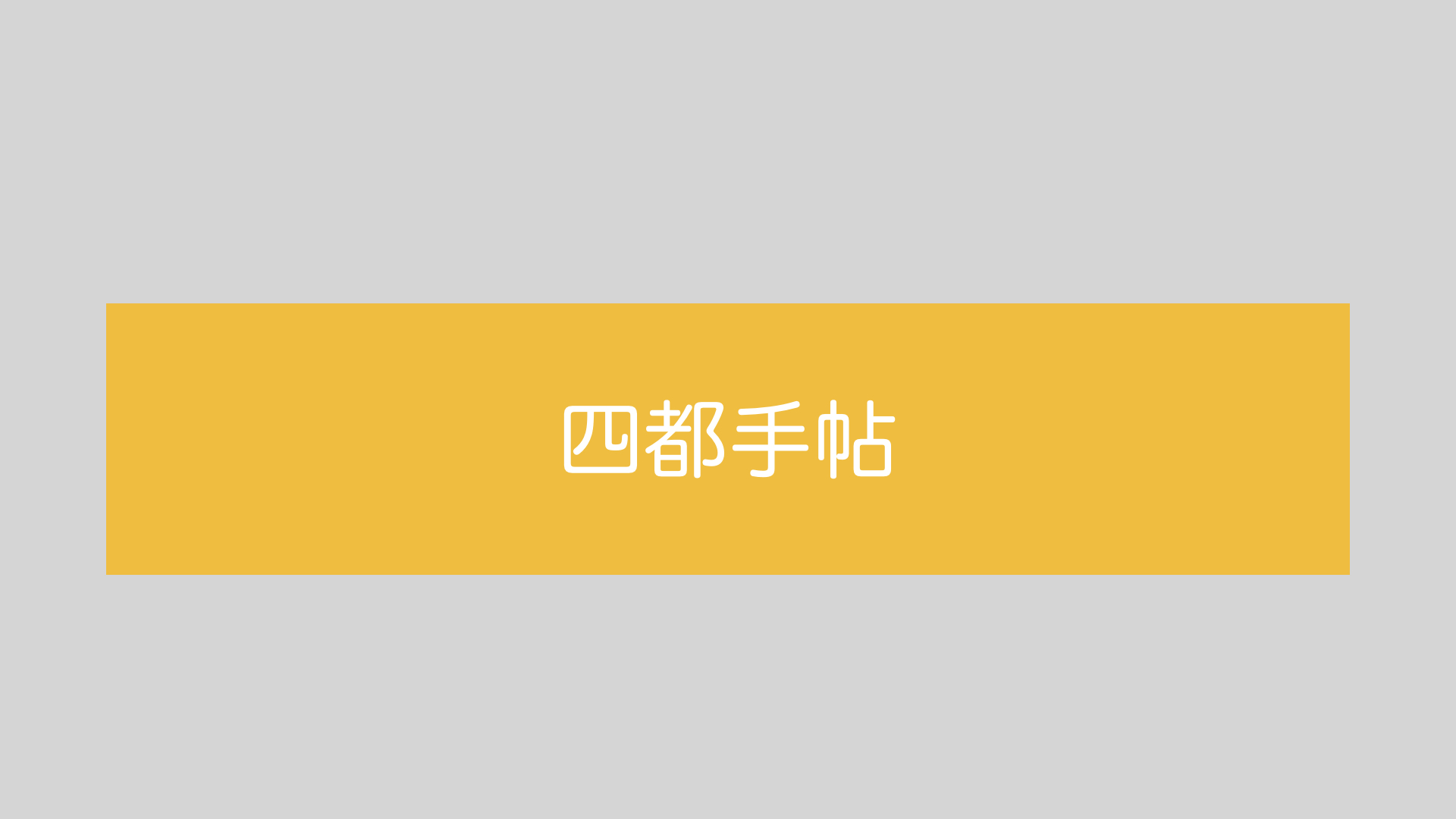

コメント