若松英輔『不滅の哲学 池田晶子』亜紀書房、2020年
「哲学者西田幾多郎と宗教ーーー若松英輔『不滅の哲学 池田晶子』第三章を手がかりに」
昨夜は上記の長いタイトルのオンライン講座がありました。
真宗大谷派教学研究所の名和達宣先生の講演と
高野山真言宗高福院の副住職の川島俊之氏の対談をオンラインで楽しみました。川島俊之氏は公認会計士で私と同じように監査役をしているそうで、親しみが湧いて、先月の講座に引き続き受講しました。
この講座の課題図書が若松英輔氏の『不滅の哲学 池田晶子』でしたので、読んで準備する過程がこの間のブログだったわけです。
西田幾多郎の本を探したのに、見つかりません。上山春平の解説を読んだ記憶があるから、近くにあるはずなのですが、不思議と出て来ません。買っても良いけど、同じ本を何冊も持っていても仕方がないので、誰かさんへ送りつけるというのも迷惑でしょうから、処分に困ることになります。本棚以上の本があっても探せなければしかたありません。
若松英輔氏は一人の哲学者の本を自身の該博な知識で論じています。池田晶子のことばなのか、リルケのことばなのか、そもそも若松英輔氏のことばなのか。響きあいすぎて、記憶が重なり一つになって受け止めるしかないようです。
さて、オンライン講座の話で印象深かったのはやはり「絶対矛盾的自己同一」でした。名和達宣(たつのり)氏によると、西田幾多郎の「絶対矛盾的自己同一」は論文のテーマにより色々な姿を現すといいます。確かに、若松英輔氏が池田晶子の言葉を読み替えた(2020年11月2日『不滅の哲学 池田晶子』(2020)その2)では「多と一」の関係で論じていましたが、宗教を論じる場合には違うと言います。
宗教を語る「場所的論理と宗教的世界観」(西田幾多郎哲学論集3 自覚について他四編』収録)では、どのようにろんじられているのか。
「絶対は、自己の中に、絶対的自己否定を含むものでなければならない。・・・真の絶対とは、此の如き意味において、絶対矛盾的自己同一でなければならない。(中略)
故に私は仏あって衆生あり、衆生あって仏があるという、創造者としての神あって 創造物としての世界あり、逆に創造物としての世界あって神があると考えるのである」(「場所的論理と宗教的世界観」『西田幾多郎哲学論集3 自覚について他四編』P327~328)。
それは「この世界が誕生したときに、創造主(神)と創造物は同時にあった」と考える思考が宗教を論じる時の「絶対矛盾的自己同一」なのではないかと名和達宣氏は言います。
「親から子が生まれるというよりは、子供が生まれることにより、親になる」という言い方が「絶対矛盾的自己同一」のニュアンスに近いのでは言います。このあたりは微妙ですが、絶対者(一)から人間が生まれる(多)という単純なイメージとは異なる使い方のようです。
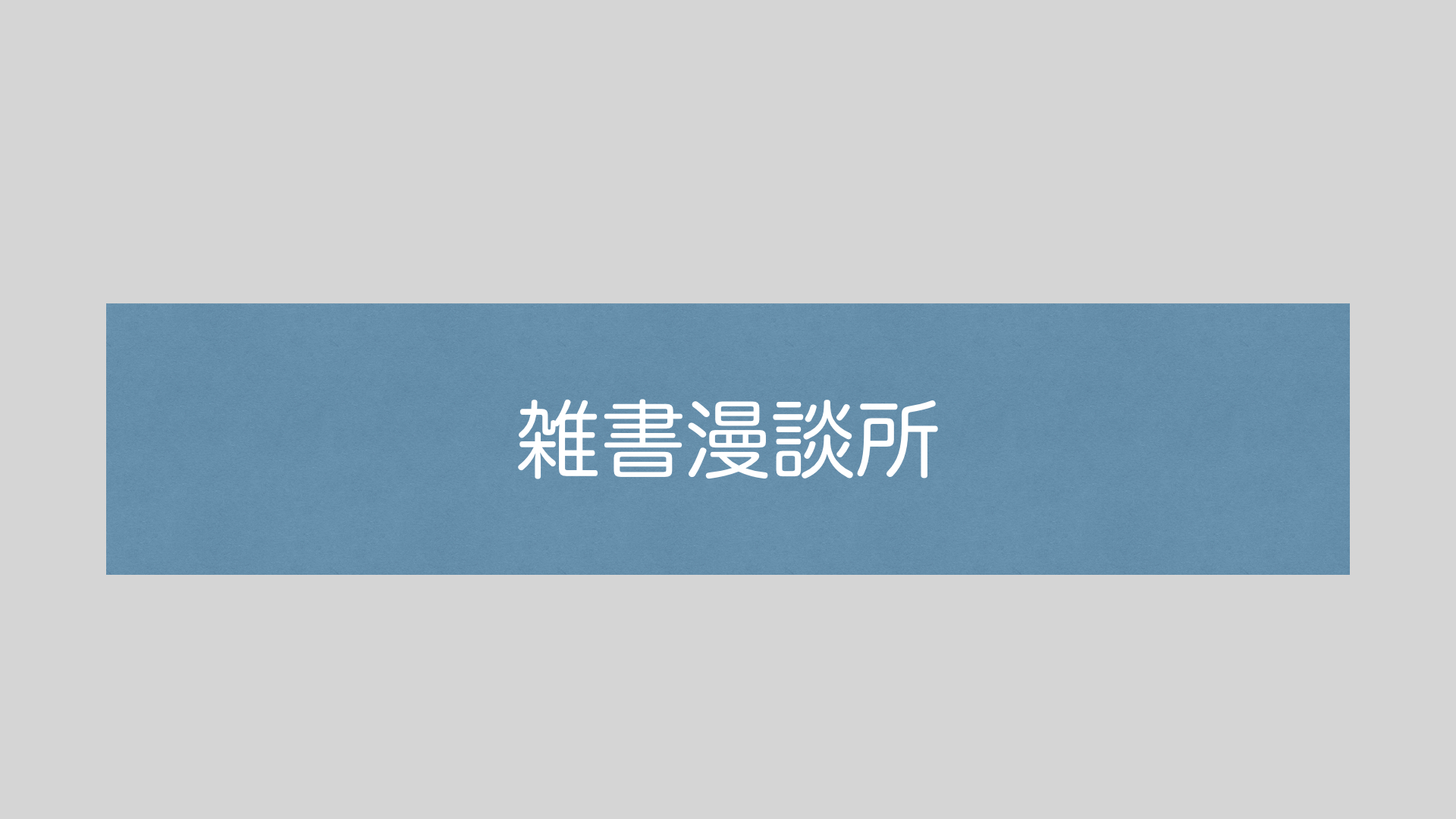

コメント