大和を歩く会編『古代中世史の探求1』法藏館、2007年
古代中世の大和を扱った地域研究の16編の論文からなる本。
著者達は「大和を歩く会」なるものを作り毎月1回大和と周辺を踏査し、100回(1995年4月〜2003年12月)で解散した。シリーズ大和を歩くの1巻は論文編で、2巻は踏査記を予定していたが刊行されなかったのかAmazonの検索で出てこない。
もともと、論文集なので引用する漢文には書き下し文がないし、漢字もルビが振ってないため、読めない人名・神名が出てくる。『日本書紀』や『古事記』などの注釈書で確認しながら読んでいたので時間がかかり、どこかで読むのをやめてしまったようだ。御多分に洩れず外部倉庫行になっていたが、去年若者達が本棚に戻してくれた本である。だから今頃気がついたというわけである。
告井幸男氏の「王名と伝領」を読んでいてロジックの組立とは難しいものだと分かる。
「まずは確実なところから話を進めていこう。稲荷山鉄剣銘文や江田船山古墳出土太刀銘文に見える「ワカタケル大王」は雄略天皇のことであるというのが定説である。雄略は『古事記』に「大長谷若建」、『日本書紀』には「大泊瀬幼武」とあるが、鉄剣銘文の出土・解読により、「若建」「幼武」が「ワカタケル」と読むことが明らかになった」(P28)。
河内春人氏の『倭の五王 王位継承と五世紀の東アジア』(中公新書、2018年)では『宋書』の倭の五王と記紀の王名を音韻で比定することに疑問を呈していた。告井幸男氏は記紀の王名を「大」は美称、「泊瀬」は地名、「幼武」はいわば諱であり、倭王の諱の一部を「音ではなく」意味的に訳したものであると考えている。「珍」も同様に考えている。しかし、「興」と「済」は分からないとしている。
そもそも日本に同時代史料がない以上確実なものはない。告井氏は「音韻説」では無理があることは分かっているので、「諱」の意味訳という説をとるが、「興」と「済」は「諱」の意味訳というロジックでは説明できない。仮説は統一的に説明できないときには無理があるものだ。学者はそれぞれの説を批判しながら、自説の依拠する根拠を説明する。定説、通説と用語を使い分けているが、我々一般読書人にはなぜ定説であるかの議論を知らないので、ロジックの前提が分からないことが、ロジックの組立を理解することを困難にさせている。法学では通説はあっても定説はない。
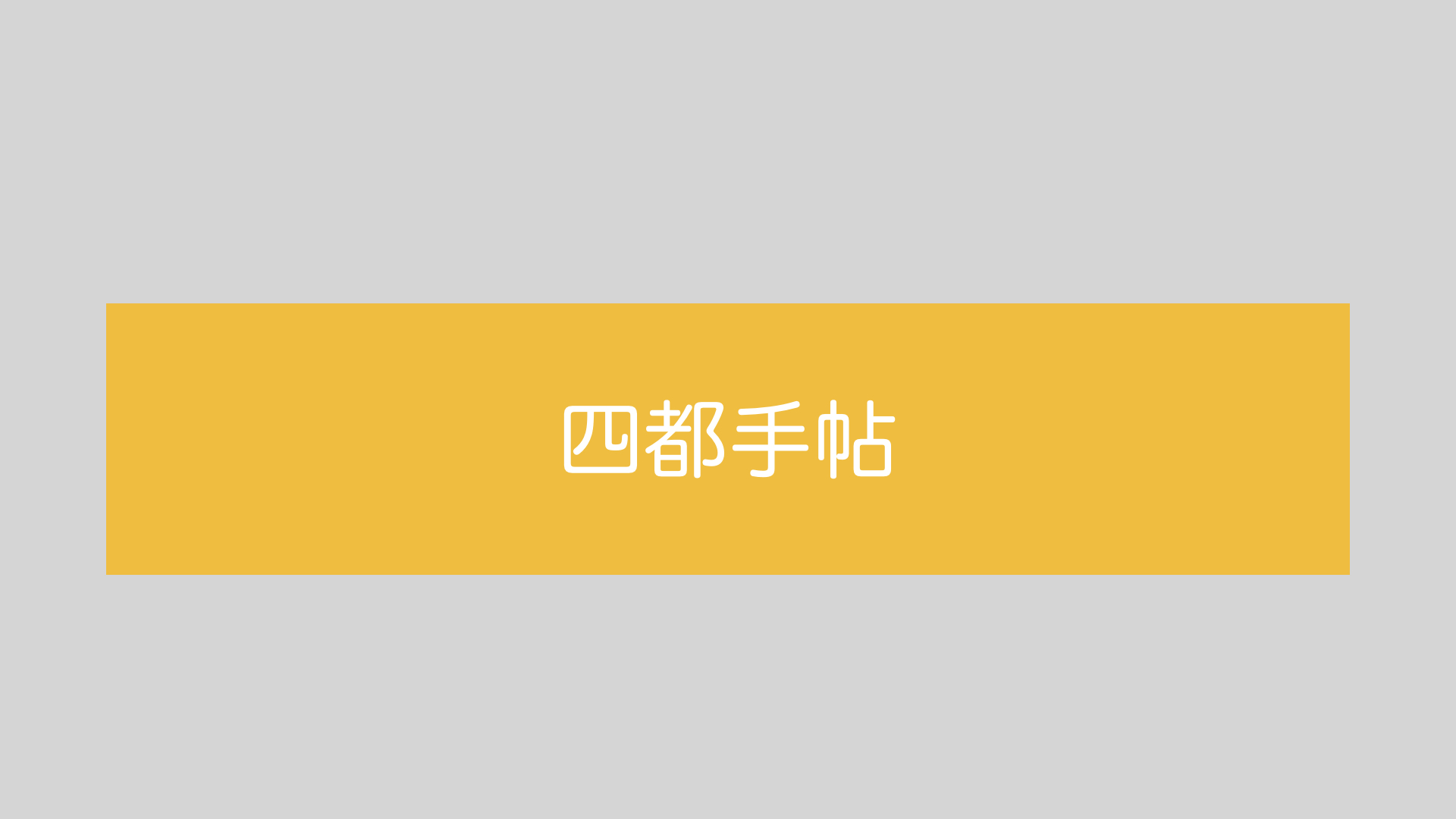

コメント