三島由紀夫『奔馬 豊饒の海・第二巻』新潮文庫、1977年、2013年第63刷
週刊新潮の「とっておき私の奈良」の三輪太郎氏の1回に大神神社の摂社の率川神社の三枝祭が出てくる。三島由紀夫が書いた率川神社の三枝祭を読むために大垣書店で文庫本を買って奈良に向かう。奈良ホテルにチェックインしてから、奈良国立博物館で地味な「忍性展」を観ることにした。
三島由紀夫『奔馬 豊饒の海・第二巻』では、大阪控訴院長の代理で大神神社の崇敬者の神前奉納剣道試合で祝辞をするため、本多繁邦が大神神社へ行き、そこで松枝清顕(まつがえきよあき 第一巻)の生まれ変わり(転生)である飯沼勲少年(国学院大学予科一年)の試合を見ることから始まる。
午後、宮司に言われて山に登ることになる。当時のあり方がわかるので宮司の言葉を引用しておくと、「もちろん一般人は入ることができませんし、ふだんはよほどの古い崇敬者に限って入山をお許ししているわけではありますが、それは森厳なものですよ。頂きの磐座を拝まれた方は、神秘に搏たれて、雷に打たれたような心地になると言っておられます」。
現在も三輪山(467m)は禁足地であり登山道では飲食・写真禁止である。狭井神社(荒魂)で志納して、襷をお借りし、お祓いして(一人だと自分でする)山に登る。途中にある三光の滝は水垢離をとる人の小屋がある。私も一度は三光の滝で引き返し、二度目は頂上まで行ったことがある。山頂までも樹々に覆われ視界はない。磐座を見てもどうということもなく降りてきた。
案内人に伴われて本多はお山に登り、下りで水垢離をとるために滝に打たれようとするが、三人の先行者がいて、その一人が飯沼少年だった。
本多は奈良ホテルにとまったが、三島由紀夫の描写が変なのでメモしておく。「窓外からは、猿沢の池の蛙の声しかきこえぬ静かな奈良ホテルの一室で、机上に重ねた訴訟書類にもとうとう手をつけず、本多は物思いに耽りながら、眠られぬ一夜を過ごした」。
奈良ホテルの前は荒池で、遠く離れた猿沢の池の蛙の声が聞こえるとは思われない。これをメモしている私は奈良ホテルの新館で朝の蟬時雨の中にいるのである。
寝坊した本多は奈良市にある率川神社の三枝祭を観に行く。この描写を三輪太郎氏は絶賛していたが、見事である。これを読むために『奔馬』を買っても損はないと自分に言い聞かせている(笑)。
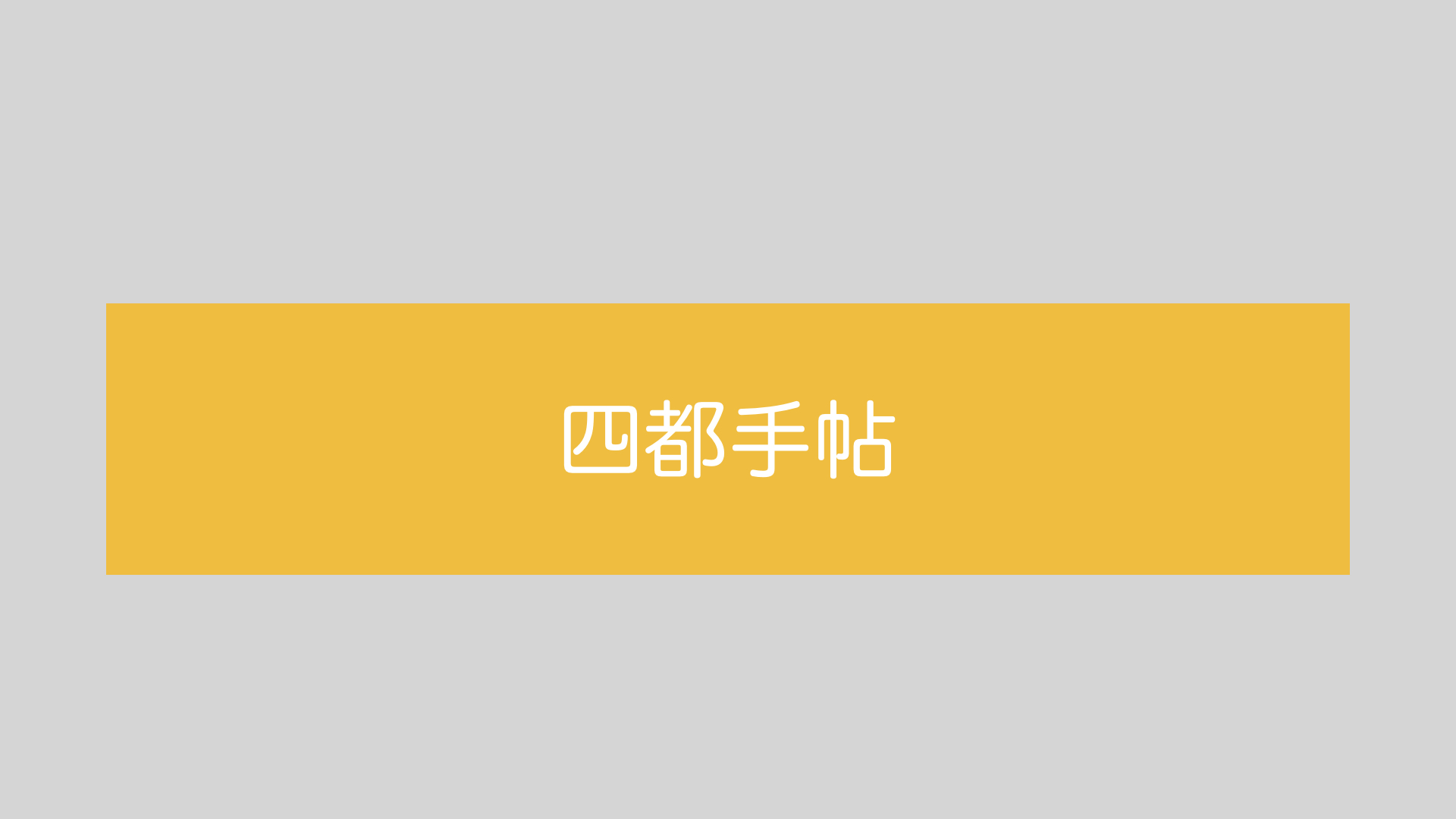

コメント