小西甚一『国文法ちかみち』ちくま学芸文庫、2016年
なにやっているの?と言われかねない。また、受験文法の本を買ってしまったのである。ある懐かしさと悔しさが同居するが、すでに不確かさを増した記憶の底に小西甚一の名前がある。この人の本が出回ることはないだろうと思っていたら、『国文法ちかみち』(2016)が出たのである。その前に『古文の読解』(2010)も出ている。この本は読んでいない。
『古文研究法』(2015)については去年に書いた記憶がある。和室から本を追い出したはずなのだが、この本は何時でも手に取れるように文庫棚に入れてある。手元の20冊である。小西甚一の本は書店に行っても手に入らないので、参考書とはいえ復刊してくれるのは嬉しい。文庫化に関しては編集方針に批判があることは分かる。しかし、再版でなく文庫化であれば、著作権やコストについての配慮が必要になるので、多くを望むことはできない。
あとがきを読むと、小西甚一が国語学の体系を示してあり、索引も完備している。本書は読者(高校生)の理解を容易にするために、分解して書いてあるが、その背景には体系的な配慮がある。このような観点で、いわゆる参考書を書いた人は知らない。
本書の構成にAssociation and progressionという原理が応用されているという(P19-20)。しかし、Association and progressionの説明がは省かれているので、ググルと著者の論文のタイトルになっていることが分かる。
Association and progression:
Principle of Integration in Anthologies and Sequences of Japanese Court Poetry , A.D.900-1350
Jin’ichi Konishi, Robert H. Brower, Earl Miner
Harvard Journal of Asiatic Studies
Vol.21 (Dec. , 1958),pp.67-127
共同研究の成果を英語で読むのは難しいと思ったが、ここに記録しておけば何かの機会があるかもしれない。
随所に英語がでてくるのは、著者がアメリカで得た刺激によるのだろう。
しばらく、本書を読むために、A4の用紙とシャープペンを使って「活用」の復習をすることになる。歴史的仮名遣いで50音図を書くことからスタートする。基礎は自在に取り出せなければ、解釈に活用できないからである。この50音図がサンスクリットの母音と子音の結びつきかたを説明するためにできたといわれると、何かワクワクするものがある。
今週の予定を確認すると仕事で遅くなる日もあり、他の本は読めない予感がする。このブログもお休みかな。
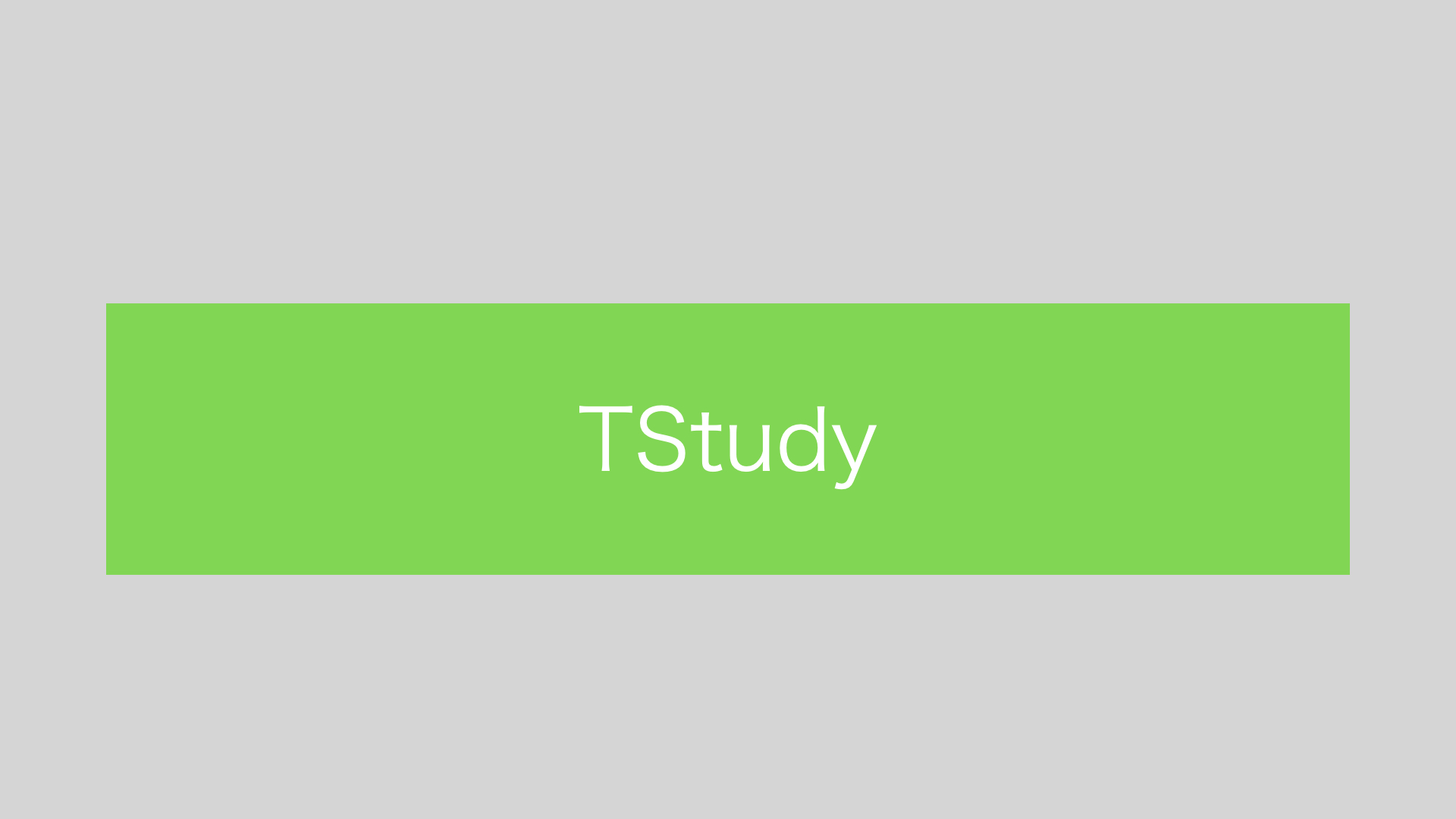

コメント