平沢慎也『実例が語る前置詞』くろしお出版、2021年
文法書や熟語帳で前置詞を学んできたが、本書はコアイメージに止まらない知識を垣間見せてくれる本である。
本書の学習姿勢は「使用基盤モデル」に沿ったものであるという(p.7)。
「使用基盤モデルとは認知文法という言語理論で採用されている言語モデル(言語とはこういうものだろうという想定)のこと」(同上)。
「使用基盤モデルは、本来、母語話者による無意識のレベルでの言語習得・使用についてのモデルなのですが、ある言語を外国語として学んでいる中〜上級の学習者が母語話者と同じように当該の言語を使えるようになりたいと本気で思った場合にはには、使用基盤モデルから学ぶべきことがたくさんあると思います」(p.8 ただし、「,」は「、」に変換している。以下同じ)。
抽象的な言い方をされているが、抽象知識と具体知識の両方を重視する姿勢であることは間違いない。しかし、「inの全ての用法に共通する性質を突き止めようとしてもーーいわゆる「本質」を探求してもーー目標の達成には直接寄与しない」(p.13)。だから、「アウトプットにおける具体知識優先の原則」(同上)が強調される。
「複数語レベルの具体的な言い回しの知識も、単語レベルの抽象的な知識もどちらも大事だと強調」(p.17)しているが、熟語を覚えよとは言っていない。追求するのはイデオム(予測不可能性)ではなく、よくある言い回しであり、具体的事例から抽象度の高い概念を見つけていくことで母語話者の発想を知ることができる。コロケーションを重視する立場をとっていない。コロケーションを重視する立場を「まず単語単体の知識を思い起こして、次にその単語が他のどんな単語と一緒に用いられやすいかの知識を利用する2段構えのプロセス」(p.23注3)とし、著者の言語観は「(可能な限り)真っ先によくある言い回しの知識にアクセスする姿勢」(同上)である。「単語があって次に組み合わせがあるのではなく、まずはじめに組み合わせがあると考える」(同上)。
『英語は決まり文句が8割』の著者の中田達也氏も「定型表現」を重視している。中田達也氏は非母語話者の第二言語習得に「定型表現」学習法の有効性を説明していた。本書の平沢慎也氏はフレーズを細かく分類するよりはインプットした事例をそのままアウトプットすることを勧めている。
本書は事例の収集と抽象化の仕方を例示している本であり、前置詞の全ての使い方がわかる本ではない。よくある表現を暗記して使い回しているのが日常の姿であるとする「定型表現」の世界に止まらない洞察に満ちている。
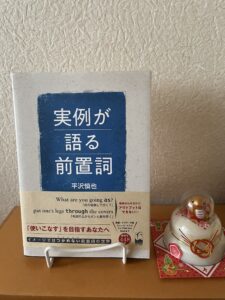


コメント