正岡子規『俳諧大要』岩波文庫、1955年、2025年改版第1刷
書誌情報
正岡子規『俳諧大要』は解説によれば、明治28年(1895)に「日本新聞」に連載されたものを、明治32年(1899)に「ほとゝぎす発行所」より出版したとある。
正岡子規の俳句はほとんど知らないので、俳句の入門者用に書いた本書でどんな主張がされているのか楽しみにしていた。正岡子規は過激な変革者というイメージがあったので、日本文学の伝統とは異なるのもであるから避けていたのだった。
今になって勿体無いことをしたのだと思うが、古今集に親しんだものとして、それを否定する価値観とは合わないと思っていたのだった。
修学第一期は俳句をものして先輩に教えを乞うのがよいとある。しかし、読んでて愉快になったのは以下のところだ。
「俳句をものせんと思い立ちしその瞬間に半句にても一句にても、ものし置くべし。初心の者はとかくに思ひつきたる趣向を十七文字に綴り得ぬとて思ひ棄つるぞ多き、太だ損なり、十七字にならねば十五字、十六字、十八字、十九字乃至二十二、三字一向に差支なし」(p.17)。尾崎放哉や種田山頭火の出現を予言しているかのようだ。
俳句を5千首から、一万首作ると第二期に入るというのも面白い。第二期と第三期は隔絶があるようだ。
第三期は「俳諧の大家たらんと欲する者のみこれに入ることを得べし」(p.102)。「第二期は天稟の文才ある者能く業余を以てこれを為すべし。第三期は文学専門の人に非ざれば入ること能わず」(同上)。ここで文学とは俳句のことだと理解した。
それにしても金気の粛殺たるとか疎豪など漢文を読み慣れていないと遣えない言葉が多く、正岡子規の生きた時代というものがこの頃偲ばれるのである。
具体的に例示した江戸に俳句を批評するところを見ていけば、正岡子規の着眼の鋭さもわかる。いずれにしても正岡子規の自作が載せらていないので、依然として私は正岡子規を知らないでいることに変わりはない。桑原武夫の『第二芸術』(1946年)ではないが、松尾芭蕉や種田山頭火なら何十首と暗誦できるが、正岡子規は片手に満たない状態では論じることなど不可能である。
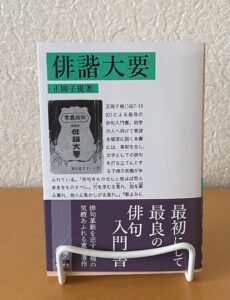


コメント