若松英輔『不滅の哲学 池田晶子』亜紀書房、2020年
オンライン読書会があるので、また『不滅の哲学 池田晶子』を取り出す。テーマは第一章 孤独な思索者(P5〜21)である。読み直すと何か別な観点が見えてくるのだろうか。
池田晶子を読んだことはないので、若松英輔氏の引用する断片からその言葉に触れることになる。
若松英輔氏の長い説明をメモする。
「だが、「言葉」と池田晶子が書くとき、読者は注意が必要だ、それは、私たちが通常感じている言語の領域をはるかに超えている。人間の肉体が「存在」の一部分でしかないように、言語は、「言葉」の一形態でしかない、言語でもありながら、姿を定めずに私たちの前に顕われる「言葉」をここでは「コトバ」と書くことにする。コトバは言語でもあり得るが、ときに色であり、音であり、また芳香あるいは、かたちでもある。温かみや寄り添う感触、不可視な存在感として感じられることもあるだろう」(P5〜6)。
池田晶子の使う「言葉」が若松英輔氏の云う「コトバ」を意味していることがあるとでも云うのだらうか。ただし、池田晶子は言葉について「コトバ」と書くことはない云う。若松英輔氏は「コトバ」を使って池田晶子の哲学を読み取ろうとする。池田晶子の言葉を引用したところを見てみる。
「「知識人」と自分の名刺に刷る人はいないのに、なぜ、このことばはいつまでも死語にならないのだろう〔中略〕このことばを捨てられない心性が、誰かのどこかに潜み続けているのだろうか」(『事象そのものへ!』)
ここで、池田晶子は「ことば」を単なる「知識人」を現す符牒の意味で使っている。
「月を指す指は月ではない
なんでこんなので納得できるのか
月も問う
指も問う
問い自体が問いの在ることを問うのである
何感覚
存在の動因」(『リマーク1997-2007』)。
若松英輔氏は絵を見るように池田晶子の言葉を味うことを勧める。
「これらの言葉を解釈することを止めて、しばらく一枚の絵だと思って眺めてみよう。ただ、感じる。言葉が動き出すのを感じるまでじっと見つめる。そのとき、私たちは、言葉がコトバへ還ろうとする瞬間に立ち会うことになる」(P27)。
ここで「コトバ」が若松英輔氏によって使われるが、井筒俊彦の『意識と本質』を経たものにとっては、「コトバ」は単なる「言葉」ではない。この後で、若松英輔氏は井筒俊彦の『意識と本質』を引いて存在の深みを探ることを云う。
池田晶子を引用したなかで「言葉」や「ことば」を定義したものはこの本には見当たらなかった。
課題図書なのに余計なところが気になるのは、集中できないためである。同時代人を論じるのは厄介である。同じものを読んでいるが、受け止め方が異なるのは「バカの壁」のせいかも知れない。
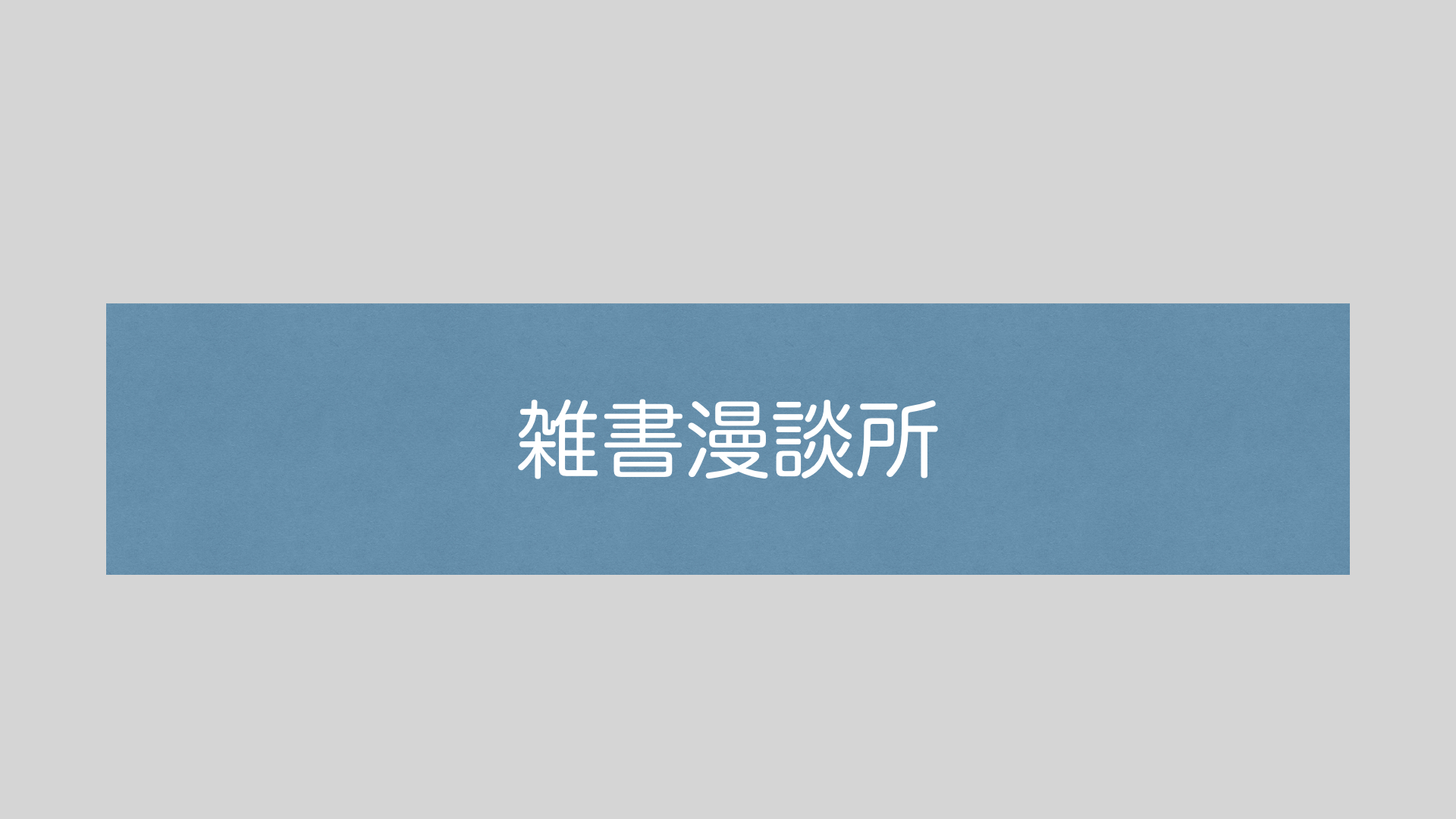

コメント