桃崎有一郎『京都を壊した天皇、護った武士 「一二〇〇年の都」の謎を解く』NHK出版新書、2020年
やっと後醍醐天皇の話になりました。本書は院政期に始まる「京都」を論じた前著に続いて鎌倉時代から南北朝時代の「京都」を論じて、土御門内裏が現在に繋がる「京都御所」の原型であることを明らかにします。
長々と読んできて、P167から186が桃崎有一郎氏の言いたかったことのようです。
第十章 後醍醐の内裏放火と近代史学の闇ーー足利氏の冤罪を晴らす
「建武三年(1336)正月一〇日の京都突入戦で、(省略)。根本内裏の富小路だのが焼失したのである。この事件を、京都を攻撃した足利軍による放火だとする説がある」(P173)。
「東京大学(戦前は東京帝国大学)史料編纂所が作っている『大日本史料』や、戦前に宮内省が作った『後醍醐天皇実録』で、その説が採られている」(P174)。
「足利軍を放火犯といい張れる材料は、信頼性が低い⑦の『太平記』だけだ。仮にその記載を真実だと認めても、まだ歪曲がある。⑦が述べているのは、逃亡した後醍醐に付き従った側近たちの家に足利軍が放火して、内裏に延焼したことだけた。「足利軍が内裏に放火した」という理解は、『太平記』からも導けない拡大解釈である」(P178)。
そして、『太平記』の古態本である西源院本では、名和長年が⑧「「敵の馬の蹄にかけさせんよりは」とて、内裏に火をかけ、今路越に東坂本へぞ参ける」(P180)。
名和長年が内裏に放火したとあります。誰が名和に命じたのでしょうか。後醍醐天皇にほかならないと桃崎有一郎氏はいいます(P182)。独断ではあり得ないからです。『太平記』の流布本では、名和のエピソードが削られ、放火の罪を足利軍に着せる改竄がなされたといいます(P183)。
後醍醐天皇は読み直す必要があると思いました。
そして、京都御所は誰のものかという桃崎有一郎氏の問は重いと受け止めました。
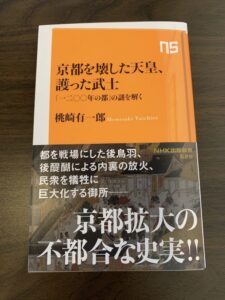
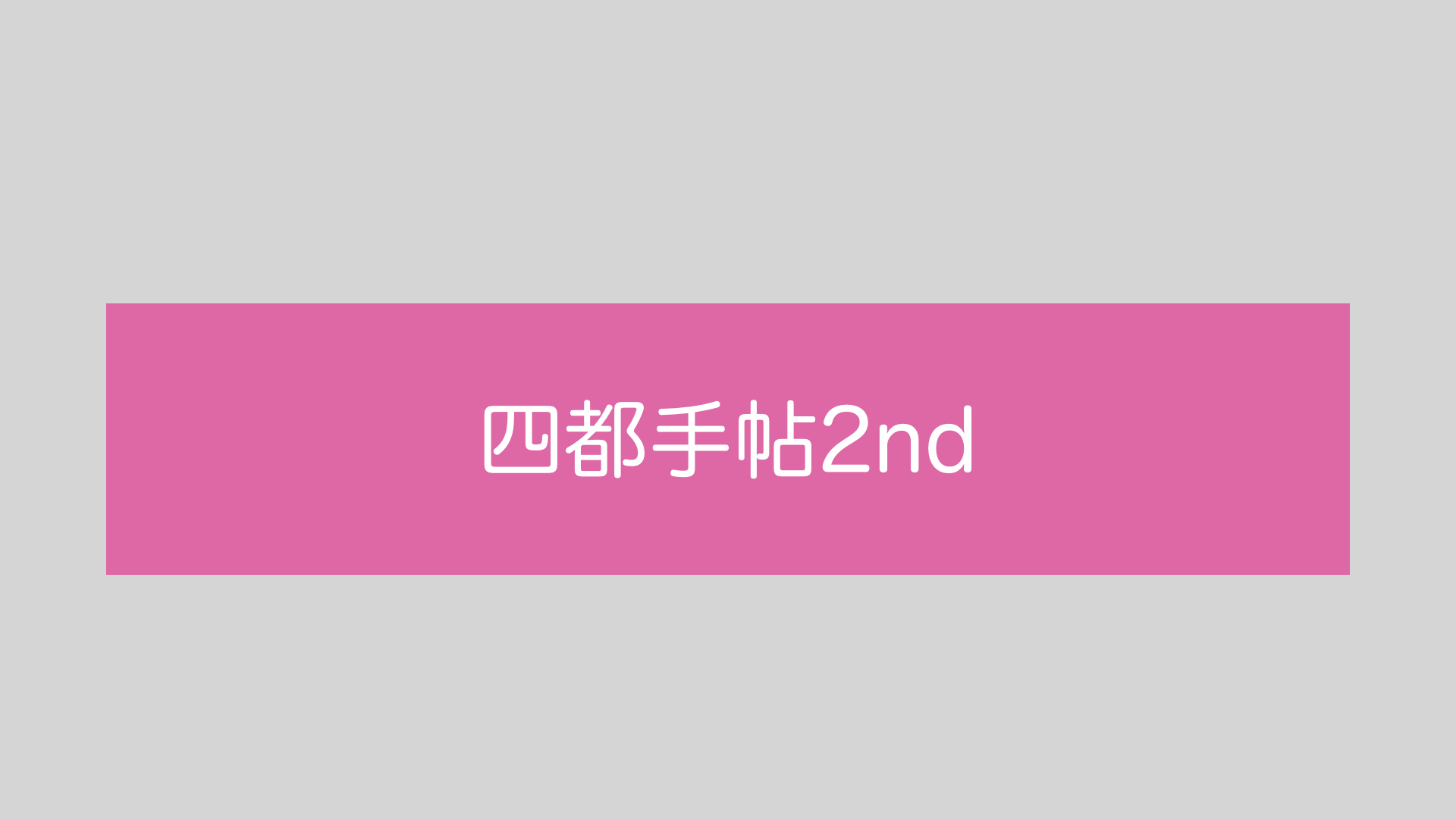

コメント