日本古典文學大系月報(昭和41年6月)で中村幸彦が「文学としての近世思想家文集」として『近世思想家文集』を通覧しているが、その前半が気になった。
「私は初学道に入るの門で聞き覚えた、文学(芸術)は表現であるとの説を、後生大事に持ち続けている。広狭様々に解せる表現の語を、文学を意識した美しい文章(韻文をも含めて)によると、更に制限して、形式的に文学と非文学とを区別して来た」。
この辺りを読んでみたいが、中村幸彦は『中村幸彦著述集』を読むしかないと思っているので、仕事を辞めて、関係書籍がいらなくなったら、綺麗に処分して、死ぬまで好きな本を読んでいようと思う。当面は存命中の先生方の話を聴いていたい。詰まる所、本よりは実物の方が刺激されるのだ。亡くなられた先生にはもう聞くことはできない。
「中国の古典は一語一句の中にも、思想がどっかと存在するのに、日本の古典は抒情的で、あえかではかな過ぎる」。
「あえか」は小西甚一の『基本古語辞典』によると形容動詞で、もろさを感じさせる優美さをいうとある。
ただ、この中国の古典がどの辺りのことを指しているかは注意したい。
中村幸彦が以下5編は独創的思想の書といっているが、紹介するまでもないだろう。前2編成はともかく、後3編はまだかじってもいないので確かめようがない。課題図書は「都鄙問答」である。なので、卷之一にある商人ノ道ヲ問ノ段はともかく、卷之二の中の鬼神ヲ遠ト云事ヲ問ノ段、卷之三の最初の性理問答ノ段が今の興味ある点である。
伊藤仁斎「童子問」
石田梅巌「都鄙問答」
安藤昌益「自然神営道」
富永仲基「翁の文」
本居宣長「玉くしげ」
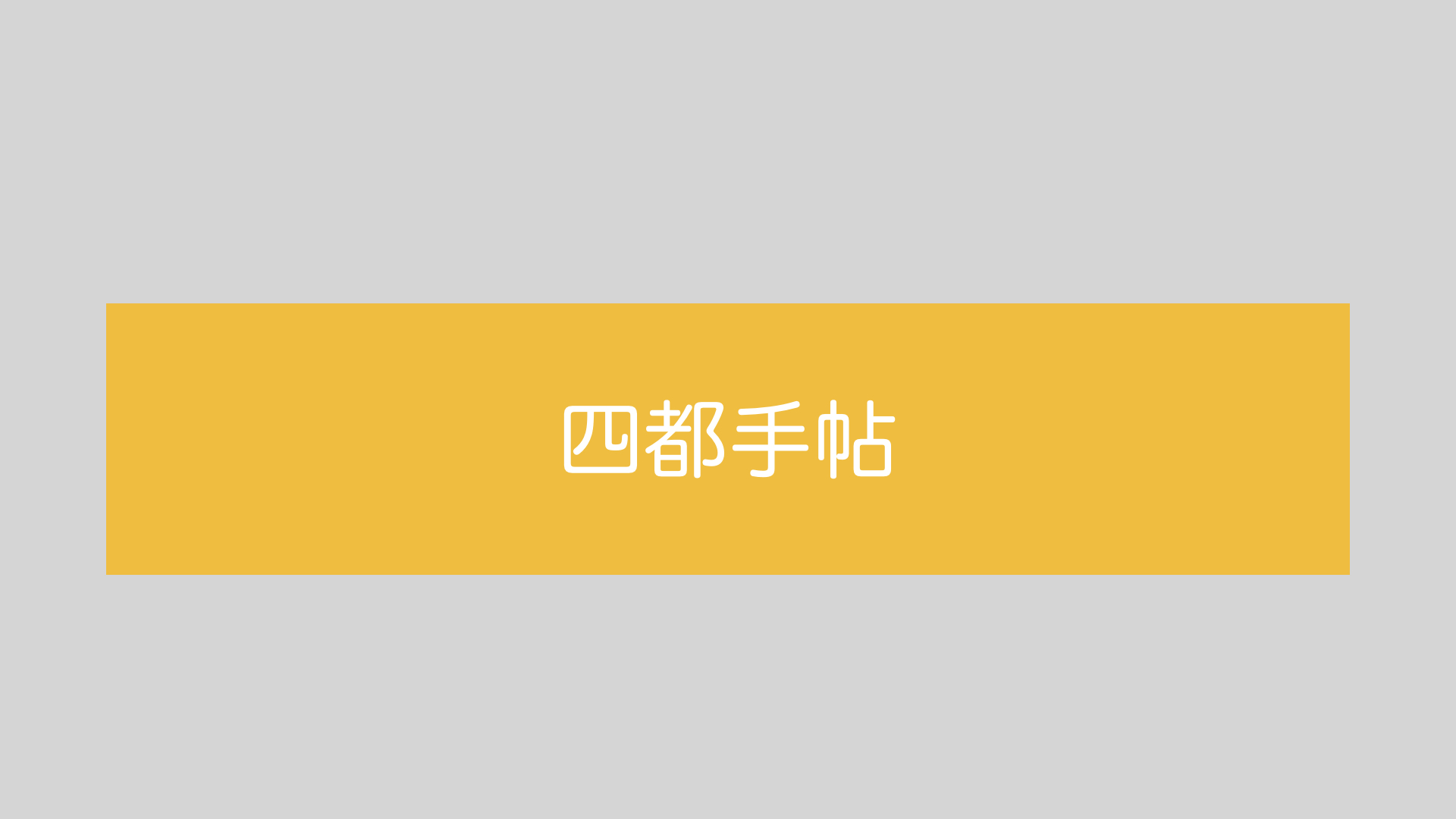

コメント