谷沢永一、渡部昇一、山崎正和、林健太郎、高坂正堯、山本七平『古典の愉しみ』PHP研究所、1983年
私は高坂正堯の「『古寺巡礼』日本の宿命を凝視する眼」を読んで和辻哲郎の読み方を教わった気がした。
しかし、「今、思い出してみても、浄瑠璃寺への道の風景描写などは実に素晴らしい」と書いてあるが、思い出せなかった。堀辰雄の浄瑠璃寺の道は覚えているのだが、和辻哲郎の方は思い出せないでいる。
『古寺巡礼』の中に日本人論が見えると高坂正堯が言う。
21 「月夜の東大寺南大門ー当初の東大寺伽藍ー月明の三月堂ーN君の話」のなかで「日本人は堕落しやすい。」と和辻哲郎が書いている。「わたくしは中門前の池の傍を通って、二月堂への細い樹間の道を伝いながら、古昔の精神的事業を思った。そしてそれがどう開展したかを考えた。後世に現れた東大寺の勢力は「僧兵」によって表現せられている。この偉大な伽藍が焼き払われたのも、そうした地上的な勢力が自ら招いた結果である。何ゆえこの大学が大学として開展を続けなかったのであろうか。何ゆえこの精神的事業の伝統が力強く生きつづけなかったのであろうか」。
高坂正堯が和辻哲郎も戦前の学者としての共通の限界は免れなかったと指摘しているのが面白い。「それは当時の知識人が西洋の俗事にややうとかったという」ことだという。「社会の運営に関して、例えば株の運営に携わる人々と知り合い、その内情を知ることはなかった」。「戦前の学者の場合、外国の原理の一面をとらえて、それが支配的であるといい過ぎることろがあるのを見てもわかるように思います。その典型的なことをいえば、教科書にかかれているようなイギリスの議会主義に関する記述です」。「教科書はイギリス議会を理想化しているわけですが、イギリス議会の歴史を見ていると、教科書に書いてあるように素晴らしかったことはたまにしかありません。実際には金も動いたし、陰謀もあったし、相当なものです」。
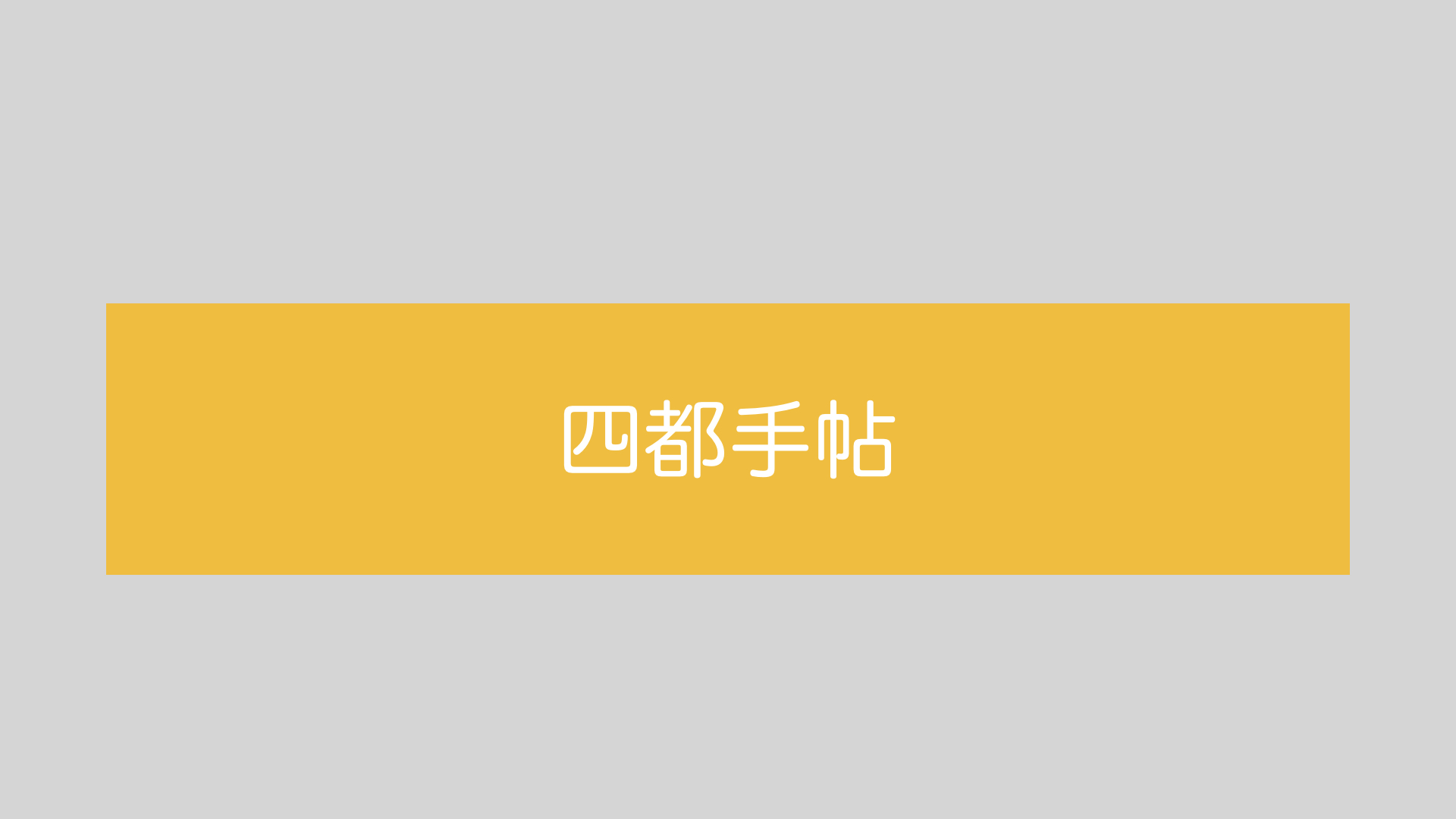

コメント