黒木登志夫『研究不正 科学者の捏造、改竄、盗用』中公新書、2016年
研究不正の古典的名著としてウイリアム・ブロード、ニコラス・ウェイド、牧野賢治訳『背信の科学者たち』(講談社、2014年)があげられていた。
原作は1983年で翻訳が1988年に出たものが、2006年に緊急復刊され、2014年にもSTAP細胞とノバルティス事件で復刊された。
我々が新書を読むのは、このような「古典的名著」を知ることができることも一つの理由だ。しかし、不正が繰り返し起こる中、本書にあげた42の不正事例を知り、不正が無くならない理由や対策を考えることは、職業として関わる以上避けて通れないところだ。
NHKスペシャル 「天使か悪魔か 羽生善治 人工知能を探る」でも、人工知能のアンチヒューマニズムというか、人間を無視することが人類のリスクに繋がるという点が指摘されていた。なんか鎌田東二教授の伊藤若冲への感想を思い出してしまった。番組では不正発見を人工知能が予測する場面もあった。論文不正の一部は、人工知能を使うことで発見が可能であろう。
羽生善治氏が最後に「倫理」をどう人工知能に持たせるのかと言っていたのが印象に残った。
研究不正については、以下の情報を参考までにあげておく。
撤回論文監視
Retraction Watchというサイトが著名である。

Retraction Watch
Tracking retractions as a window into the scientific process
WILEYが出版倫理最良実践ガイドライン第2版を出している。出版社の視点からする不正への取組みである。
出版倫理最良実践ガイドライン第2版
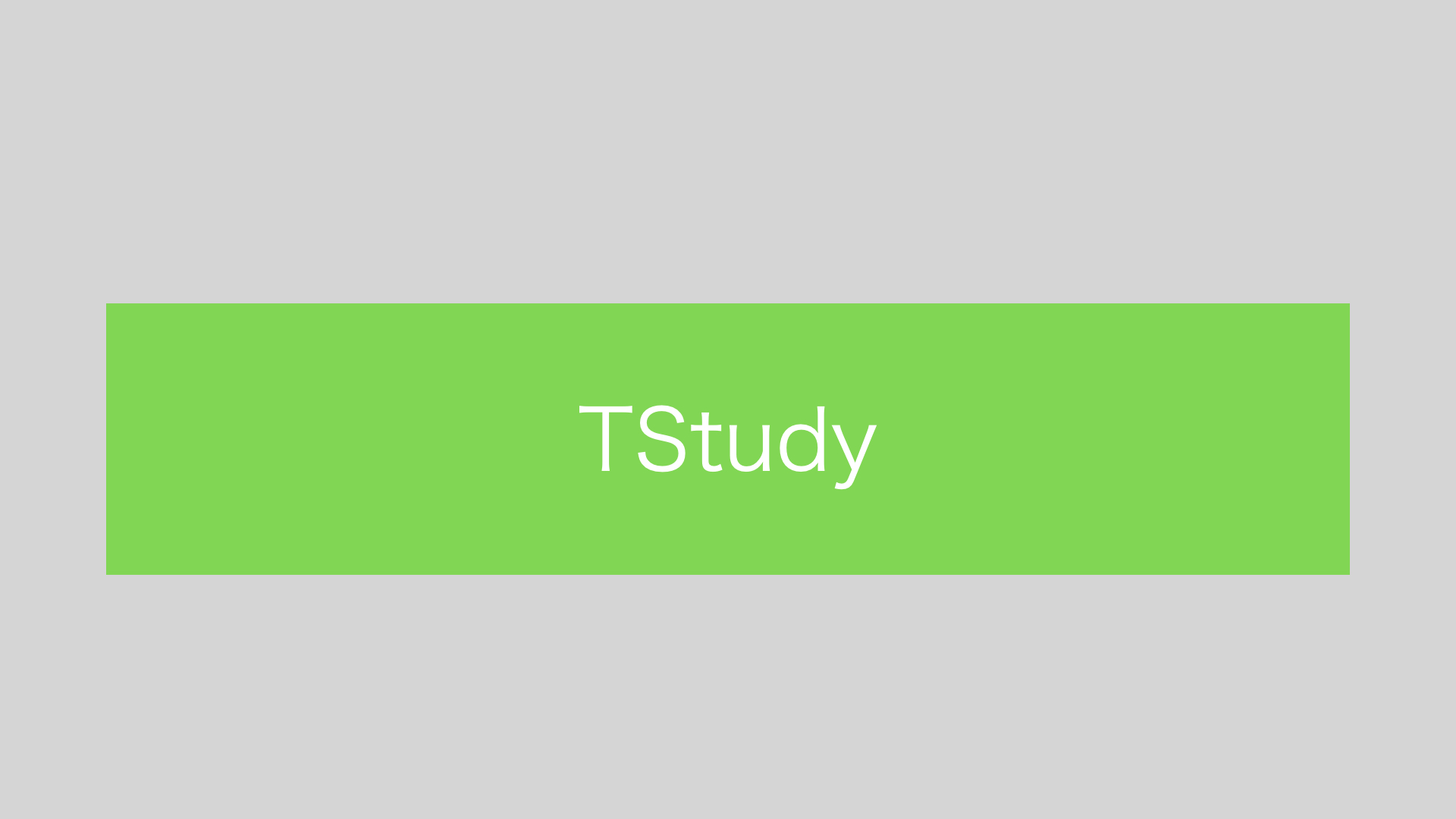

コメント