そう言えば通史というものは、高校の教科書以来読んだことがなかった。まあ、それも記憶に残っていないし、いまさら教科書でもあるまい。何か適当な本はないかと、『日本書紀』の現代語訳を買ってみたのだが、10分で眠くなった。
日本の通史を死ぬまでには読んでおこうと思い立った以上、最初から最新の岩波に投資してもよいのだが、いかんせん敷居が高い。その点で原本が1965年から1967年とちょっと古くなったが、中公文庫の日本の歴史は著者も名前くらいは知っているので、トライしてみることにした。
まずは、好きな奈良ということで、『日本の歴史3 奈良の都』を選ぶ。井上光貞氏からスタートしてもよかったのだが、パラパラめくった感じで文体が平易な青木和夫氏を選んでみた。
奈良時代を扱う史料は『続日本紀』である。『続日本紀』については現代語訳で読んでいるのだが、著者の感想と同じ思いだ。長いが引用する。
「第一、くわしさがちがう。前半二十巻が孝謙女帝の譲位まで六十一年間の記事をおさめるのに、後半は同じ巻数でその半分の歳月を記述する。つぎに質がちがう。前半はもと三十巻だったのを圧縮したのだが、けずった理由は、「語に米塩多し」であった」(20頁)。
何が削られたのかはわからないけど、「ささいなことなど史書には記すべきでなく、「声教」や「勧徴」、すなわち教育や道徳こそ、歴史に徴して論ずべきだったのだろうが、われわれにはそうはゆかない。けずられてしまった詳細が今日に伝わっていたら、と思うと残念である」(20頁)。
注意すべきは、事象の統計をとる際の記述基準が異なっているとするならば、単純に比較ができないということだ。
例えば、「奈良時代前後の疫病の研究ー『続日本紀』に見る疫病関連記事を中心に」(菫科、関西大学、『東アジア文化交渉研究第3号』2010年)では、青木和夫氏のこの著書を引きながら、慎重に検討している。
この本が気に入った理由は、とにかく数字がよく出てくることだ(逆の人もいるかもしれないが)。規模感が分かると、今と違った政治都市である平城京が見えてくる。但し、解説で丸山裕美子氏が指摘しているように、その後の研究成果により推定数字は問題がないとは言えなくなっている。例えば「都の人口二十万」という説は、もっと少なく十万と見る見解が有力なのだそうだ。半世紀前の研究水準であることは注意したい。
谷沢永一氏が言っているように、どんな著者の話でも鵜呑みにしてはならない(『本はこうして選ぶ買う』)。
索引まで入れて585頁あるので、電車の中で読んだらいつ読み終わるかわからないけど、しばらくはバックに入れておきたい。
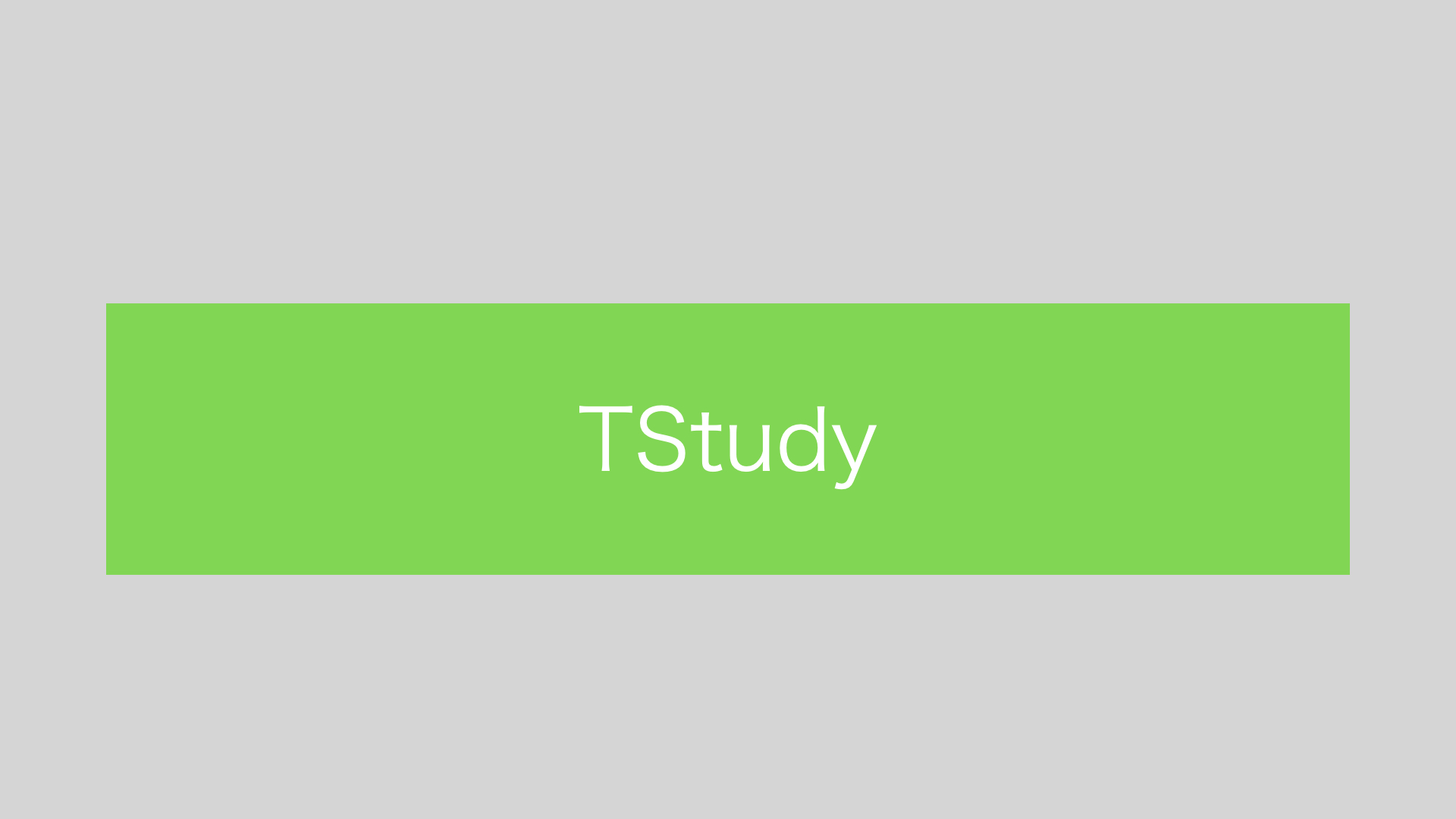

コメント