外山滋比古『忘却の整理学』筑摩書房、2009年
そういえば、外山滋比古は先月に亡くなっていた。正確には2020年7月30日のことで、96歳であった。この人は英文学者だったが、エッセイを読んできた。
『思考の整理学』(1983年)の後に出た本で、「整理学」と謳った単行本はこの二冊である。『読みの整理学』(ちくま文庫、2007年)は、『読書の方法』(講談社現代新書、1981年)を文庫化に際して改題したものだ。『老いの整理学』(扶桑社新書、2014年)は新書である。
外山滋比古は長生きしてエッセイをたくさん書いたので同じような話題が多い。だから、追悼の意味で読む本はどれでもよかったのであって、特に役に立つからなどど理屈で選ぶ必要はない。
ただ、年をとって「忘却」を毎日のように感じるようになると、自分も「忘却」について考えることになるので、この本を読んでもよい時期になったと思う。
将棋の番組を見ながら棋譜を録っていた時は、棋譜を暫く頭の中で再現することができた。将棋盤に駒を並べて棋譜調べてをしていた時とコンピュータで自動で棋譜が再現されるようになって、手順の再現能力は明らかに落ちたと感じる。以前は手が覚えていた。そのくらい当時は棋譜を見ることは少なくて月刊誌か将棋番組しか情報を得ることが出来なかった。
今は、対局の翌日には棋譜が無料で手に入るので、結果を知るのは早くなったが、『近代将棋』の解説を読みながら、棋譜を並べて自分なりに結論をだすことをしないので、手順の意味も分からず進行を見ているだけになっている。棋譜も記号では処理できない人が多いので、アプリは駒の動きに変換して見せるので、局面を全て見ることができる。本や新聞では選ばれた局面だけが掲載されているので、棋譜を並べて見なければゲームの展開は分からなかった。
忘却ということばを将棋に当てはめればそれなりのエッセイになる。しかし、これ以上は思い出になりそうなので、本に戻る。
記憶と忘却はセットであると外山滋比古はいう。呼吸に喩えている。呼吸は吐いてから吸う。記憶も、まず、忘却という整理が最初だという、コンピュータに喩えると初期化であろう。ただし、人間は確かめようがない。だだし、忘却という整理を経ないと記憶も強く残らない。
「一般にはしかし、ものを覚え、ものを知って賢くなるように考えられている。それはその通りかもしれないが、その前に、しっかり、頭を整理しておくことを忘れてはいけない。整理とは余計なものを捨て、邪魔なものをとり除くことーーつまり忘れることである。これが、記憶のあとではなく、先行しなくてはならないというのが、この忘却論である」(P52)。
外山滋比古の直観が当たっているような気がする。記憶のメカニズムの本を読みたくなった。
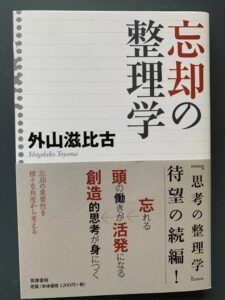
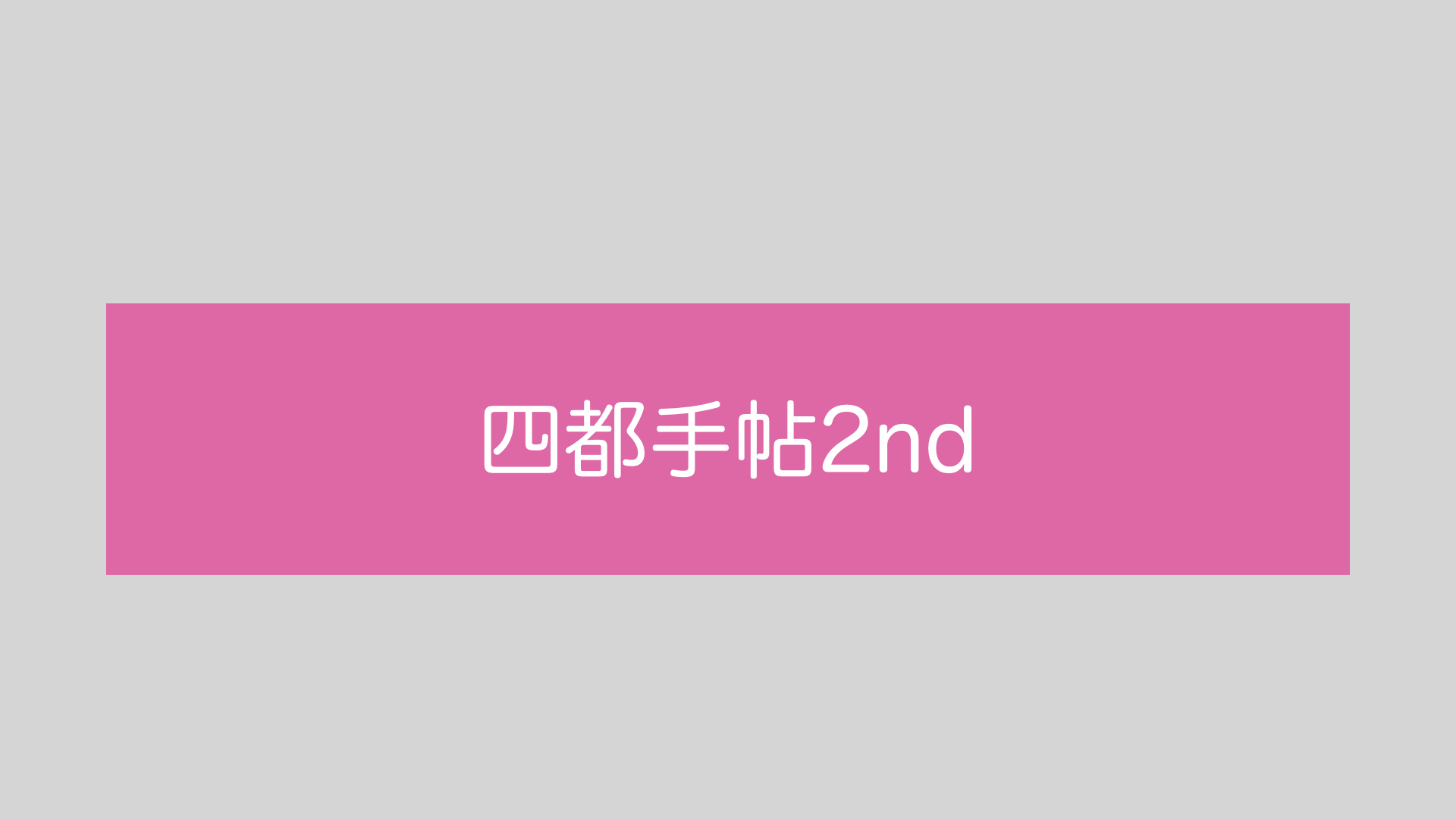

コメント