入江相政『余丁町停留所』人文書院、1977年
昭和天皇の侍従長を務めた入江相政(1905-85)の名前を久し振りに思い出したのは、書肆スーベニアの本棚にあった本の背表紙を見たときだった。同時に面長な顔を思い浮かべたのはよくテレビで見る顔だったからだ。これを読んでいる若い人は今の侍従長を含めて興味ないだろうが、侍従を長く務めたことで当時は世間ではよく知られた人だった。
「私の京都」
藤原定家の子孫であるが東京生まれの入江相政(いりえすけまさ)にとってふるさとは東京ということになる。しかし、生まれ育った町名もなくなり、高速道路の下に埋もれてしまえばもはやふるさとではなくなる。父が育った京都をふるさと思っているという。そのふるさと感はちょっと変わっている。
“ただ、私の抱く京の幻とは、大正中頃のもの。春の日長に、北野から嵐山まであるいたがその感、仁和寺の山門の前で、牛車を見かけたくらいで、ほかには出合うものもなかった。あの頃の京。私が心に強く抱きしめている「ふるさと京都」はあれなのである。”
「京の幻」などとあると、西川照子氏の『幻の、京都』(2014年)を思い出すが、牛車とは畏れ入る。
日曜日の朝にひかりで日帰りしたと書いてあるのが時代を感じさせる。真如堂へ墓参りして、「いづう」の鯖寿司、「かね正」の茶漬鰻を土産にし、昼は「しる幸」か「平野家」にするか、権兵衛か河道屋のそばか。夜は三島か堀川の木藤と書いてあった。
昭和天皇が好きな鰻茶漬を侍従として見ていたのだろうか。店の選択は私も重なるところがある。
「余丁町停留所」
本のタイトルとなっている「余丁町停留所」は入江相政の父の入江為守が1916年3月に永井荷風から余丁町の地所の半分の五百余坪を譲り受けて住むことになったでので、入江相政が砂土原町に家を建てるまでは学習院や東大に通った停留所だった。
余丁町にいつから住んだかははっきりしない。入江相政は永井荷風を一度だけ庭で見かけたと書いてあり1918年で小学六年生だという。『断腸亭日乗』を読むと1918年11月末に永井荷風は余丁町の屋敷を売却して12月には築地へ転居しているので、入江相政が移り住んだのは1918年4月以降のいつかと思われる。
“うまれたのは麻布の笄町、(省略)。その後、西大久保、白金三光町、麹町の六番町と転々して、牛込余丁町に落ちついた。いまは新宿区余丁町、大正七年のこと。亡父は永井荷風から地所の半分の五百余坪を譲り受けた、私は小学六年生。
当然ながら越してからしばらくは、見るともなく、庭を散歩する荷風の姿を見たものだった。わざわざのぞいたわけではない。少し尾籠で恐縮だが、私の使う便所の窓から、自然荷風のうちの庭が見えた。だから荷風が庭にたたずんだ姿を一度だけ見たのである。”
一度しか見ていない割には何度も見かけたようにも受け取れる変な文章である。
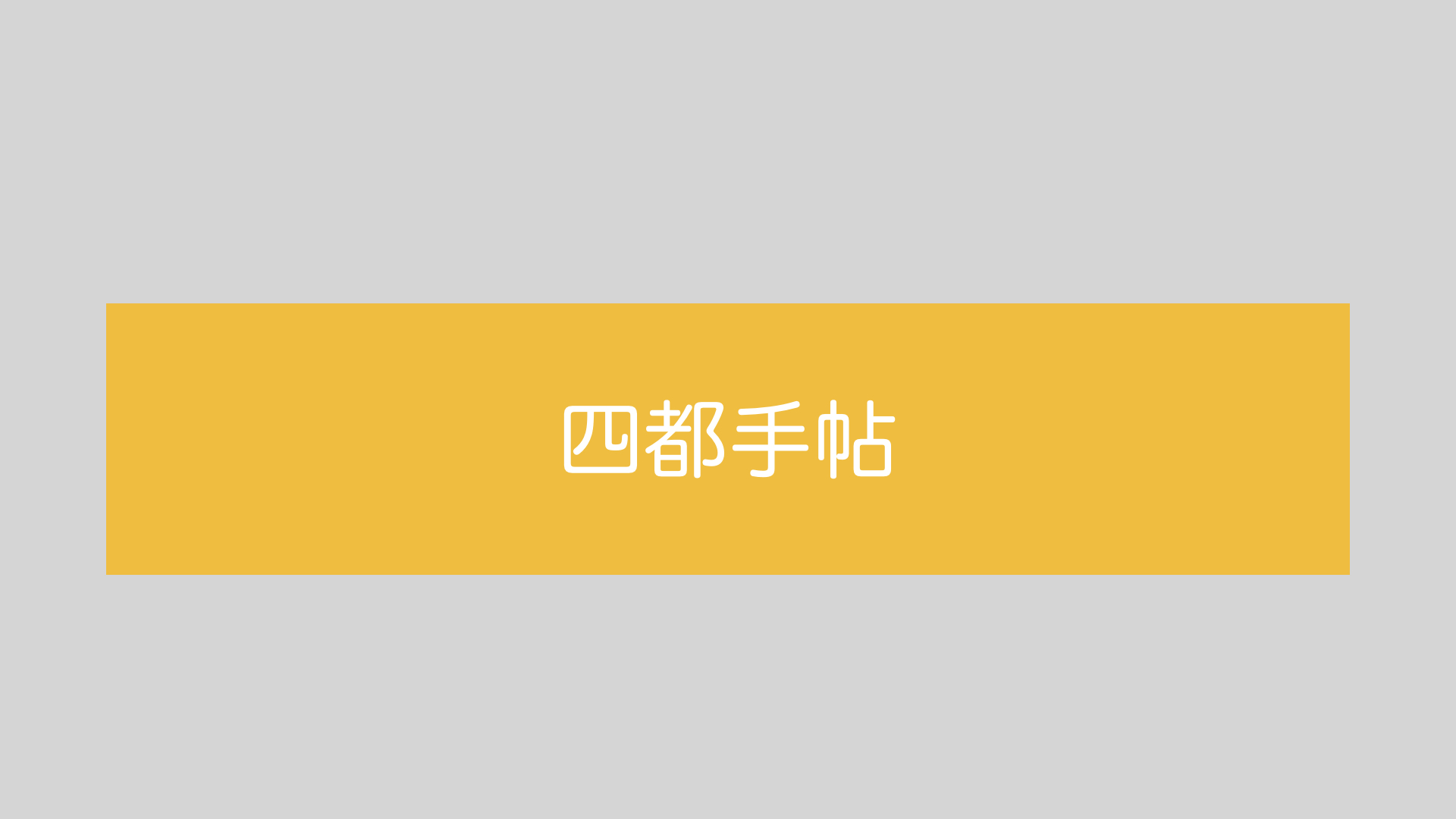

コメント