東洋陶磁美術館で「朝鮮時代の水滴ー文人世界に遊ぶ」
大阪歴史博物館の「関西大学の本山コレクション」の中吊り広告が面白すぎてよく分からなかった。予定通り、淀屋橋で降りて東洋陶磁美術館へ行く。
朝鮮では水滴を硯滴という。
中国よりの輸入から、朝鮮での製造が始まったのは、李朝朝鮮前期15世紀であるという。展示では、青磁彫刻 童子形水滴と童女形水滴が高麗時代の12世紀として最初に展示されていたが、あとは朝鮮時代のものだった。コバルトの輸入が限られていたため、粉青、鉄砂のものが多い。コバルトが高価なため、青花のものは官製の窯で焼かれた。
18世紀よりコバルトの輸入量が増え、青花の硯滴が多く造られるようになる。19世紀になると多彩な硯滴が見られるようになる。
大阪市立東洋陶磁美術館
2016年8月13日〜11月27日
9:30〜17:00
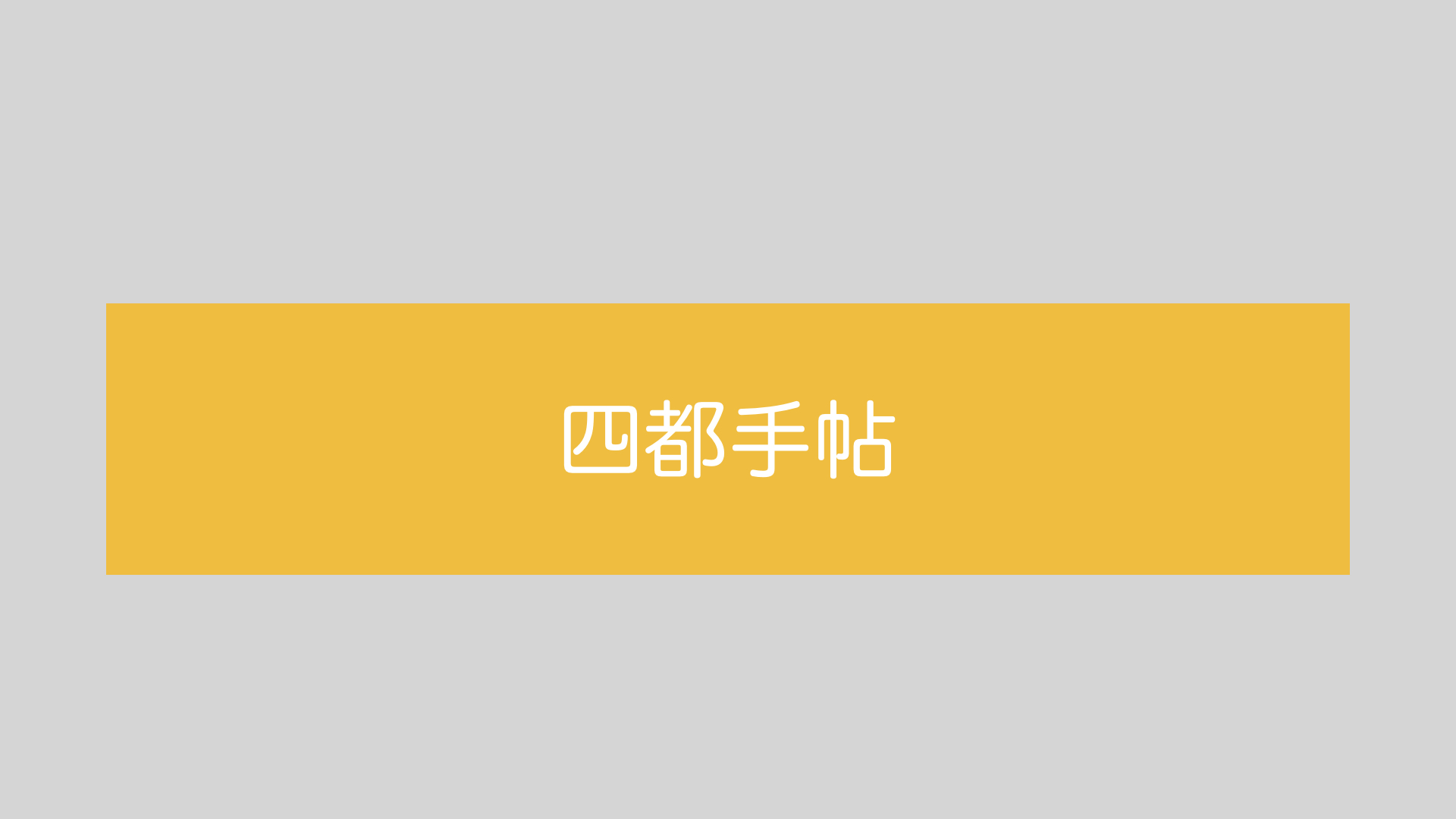

コメント