1.適正な本の量とは?
普通の生活をしていると、寝床の周りに積んである本を読むことで一年は経ってしまうに違いない。1日で1冊読める本はほとんどない。まして、ライブラリーや居間の本棚と洗面所の段ボールや玄関の段ボールは開けるまでもなくもう読まれないに違いない。外部倉庫の捌き先も片貝孝夫氏が亡くなったので、宙に浮いたままだ。
2.本を読んでいる時間は短い
本を読む時間はそれほどない。掃除、洗濯、食事、入浴などをした残りの時間で、仕事上で必要な新聞を読み、専門誌を読み、ブロクを読み、WebinarをしてCPEを稼ぎ、ポッドキャストを聴いて耳からも情報を仕入れている。
本は、通勤時間や昼飯の時に読むことになる。後は寝床で眠気が起きるような本を開けばすぐに眠ることができるし、このようにブログを書いていればいつまでも起きていることになる。本を読むことができないのは言うまでもない。
3.本のことをブログに書くことのジレンマ
このブログも付き合いで見てくれる人がいる限り、私も付き合いで書くのだろうか。お互いに読書時間を削って、ブログを書いたり、ブログを朝から読んだりする悪しき慣習は改めるに限る(^o^)/
ブログを書くのは、読んだことを忘れてもいいようにメモしておくためだった。買った本をメモしないと、また、間違って買ってしまうためだ。部屋の中を探しても見つからなくて買ってしまった本が土曜日に2冊もでたのは痛手だったが、記憶と本の内容が違ったので、記憶を修正できてよかった。
4.メモは使える形にしなければ、再利用できない
メモが必要というならEvernoteにメモれば済むことなのだろうか?
ブログに書くのはコンテクストの中にメモを入れるためであって、ただのメモはほとんど再利用されずにいる。使える形にしておかなければ、時間がたてば使えなくなる。講演会の資料なども、使える形でまとめておかないと、結局は使えなくなって鮮度が落ちれば捨てることになる。
5.実務知識は常にアップデイトが必要
会計などの実務知識は、法律の体系に沿って整理されていなければ使えない。何度も読んだり、ラインを引いたり、プレゼン資料を作ったりして、常に自己の記憶のメンテナンスが欠かせない。
マーケティングなど、正解のない領域は何故かという問題意識が重要であり、仮説と検証の観点で整理しなければ使える知識とはならない。
今井むつみ氏は知識について直球勝負している。知識は体系であって、事実の断片の集まりではない。「知識」と記憶の関係を最新の認知科学でおさらいすることにしょう。
今井むつみ『学びとは何かーー〈探求人〉になるために』岩波新書、2016年
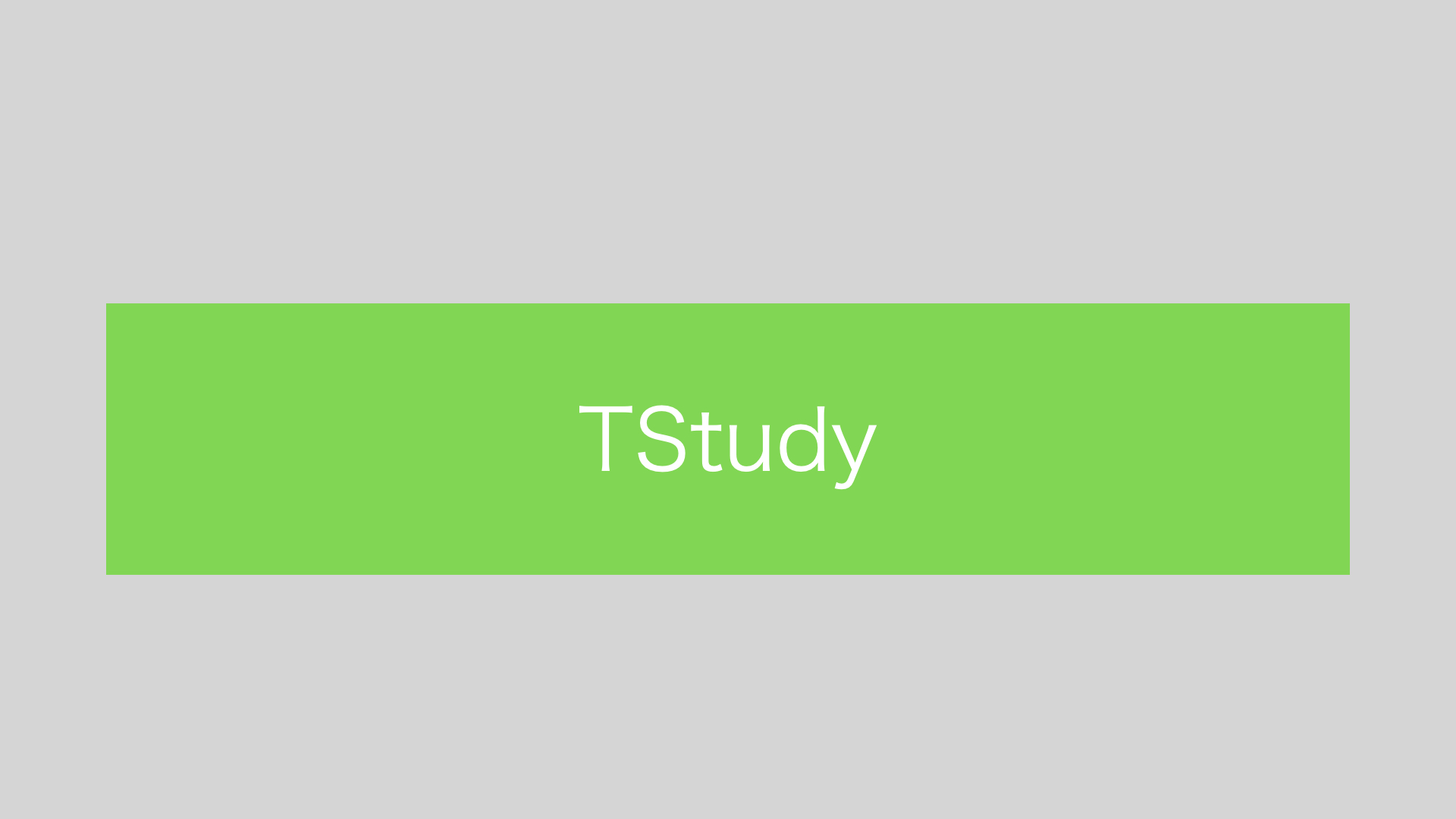

コメント