森敦『新編 意味の変容』ちくま学芸文庫、2024年
書誌情報
『意味の変容』論ーー「解説」にかえてで柄谷行人氏は「1984年に筑摩書房から出版された森敦の『意味の変容』は、もともと1974年から1975年にかけて雑誌「群像」に連載された作品を改稿したものなのだが、さらにそれ以前に断片的な先駆稿がある」(p.444)と書いている。
本書の書誌情報は「本書は、2012年1月刊講談社文芸文庫『意味の変容・マンダラ紀行』および1993年3月筑摩書房刊『森敦全集』第二巻を底本とし、旧字を新字に改め、適宜ルビを加えた」(p.459)とある。
長々と引用したのは、森敦が改稿に時間をかけた意味を柄谷行人氏が指摘しているからである。
柄谷行人氏の切り口は面白い。森敦が改稿により削除したところを『森敦全集』第二巻から3箇所引用している。ここでは、その一部の「わたしはこの「最小の幾何学」を近代の智脳のつくったすばらしい「寓話」だとおもい、「寓話」もまた一種の「最小の幾何学」だとおもいました」という条りをあげたが、柄谷行人氏は森敦の「寓話」を受けて、「『意味の変容』が寓話だということは、それが近代小説ではないということでもある」(p.447)と返している。
先日から読んでいる『一即一切、一切即一 ーー『われ逝くもののごとく』をめぐって/森敦対談集ーー』(法藏館、1988年)の2頁の金剛界と胎蔵界の説明が何度読んでもわからなかった。森敦が「意味の変容」という本を書いたと瀬戸内晴美氏との対談で言っていたので(p.42『一即一切、一切即一』)。そこで、『新編 意味の変容』を近くの本屋で見たことを思い出したのである。森敦の本が出るのは珍しいなと思ったくらいで、井坂康志氏の『ドラッカー 「マネジメントの父」の実像』(岩波新書、2024年)を見つけてそちらを買ったので、その時は買い忘れてしまった。
柄谷行人氏が書かれたものを読んで、「意味の変容」ということが森敦の『われ逝くもののごとく』を理解するためのキモであることがわかった。
本丸へはなかなか辿り着けないのが山城の工夫である。『月山』まで戻る覚悟が必要かもしれない。
注)
「任意の一点を中心とし、任意の半径を以て円周を描く。そうすると、円周を境界として、全体概念は二つの領域に分かたれる。境界はこの二つの領域のいずれにか属さねばならぬ。このとき、境界がそれに属せざるところの領域を内部といい、境界がそれに属するところの領域を外部という」(pp.22-23)。
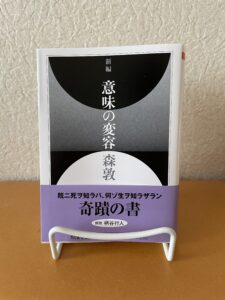


コメント