相変わらずココログの混乱は続いている。この失敗事例から我々は何を学ぶのだろうか。
時は経つものである。その感じ方は年齢や体調によっても一定ではない。日々、少しの時間を捻出して読書やblog書きに充てている。もっとも、長時間の読書には耐えられない身体になった。書きたいことがそうあるわけでもない。仕事で読む本は、内容を吸収し、使うことが目的なので、要点をメモに取ることもある。そもそも読み方が違うので、別の機会に書くことにして、ここでは余暇に読む本について書くことにしよう。
推理小説は別として、読んで楽しかったで終わってしまっては、残念なこともあるので、メモしてきたのはこの数年のことだ。時々、公開していないメモを読み返しては、メモを更新したりしている。自分が感動しないことはメモしても仕方ない。研究や勉強のために読んでいるわけではない。人それぞれに異なる面白さを味わうために読んでいる。自分の波長に合う著者の本が多くなることになるけど、同時代を生きている人の本は年に何冊も出ないので、長い時をかけて読んできたことになる。宮城谷昌光氏の本など年1冊として30年を超えている。森浩一先生の本も先生がお亡くなりになるまで毎年楽しみにしていた。
blogを書くようになってwebにメモを残すとどこでも検索できるからいいと思ったが、ココログの検索機能が使えたものではないので、iCloudのPagesにメモを定期的に保存するという原始的な方法でやっている。スマホのアプリ内の保存すると機種交換やサービスの変更の時に困るので、依存性の低いやり方にしている。Evernoteの検索もあてにならないので信用していない。メモにメモするというのもメモの数が3千を超えたくらいからストレスを感じるようになって、メモをアーカイブすることで、減らすことにした。
宮城谷昌光氏の本もかなり読んだ。しかし、手元にはあまり残っていない。これは若者達が売れるので処分したためだった。『湖底の城』の時はどうせ売るならシリーズが完結してからが高く売れるのではないかと抗弁したが、聞き入れてはもらえなかった。買った時に読んで反芻してそのまま読み返されることがないのを知っているのだ。好きなフレーズに付箋を貼ってあっても、抜書きをしないでいることは、彼、彼女達の感覚からすれば、重要ではないということになる。だからというわけではないが、最近の本はblogに感想を書いておいた。手元にない本がblogに記憶されているのも変な感じがする。何度も読み返す『孟嘗君』5巻と『奇貨居くべし』5巻は逆にblogでは検索できない。毎年1冊という意味では子安宣邦先生の本を読むのを楽しみにしているが、感想を書けるレベルではないので、付箋だけにしている。これは若者達も手を出さないので安心しているが、課題図書で買った本は箱の中にしまっているので、いつか気がつけば、処分されてしまうだろう。
人生のend gameをプレイするに当たり、仕事の本をこの数年で片付けてきた。さて、次は楽しむための本とレファレンス本である。人に任せていたが、これは自分でしなければ、若者達も本の価値がわからないので手出しできない。別れは悲しいが、断腸の思いで片づけることにする。箱を開けては1冊ずつ選ぶことをすれば、1日1箱で約3か月。いつだって途中でやめるから、最後まで行かないかもしれないが、花火の前に首を洗って差し出す覚悟である。
注)1月30冊を対象に1箱分を出すけど、1月5冊から10冊買う本で差し引きの計算になる。多分、この方式は私に優し過ぎるので若者達の支持を得られない公算が高いが、まずはできることからするのが無理のないところである。
注)ココログの管理ページからの検索は使えることが分かった。しかし、読者はどうなる? スマホからは使えない。
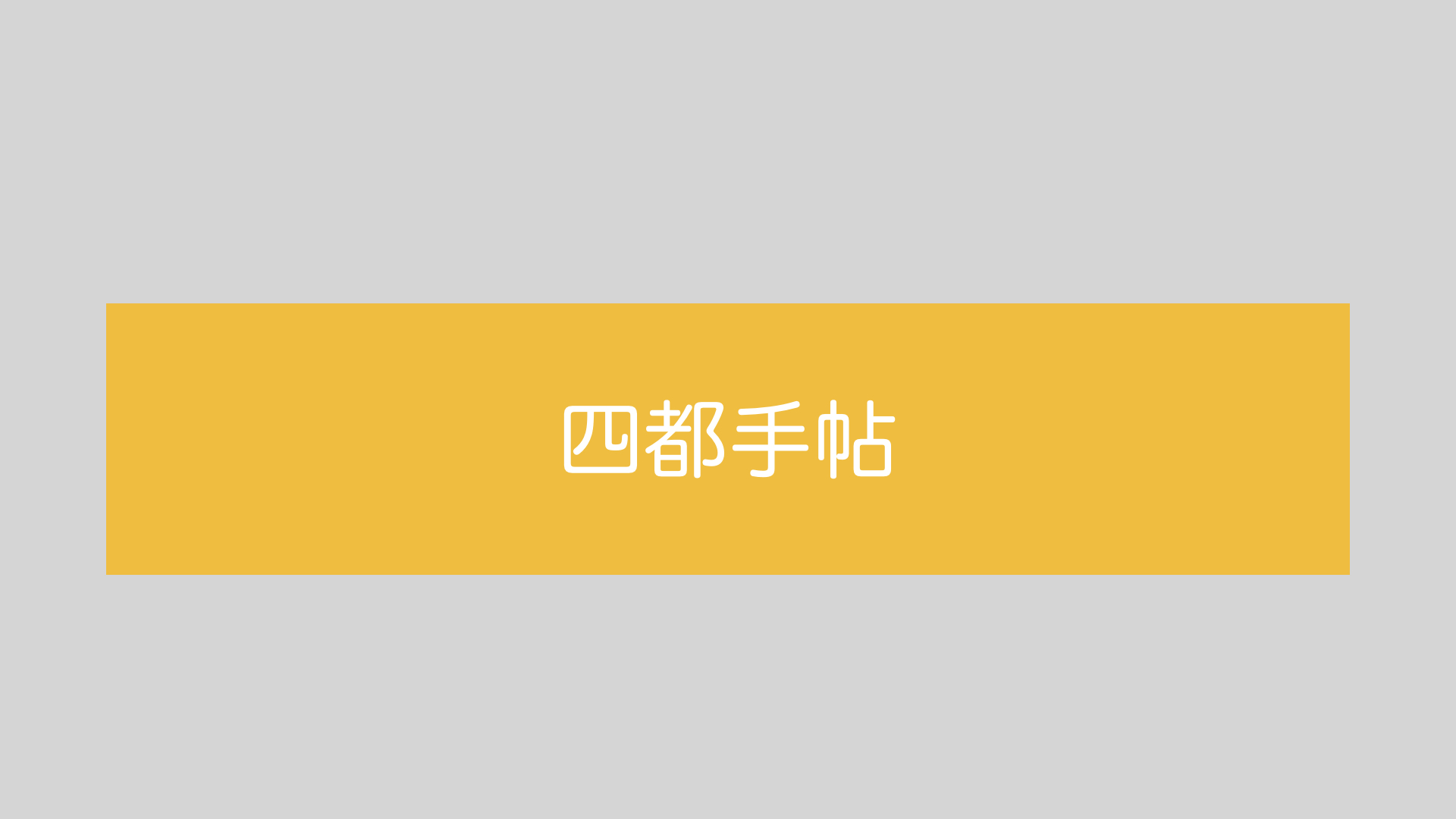

コメント