奈良その奥から二 「儀式の解読」
岡本彰夫 『ひととき』2018年12月号
春日大社の元権宮司の岡本彰夫氏が「春日若宮おん祭り」について『ひととき』2018年12月号に書いていました。この祭礼で神楽などとともに「田楽」が奉納されますが、おん祭りの田楽は世襲となっていて、たとえば「高足(こうそく)という芸は「十文字に組んだ棒に片足を掛けて、袖を大きく上げる。これは元々曲芸の一種で、この棒の上に乗って飛び跳ねるという芸を儀式化したもので」す。「因みにこの姿が豆腐や茄子を串に刺して焼き、味噌をつけて食べる料理に似ていることから、これを「でんがく」と呼んだ」といいます。なるほど味噌田楽の名の由来でしたか。知りませんでした。
ここで岡本彰夫氏は「棒に足を掛けて袖を翻すだけの簡素な芸」について、「もし曲芸の高足に拘っていたならば、熟練したプロにしか、この芸は伝承出来ず、いつしか歴史の波浪に呑み込まれ、その存在すら判らなくなってしまってしただろう。しかしこの芸を儀式化した事により、誰もがこれを行えて、かつての姿を後世に留める事が出来た」と「儀式化」の意味を読み解いています。
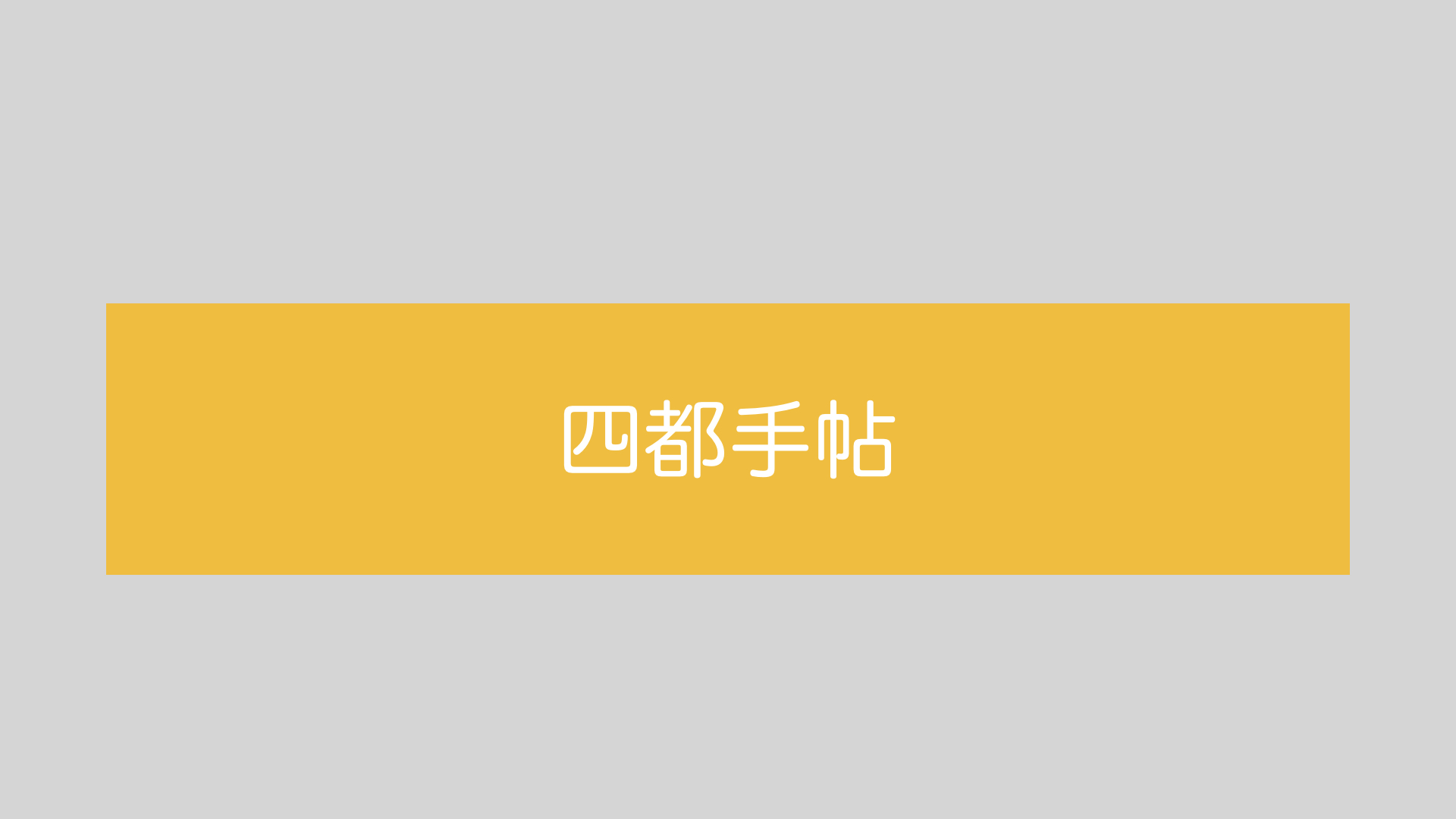

コメント