山紫水明処に伺う。12月から3月まで休んでいた。相方が往復葉書で見学の予約をしてくれたのだ。
正式には頼山陽書斎山紫水明處という。
鴨川に架かる丸太町橋を西に向かい歩くと国定史跡頼山陽書斎山紫水明處の標石(昭和58年9月)があり、この北 右側とある。北へ向かいすぐ突き当りを右側へ行く。道は北側へ折れ、暫くして右手に頼山陽山紫水明處の標石が立っているのが見えた。通りの引戸を引いてから細長いアプローチを進み、中門を潜ると茅葺屋根の建物が見えた。露地の濡れて光る飛び石を苔を踏まないように注意して伝いながら茶室のような離れに上がる。窓を開けていると風が冷たい。ガラスは泡を含んだもので当時は高価なものだったという。資料に沿って説明を聴きながら、頼山陽が脱藩しようとして幽閉されたことを思い出していた。
山紫水明處は頼山陽の水西荘の離れだった。水西荘が頼家の手を離れていた時期があり、明治の中頃に買い戻された。買い戻した当時、母屋を解体し、6軒の借家にし、書斎だけを残した。山紫水明處は戦前に鴨川の河床を下げたため、西の庭の湧き水も枯れた。京都の頼家は6代目と案内人が告げた。ちらっと見かけた女性がそうであるという。今は屋根も新しく拭かれて気持ちが良い。四畳半の北側に2畳の書斎と半坪の板敷があるだけの小さな離れである。四方に戸があり、二重になってる。雨戸の一部に自動ロックの仕掛けがあった。この離れは頼山陽が晩年を過ごしたところだ。炉も切っていなかったのだろうか。ここで夕方から酒を飲んでいる姿が想像された。鴨川寄りは廊下もあり栗の欄干となっていているのが中国風である。書斎の中の書はレプリカであった。天井がヨシを漆仕上げしたもので、何とも趣味にあふれた離れである。
西側は庭であるが、真ん中に枯れた井戸があり、石組が下がっていく造りとなっている。降り井という。こんな庭は初めて見た。相方はハイヒールにも関わらず大胆にも石組を伝って降りていって底の井筒を覗き込んだ。「壺中天」という言い方があるとすれば当に「井中天」を味わうためだったのか。好奇心は若さの秘訣であるともいう。羨ましく思うのだった。降り井は頼山陽の趣味ではあるまい。手入れのされた庭に当時から残るのは棗の木であるという。ぼうぼうたる想いを一首にこめて供えることにした。
山近し 紫の雲 水に映え 明かるさをます 處處の庭石

かつて三本木は花街だった。

山紫水明處の全景

当時は欄干の下まで鴨川だった。

離れから降り井を臨む
注)
三本木は旧花街で、大田垣蓮月の生まれたところだ。
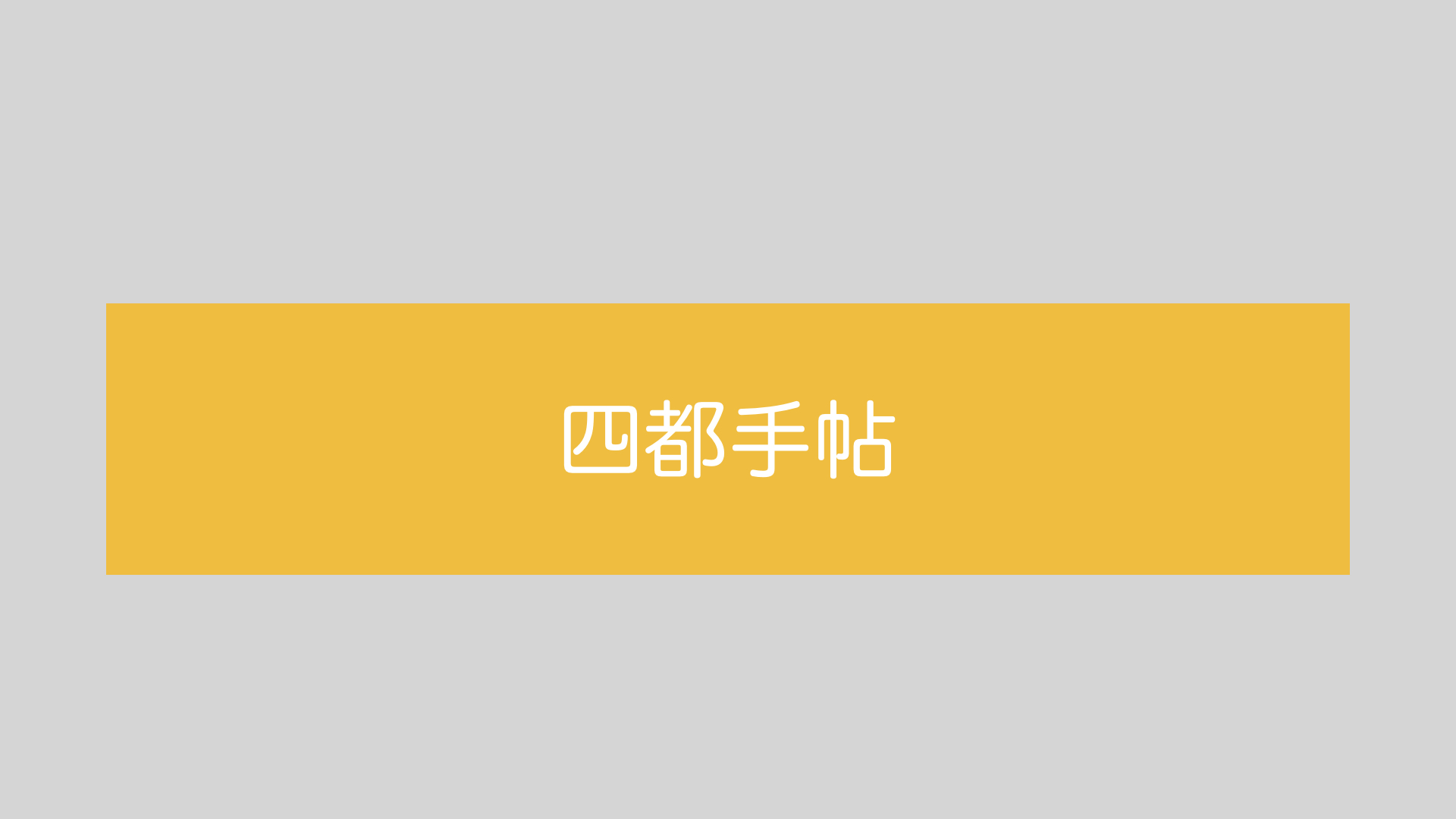

コメント