光村推古院編集部『京都手帖2017』光村推古院、2016年
京都手帖を買うのも10冊目となった。最初の年のは買っていない。「京都を持ち歩くスケジュール帳」というコピーにも関わらず、近年は持ち歩かないのだ。
京都手帖は買ってくると、まず今月のおすすめを見る。次に微妙なところを見る。
都をどりの日程の変更の発表が間に合わなかったか(京都手帖の予定は2016年6月現在)、4月1日〜23日となった悲しい情報が載っていないことは良いことかもしれない。
顔見世も今年の12月は先斗町歌舞練場で行うことは載っていたが、2017年は載せていない。
赤山禅院のへちま加持は名月に合わせるので2017年は10月4日だ。
京都の祭は日が決まっているものが多いのでカレンダーになりやすい。近年は休日に寄せるものもあり、4月の第2日曜日に今宮神社でやすらい祭がある。
以前は春秋限定と事前申込制だった一般公開が通年化した京都御所はどう表現したか見ようとしたら、載せていない。ちなみに、2016年版は例えば「京都御所春季一般公開(上旬の約5日間)と欄外に記載していた。京都御所通年公開の情報がどこにもないと京都御所は見落とされる可能性が出てくる。京都御苑の項ではだめなのだ。
通年公開となると土産物が気になる。秋季一般公開のときに皇室カレンダーを買うのを楽しみにしていた。菊葉文化協会から平成29年版が発売開始されているが、京都御所へ紅葉の時期に(一般公開の時期では紅葉に早かった。)参観して確認してみたい。
京都もたまにしか行かなくなって、しかも、来れば毎度お馴染みのパターンになると、手帖は本当に書き込めるのがいい。四都手帖としては、京都手帖に載っていない情報で自分が使う情報をデジタル化して持って行くので、現場で使わない京都手帖は持ち歩き不要である。
やはり、買ってきて、パラパラめくり、京都の四季を味わい、空想の旅を堪能したら、本箱行きでよい。正しくは、週刊新潮のようにブログのネタにするためだけに買っているようなものだ(笑)。今回も十分に楽しめた。
いつも思うのだが、観光地図に工夫が欲しい。愛宕神社、大悲閣千光寺や月輪寺は社寺データにあるが、地図にはない。このあいだ行った志明院などは社寺データにすらない。いずれも京都市所在である。
そもそも京都手帖の「京都」は何を指すのか明らかでない。したがって、掲載基準も不明である。このあたりは大人の事情もあるだろうが、この曖昧なところが京都らしくて良いということで支持されているのであろうか。惰性で買っている身としては、本の片付けの時期に処分されても抵抗はしない。
井上章一氏は宇治に住んでいるが「京都」にアンビバレントな感情を抱いていると思われる『京都ぎらい』(朝日新書、2015年)を書いた。この「京都」は洛中と呼ばれる京都中心地に住まいする人びとの「京都中心思想」のことであった。
光村推古院の編集部には色々と聞いてみたいことが多い。大垣書店さんで『京都手帖で遊ぶ』みたいな発売記念イベントとかしないのかなあ。
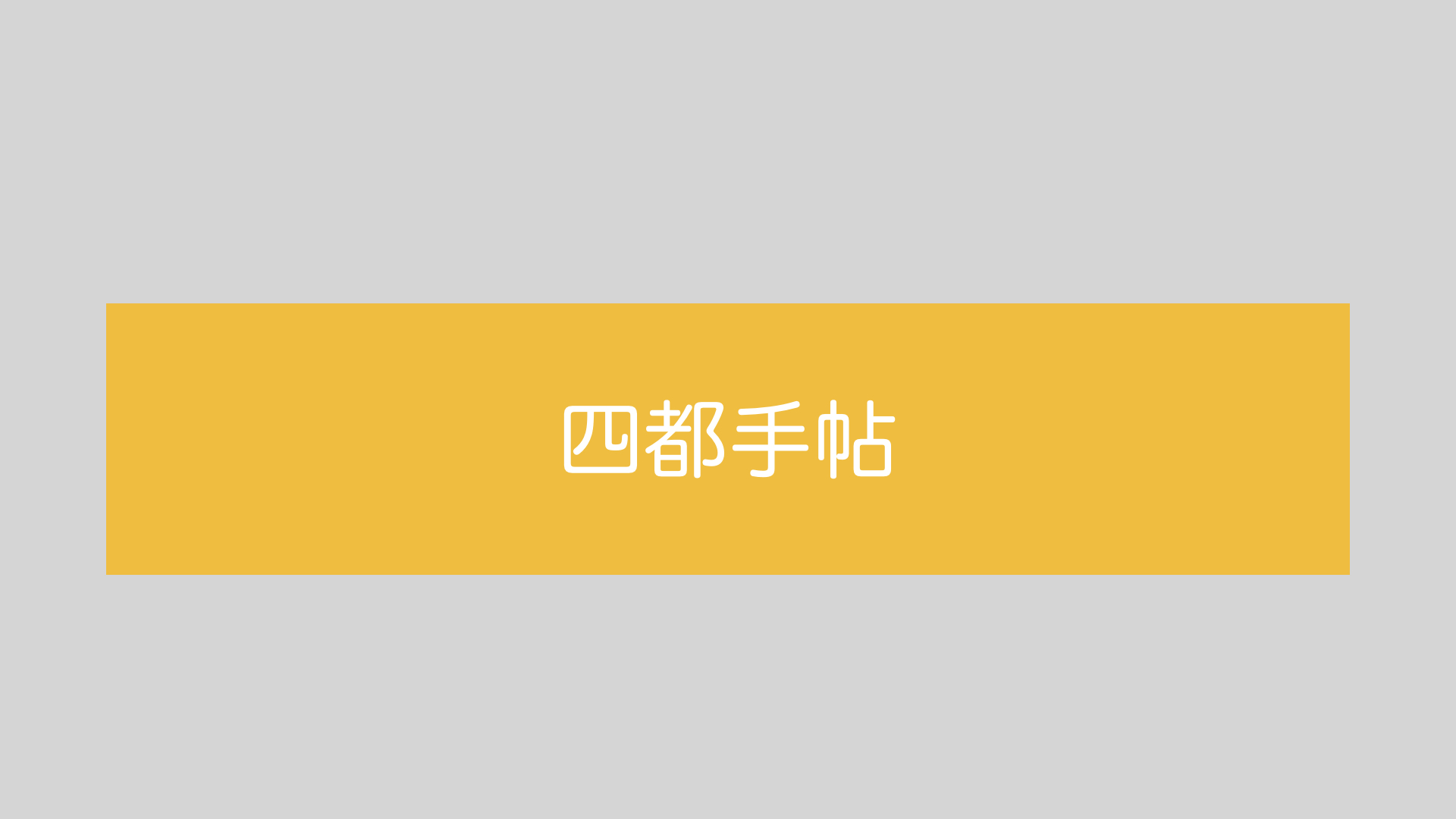

コメント