先日、蛸島彰子先生に稽古つけていただいたのを契機に、将棋の駒落ちのお浚いをしている。定跡とされている手順の意味について駒の働きの観点から見直してみたい。最近の棋譜はネットで手軽に入手できるが、ほとんど解説がないうえ、上手のテクニックを知るには役立つが、定跡から離れた過ぎている戦法は、それで上手に勝てるのであれば手合違いとしか思えないものが多くあまり参考にならない。木村義雄十四世名人の『将棋大観』がなかなか探しだせないので、見つけた本をまずは活用することにする。
大山康晴二段が升田幸三六段に角落ちで勝った棋譜が『大山康晴名局集』の第2局に載っていたので並べてみた。下手矢倉で上手が7二金から右金を繰り出す形であっった。「現在は上手5二金右と上がって、この金をいつまでも動かさない作戦が多く見受けられる。その狙いは、普通に攻め合っても、角がないのが大きいから、下手にコツを覚えられると、とても上手が勝てない。だから、徹底的に待つ方針を採り、下手のミスを誘おうという魂胆なのである」(p.23)。
蛸島先生もその方針であった。そこで上手の右金と下手の右銀を交換させる方針で指してみた。上手の右金が下手の右銀と入れ替わり大勢は決したようだ。上手の左銀が2四に上がったときの措置や9筋の端歩を受けるか否かについて研究が足りていないことがわかったので、今後も棋譜を並べながら検討していきたい。
注)大山康晴『大山康晴名局集』マイナビ、2012年
自戦記100局と名人戦順位戦解説82局のうち、駒落ちは1局のみである。
勤めていた会社を辞めた時期の本なので、のんびり余生を過ごそうと思ったのだろうか。10年も経ってようやく手にしてるのは、気まぐれでしかない。
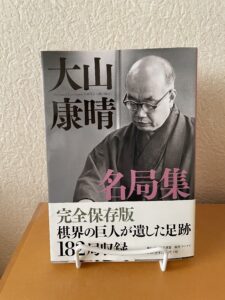


コメント