kindle版『吉田健一 池澤夏樹=個人編集 日本文学全集』のなかの『文学の楽しみ』にT.S.EliotのThe Waste Landのことが書いてあって、エリオットの『荒地』を岩波文庫の岩崎宗治訳で読むことにした。
吉田健一がエリオットの詩について書いているのが、いつものように切れ目がない。旧仮名遣いでないのが残念だが、旅の夜には他の選択肢はない。
「エリオットが使った言葉に温かみが籠っていてそれが我々にも伝わり、その言葉が響きを生じて我々を魅了し、そのためテエムス河の秋の荒んだ景色が優雅な一つの影像に変って、それで詩という普遍的なものがエリオットの個別的な作品にその存在理由を与える訳であるが、字引で優雅という言葉を引いても、その説明に、エリオットの「荒地」の第三部とは出てこない。それでどうしても神様に助けを求めることになって、「荒地」の第三部はどうでもよくなるのである」。
吉田健一は「文学は学問ではない」というテーマで書いている。「要するに、人間を文学に引き寄せるものが足りない大学の教授や講師がそれを補う方法もないので、文学を真面目に、文字通りに取る方に傾き、その考えを書いて批評家にもなった」とし、エリオットの亜流を批判している。
私の興味は言葉のもつ温かみにあって、それが「荒地」の第三部に現れているとしたら、分かるのかどうか知りたかったのであった。第三部はTHE FIRE SERMON「火の説教」だ。「火の説教」は原注には仏陀の「火の説教」とある。訳注では仏陀の伽耶山での説教を指すとある。教説に深入りするのが趣旨ではないので、この解説はまたいつか書くことにして、テエムス河の荒んだ秋の景色に戻りたい。
岩波文庫の『荒地』の岩崎宗治訳で読んでみる。
河辺のテントは破れ、最後の木の葉の指先が
つかみかかり、土手の泥に沈んでいく。風が
枯葉色の地面を音もなく横切る。妖精たちはもういない。
美しいテムズよ、静かに流れよ、わが歌の尽きるまで。
川面に浮かぶ空き瓶も今はない。サンドイッチの包みも、
絹のハンカチも、ボール箱も、煙草の吸殻も、
もっとほかの夏の夜の証拠品も。妖精たちはもういない。
彼女らの男友達、シティーの重役連の彷徨える御曹司たちも
いなくなった、住所も残さないで。
原文
The river’s tent is broken:
the last fingers of leaf
Clutch and sink into the
wet bank. The wind
Crosses the brown land,
unheard. The nymphs are
departed.
Sweet Thames, run softly,
till I end my song.
The river bears no empty bottles, sandwich
papers,
Silk handkerchiefs, cardboard boxes,
cigarette ends
Or other testimony of summer nights. The
nymphs are departed.
And their friends, the loitering heirs of city
dirctors;
Departed, have left no adresses.
ここでは、火の説教はまだ始まってない。しかし、優雅さを味わうことはできて、エリオットが夏のテエムス河で見られたものの痕跡もないと歌うところが良い。荒涼たる景色とは生の証の不在を歌うことで極まる。現前の荒涼たる景色の中に彼彼女等の夏の夜を思い起こさせる力がある。
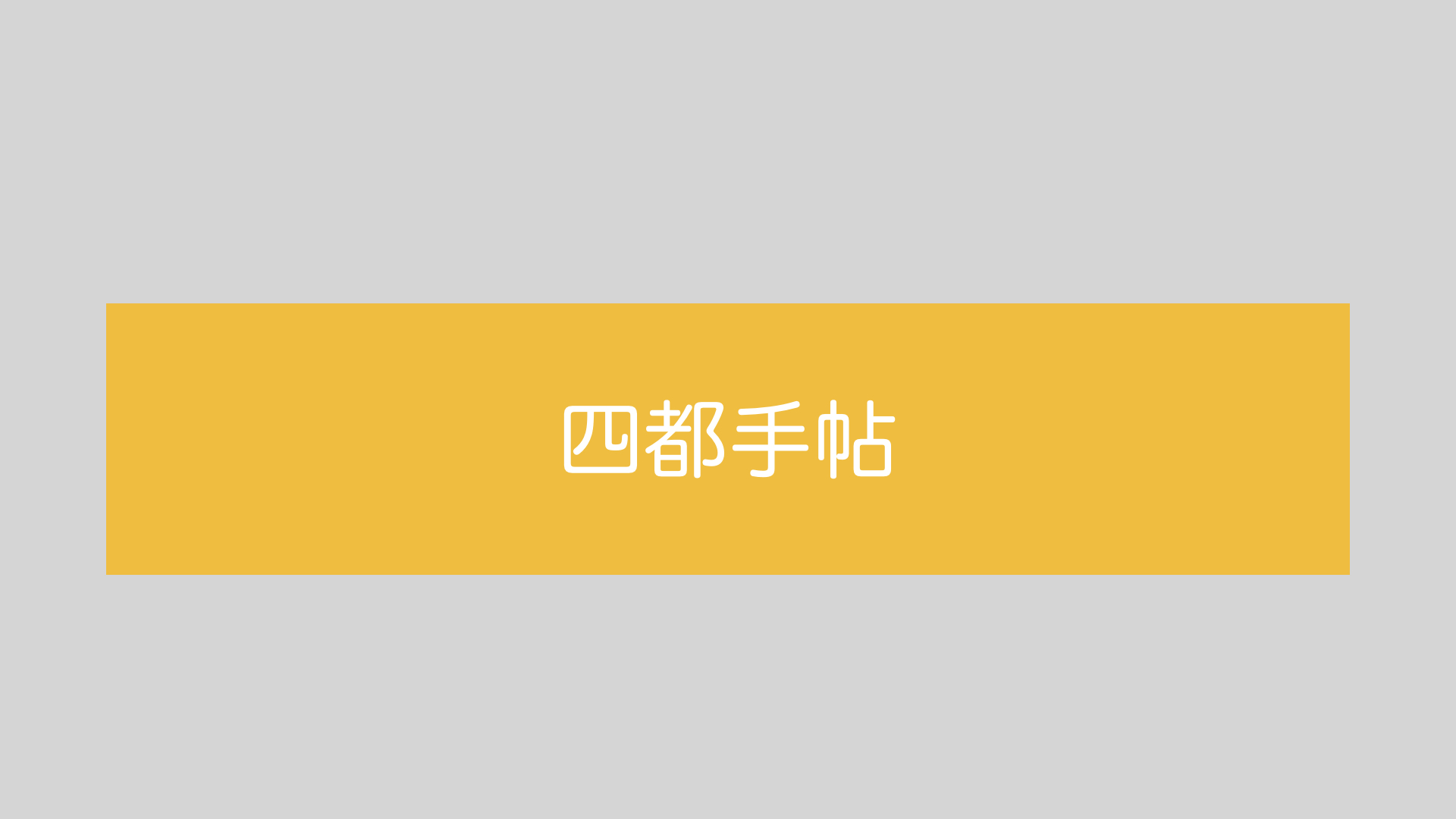

コメント